こんばんは。書くべき案件が溜まりすぎて更新が追いついていないただけーまです。オリンピック意外と面白いですね。ふと見たシンクロで感動してしまいました。
さてさて、今回は久しぶりに小説で更新。巷で話題の芥川賞受賞作、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』を読みました。
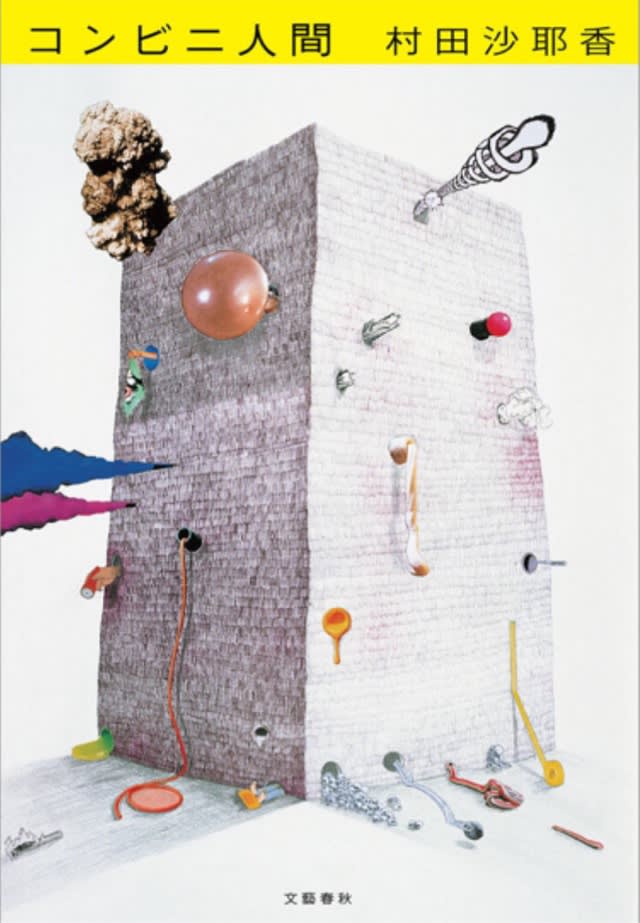
「コンビニの店員」としてしか生きられない合理主義を徹底する非人間的な主人公が、共有概念の浸透した社会で人間的な在り方を模索していく話。「社会に適合する」ということは一体どういうことなのか、改めて考えさせられるとともに、ソーシャル化が進んで価値の共有・画一化が進んだ社会を疑問を呈しているようでもあります。
コンビニでしか人間社会に適合できない「コンビニ人間」は果たして人間なのか、それとも別の何かなのか。人間という生物としては生きられないが、コンビニ店員という生き物であれば必要とされる、と語る主人公の言葉が印象的です。
そんな人間ではない生物「コンビニ人間」を象徴するのが、表紙に描かれた不気味な箱です。非人間的なモノが人間的に振舞おうとすることのグロテスクさが凝縮されたイメージ。味のある飲み物を飲む理由がわからないから白湯を飲む古倉さんの不気味な異常性が伝わってきます。
現代社会に潜むそうした不適合者と言われるような人物像を視点に据えることで、知らず知らずのうちに定義された「普通」に群がる周囲の登場人物たちが奇妙な生き物にさえ見えてきます。
非人間的な存在の視点から見れば、人間的な振る舞いは、「合理性に欠け、共有化された価値観を最重要視する」行動に映るわけです。
確かに無闇やたらにコンテンツをシェアし、「いいね」ボタンを押し、写真を投稿し、明確な境目を失った共有の集団主義は、新しい時代の到来というよりも、確かにムラ社会的であるのかもしれません。
妙齢にも関わらずアルバイトで生計を立て、交際相手も居ない、という主人公の状態が異常であると判断されるのは、多様化の容認が徹底されていないからなんでしょうね。
多様性を認めるポーズをとりながらも、多様性に対して排他的な普通という軸のある現代社会。芯のない人々を揶揄しているかのようです。
さてさて、今回は久しぶりに小説で更新。巷で話題の芥川賞受賞作、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』を読みました。
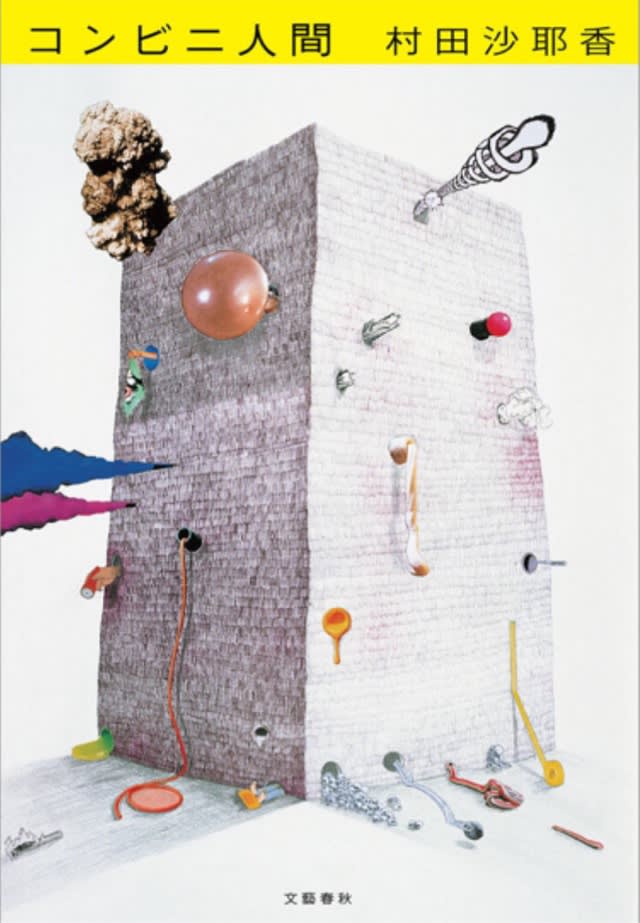
「コンビニの店員」としてしか生きられない合理主義を徹底する非人間的な主人公が、共有概念の浸透した社会で人間的な在り方を模索していく話。「社会に適合する」ということは一体どういうことなのか、改めて考えさせられるとともに、ソーシャル化が進んで価値の共有・画一化が進んだ社会を疑問を呈しているようでもあります。
コンビニでしか人間社会に適合できない「コンビニ人間」は果たして人間なのか、それとも別の何かなのか。人間という生物としては生きられないが、コンビニ店員という生き物であれば必要とされる、と語る主人公の言葉が印象的です。
そんな人間ではない生物「コンビニ人間」を象徴するのが、表紙に描かれた不気味な箱です。非人間的なモノが人間的に振舞おうとすることのグロテスクさが凝縮されたイメージ。味のある飲み物を飲む理由がわからないから白湯を飲む古倉さんの不気味な異常性が伝わってきます。
現代社会に潜むそうした不適合者と言われるような人物像を視点に据えることで、知らず知らずのうちに定義された「普通」に群がる周囲の登場人物たちが奇妙な生き物にさえ見えてきます。
非人間的な存在の視点から見れば、人間的な振る舞いは、「合理性に欠け、共有化された価値観を最重要視する」行動に映るわけです。
確かに無闇やたらにコンテンツをシェアし、「いいね」ボタンを押し、写真を投稿し、明確な境目を失った共有の集団主義は、新しい時代の到来というよりも、確かにムラ社会的であるのかもしれません。
妙齢にも関わらずアルバイトで生計を立て、交際相手も居ない、という主人公の状態が異常であると判断されるのは、多様化の容認が徹底されていないからなんでしょうね。
多様性を認めるポーズをとりながらも、多様性に対して排他的な普通という軸のある現代社会。芯のない人々を揶揄しているかのようです。










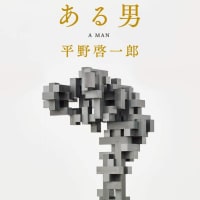









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます