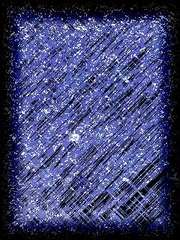今僕は、故郷に身を預けている。
カーテンを開け、窓を開けると、一面銀世界で、いつの間にこんなに雪が降ったのだろう?と驚くばかり。この町に降る雪も年々少なくなっているようで、昔のように近所の人が集まって雪かきをしたり、塩カル(雪を溶かすカリュウム)をまく機会も減ってきた。
家は山の途中にある為、雪が降ると決まって車を坂の下に止め、歩いて家に帰ったものだ。しかし挑戦的な父親はいつも車で山を登ろうと挑んでいた。
しかしそのたび、坂道の途中でタイヤは空回り。家族はその車のケツを押して登らせる。何時間もかけて、家に到着させるのだ。母親は、夫を叱り、父親はスマン、スマンと苦笑い。
そんなやり取りも、雪が降らない限りは行う必要もないのだ。
いつの間にか、老いてく両親に気付く。
そんな両親に生を執着させようとする自分がいる。余計なお世話かもしれない。きっと受け入れがたいのかもしれない。それでもそれは愛であるかもしれない。
僕達を繋ぐモノ。姿や形ではなく。
それは間違いなく瞳には写らない、でも確実に握り締めている温もりであろう。
夜が来て、降った雪は、もう融けている。
カーテンを閉めて。
少し温もりを握り締めて。