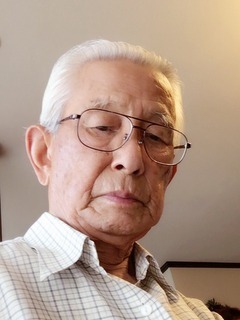10月23日 (木) 
陰鬱な秋雨の日が続く。こんな日は「徒然草」ではないが「つれずれなるままに日暮し硯」ならぬパソコンに向かって「移りゆくよしなしごとを書き綴る」心境になる。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
2週間ほど前だったか、NHKの番組の中で最近の老人学Gerontologyで使われるようになったという「老年的超越」という言葉を初めて聞き知った。
「老年的超越」Geotranscendenceとは、85歳頃から90歳台にかけての所謂「超高齢者(スーパー・シニア)」がその身体的機能の低下に係らず、その置かれた現状を肯定的に捉える感情というか日々の生活への満足感が高くなる心理状態をいうものであるらしい。
この言葉に関心を持って調べてみところ、スウェーデンのトルンスタムTornstamという社会学者が近時急速に増加してきた百寿者の調査を通じて導き出した「老人学」上の理論とのことで、わが国でも近時これに基づく調査研究が進められ次第にその事実が実証されつつというものであるらしい。
これまでの老人学におけるエイジングのモデルは孤独、喪失、不健康、孤立、無視などといったマイナスイメージを伴うもので、サクセスフル・エイジングのモデルといえば「身体的機能の維持」「社会活動への参加」などを視点をおいて語られてきていたが、「老年的超越」はこれを見直す老人学理論で、80歳、90歳を境に高齢者がそれまでの価値観が質的に転換しこれまでとは違った「豊かな精神世界に生きる」ようになるというのである。
超高齢者に近づいた私としては「身につまされる」理論であり、無関心には聞き流せないので、インターネットでこれに関するサイト、PDF文書でのいくつかの研究論文まで拾い読みしてみた。
「物質的で合理的な世界観から、宇宙的で超越的な世界観へのメタ認識における移行」などえらく難しい表現に出会うと戸惑ってしまうが、いろいろ難しい理屈はべつにして実証的に得られた結論めいたものだけを私なりに勝手に理解してみれば、おおむね次のようなものと考えたい。
〇死が怖くなくなり、生と死に対する新たな認識が生じる。
〇日々の生活における些細な経験に喜びを感じるようになる。 (「多幸感」)
〇自己中心的な考えから解き放たれ幅広い他利的な考え方や寛容な気持ちが増す。
〇衰退する身体的健康、身体の在り方に必ずしも執着しなくなる。
〇それまでの社会的慣習にとらわれなくなり、自由な心を得る。
〇現世的・世俗的なものから精神的・宗教的なスピリチャルなものへの関心が高まる。
「老年的超越」とは、選ばれた特定の超高齢者に見られる特徴ではなくて、一部の例外はあるもののすべての高齢者が加齢に伴って発達していく特徴で、普遍的なものだという。
そういわれれば、85歳からという超高齢者といってもいい私も我が身に照らしてみて、これらのことにはかなり納得しうるところがある。
もともと私は生来楽天的な性格だったようで、なんでも肯定的に捉える所謂「オメデタ人間」のようだが、歳を重ねるに伴い特に最近では些細な事にも幸せを感じる心理状況に近付きつつあることを自覚しており、また、己の「死」も平静に受け止める心境が強まってきている。
いつも「多幸感」に包まれているとまでは言わないが、客観的機能側面での低下・衰退にも係らず主観的幸福感に低下がみられていないことは確かである。
(これは、ひょっとしたら昔からよく言われる年寄りの「呆けの心境=恍惚の境地」に通じるのかもしれないが、そう言ってしまえば身も蓋もないことになる。しかし、マイナス評価としてでなく、プラス面でみることの方が我々超高齢者を勇気づけることは間違いない。いずれにせよ、これから老いの道をひたすら進むことになる私にとって「老年的超越」という言葉の響きには悪い気はしないし、気分の上でも老いの足取りを支えるしっかりした杖になりそうである。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
そんなとき、たまたま毎年1回東京駅に隣接する大丸12階「たん熊」で行なってきている「所属組織のOB会」に10/16出席したときのことを思い出した。
この会合は20年も前から欠けることなく続けられてきているもので、今回の出席者は12名、近く85歳となる私を最年長としていずれも後期高齢者ばかりの会である。
そこでの話題となったのは、かつて身を置いた組織に係る話はなく、もっぱら最近の年金生活での自足した暮らし向きに関するものばかりであった。
それぞれの最近身に起こった「病気」の話も、深刻には語られず淡々たる話しぶりであったし……。
「老年的超越」を云々する80歳台はこの会ではまだ少数派だが、それでも以前のような現世的・世俗的な生々しい話題(棋院7段の免許を得たとか、大学の学長に就任したとか、100名山を踏破したとか、若い夫人を得たとか)は出なかったことは、皆がいずれ迎える「老年的超越」を前に徐々にではあるが現状を是とする穏やかで寛容な思考での立ち位置に移りつつあることを感じさせられた。















































 /
/