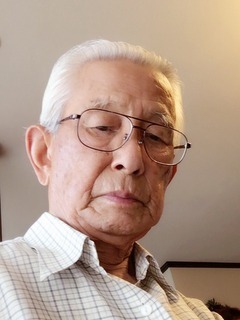1月15日午後、何気なく血圧を測定したら上が200、下が100を超えているのに愕然とした。
私の血圧は、下はおおむね80台でいつも安定しているが、上は必ずしも安定的でなく140-160、時には180くらいになることもあったが、200をこえるようなことはこれまでなかったことである。
この数値を見た途端、急に頭がぼーっとし、頭痛みさえ感じるようになった。これはもっぱら心理的影響によるものであったろう。
血圧については、当地に来てから10数年も医者の言われるままに降圧剤を飲んできていたが、数年前に浜六郎「高血圧は薬で下げるな」を読んで、おおいに頓悟するところがあり降圧剤服用はきっぱりやめ、血圧管理はもっぱら運動と体重減で対処することにして、なんとか150-160くらいには収まっていたので、最近はあまり気にしていなかったのである。
しかし、上が200を超えたとなるとにわかに心配になってきた。そこで、改めて私の血圧管理のバイブルというべき浜docの本を引っ張り出して再読することになった。
そして改めて理解したことは、現状はさほど深刻な事態ではなく(時には200を超えることがあってもさほど心配することはない)、まあ言ってみれば、このところ少し緩んでいた血圧コントロールの意識を反省し、運動・食事への配慮を中心とした健康管理に一層気を引き締めねばならないということだった。
浜doc「高血圧は薬で下げるな」は極めて説得力のある本である。医学界では異端の説のようだが、現在のWHO・国際高血圧学会の2004年ガイドライン「140/90以上は高血圧、血圧を130/85未満を目標に下げよ」「高齢者も同様」というのがいかに欺瞞(降圧剤を使用させる)に満ちたものであるかを基礎となった原データを徹底的に調べ上げて論証(糾弾)している。浜docの見解に対する個人的攻撃はあっても、これを正面jから反論するものはないようだ。製薬会社となれあった医学界は無視はできても反論することはできないように私には思える。
ところで、私のとってなにより重要なことは「高齢者の血圧管理目標」である。
WHOガイドラインでは1993年の軽症高血圧者の治療指針は70歳以上は上180未満、下100未満であったのが、2000年には70-79歳は上150、下90、80歳以上が上160、下90と引き下げられ、さらに2004年は75歳以上も若年者と同様に上140、下90へ引き下げられたこと。つまり高齢者もすべて若年者と同一の血圧目標値になったことである。
これに関して浜docは「血圧の目安は、新基準ではまったく低く設定しすぎて話にならない…旧基準の160/90でもまだ低すぎる可能性が十分ある…75歳以上の高齢者なら、降圧剤の副作用を考えると180/100では降圧剤は必要ない…180/110を少し超えている程度でも慌てて降圧剤を使う必要はない」というのにある。
ついでながら、血圧測定について「血圧は自分で測る」とし、「日本の高血圧治療ガイドラインでも『少なくとも15分以上安静座位の状態』で測定することを推奨している」とあるが、降圧剤処方でこんな測り方をしている病院など皆無である事実も重要な指摘であると私は考える。病院での測定による降圧剤処方は全く当てにならない。
1993年基準を知っていた私は、かねてから高齢者、それも後期高齢者の血圧と若い人の血圧が同じ基準とすることには疑問を持っていた。
そんなこともあり、今回はインターネットで調べてみたらこんな記事が見つかった。
東洋大学医学部(医療統計学)大櫛陽一教授の次の文章である。
「全国約70万人の検診結果から求められた(結果)、男性の最高血圧の上限値は20~39歳まで145mmHgと一定であるが、その後60歳まで直線的に上昇して、165mmHgでほぼ一定となる。 女性は20~34歳まで130mmHgであるが、その後65歳まで直線的に上昇して、165mmHgでほぼ一定となる。男女とも中高年での最高血圧は、160mmHgまでは正常範囲ということである。
血圧が年齢に伴って上昇するのは生体にとって必要な変化である。加齢に伴い血管の弾力性が少なくなることは避けられないため、血圧を上昇させていくから」
※ 結論は現状から降圧剤を飲む必要はまったくない。血圧コントロールのためには運動・食事・体重に気をつけること。









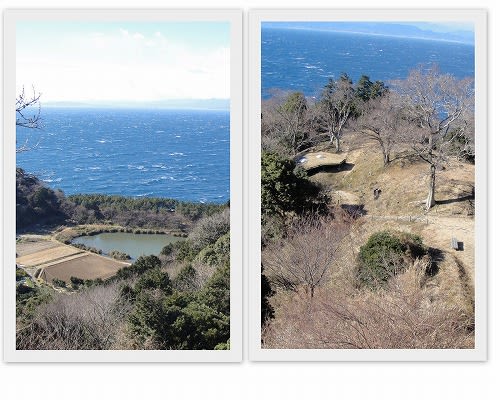































 /
/

































 -
-