当院は病院の移転再構築の計画がある。
いつまでたっても全体像が見えてこないので私なりの青写真をつくってみました。
プロダクトイノベーションよりはプロセスイノベーションが中心です。専門的な内容、ハード的なアイディア、それぞれを実現するプロセスについてはここでは割愛します。
再構築にあたって、当然作られるであろう、高度医療センターや地域医療センター、ER型救急外来、緩和ケア病棟や、回復期リハビリテーション病棟、外来化学療法部門などはあえてあげません。
提案は、各自が「できる医療」、「やりたい医療」をやるだけの状態から、本来の住民のニーズが反映され、よりよい地域医療体制を、地域住民とともに考え、育てていくための仕掛けが中心です。
--------------------------------------------------------------
2009年に高度医療センターの移転工事開始、2010年に移転を完了するために2007年度から本格的に組織、機構の再編成を始める。(様々な事情で少々前後するのは構わない。JFKのアポロ計画みたいに、とりあえず、そう決めちゃってそれにむけ準備をすすめていく。そうしないと絶対に実現できません)
●もはや情報化は避けて通れません。しかし上手にやらなくてはいけません。本格的な電子カルテ、院内情報システムの導入に向けネットワーク上での情報共有の仕組みを準次整備していく。2007年度から本格運用。全面電子カルテ化は移転後(ITシステムに予算を投入する。各職域にITスペシャリストをおき、そのための勉強、資格取得、情報交流を支援し職員のITスキルを戦略的に高める。電子カルテの規格統一をにらみながら、IT企業と組んで独自に斬新な電子カルテを開発する。)
●電子化の準備、医療の標準化、情報共有のためにクリニカルパスの作成、使用をさらに推進する。
●地域との連携、診療所や他院、開業の医師、職員との情報共有、勉強会、ヒューマンネットワークの構築を積極的におこなう。地域の限られたスペシャリストの技術、知識、経験を最大限活用するために、各専門科が中心となって、地域全体の医療のレベルアップをはかり、(連携室、各専門科)地域診療所や開業医と共通の電子カルテシステムを導入し、地域循環型医療連携システムを確立する。(これも移転再構築時に本格始動)
●地域住民や患者が主体的に自らの健康について考え、地域や医療のあり方を考えるのを支援するために、病院患者図書館、患者情報センター、総合的な窓口を行政と協力してつくり、患者会活動や地域活動を病院としてサポートしていく。(ハコは何でもいい。すぐに始める。ここが全てのカギとなると思います。)
●患者情報センターとも協力しながら、病院、地域からの情報発信、交流のために病院としてのメディアをもつ。IT部門、出版社、放送センター等、WEBももっと活用していく。専門職員を配置したシンクタンクをおき農業問題、保険医療福祉、プライマリヘルスケア、国際問題等の情報収集、アセスメントをおこない、政策提言し政策決定に反映させる。(・・・保健医療福祉政策に翻弄される受身の姿勢ではなく積極的にデータをだして発信していく。S総研、通称レモン)
●高齢害、障害をかかえて暮らす人の増加に備え、年をとっても障害があっても自分らしく安心して地域で住みつづけ、天寿をまっとうできるようにするために、地域ケア、リハを戦略的に充実させ、福祉の充実を図る。
そのために病院、厚生連、JAの支援のもと、別組織をつくり、職員OBや、やる気のある職員にノウハウや医療、資金を提供し小規模多機能の居住福祉(できれば診療所や訪問看護ST、ヘルパーステーションなどと一体化して)、グループホーム、授産等、をつくる仕組み(ケアベンチャー支援体制)をつくる。(明日はわが身、今すぐにでも必要。ここまでいってこそ地域ケア)
●次世代を担う人材育成のために、看護大学、医科大学等の教育機関の設立。(これはすでに公表されている。農村医科看護大学)
●S病院にくる学生、インターンシップ生、研修生、就職希望者、医局派遣医師等を受け入れる窓口を一本化し、病院、地域の事情、歴史について学ぶプログラム、短期研修制度を作る。 (共通の認識、目標をもてるように。)
●地域医療を担える人材をそだて、僻地医療や農村医療のネットワーク作りのコンサルタント事業部をつくり全国の過疎地、それから中国をはめとする途上国の医療体制づくりを支援する。
これらのプロジェクトは全職員の中からやりたい人を公募し組織編成上、院長直属とし、期限を区切り成果をもとめる、組織横断的なプロジェクトチームで行う。そのための他の業務から開放される時間の確保が保証されなくてはならない。 またプロジェクトの進捗状況は全体に公表される。
一方、地域に必要な様々な技術の移転に関しては外部からのヘッドハンティングも積極的に行う。(目的をもった年俸性、予算をつける。)スカウト部門もつくる。(すぐに始める。)
それぞれの事務局機能を担える優秀な事務の人材が不可欠である。
これらのことは、基本的に南部、K分院を中心にモデルケースとして行い、そこで得たノウハウ、データを本院、新病院に移転する。(南部に優秀な人材を投入して自由にやってもらう。)
あとはリーダーのGOサインがでるのを待つのみ。
いつまでたっても全体像が見えてこないので私なりの青写真をつくってみました。
プロダクトイノベーションよりはプロセスイノベーションが中心です。専門的な内容、ハード的なアイディア、それぞれを実現するプロセスについてはここでは割愛します。
再構築にあたって、当然作られるであろう、高度医療センターや地域医療センター、ER型救急外来、緩和ケア病棟や、回復期リハビリテーション病棟、外来化学療法部門などはあえてあげません。
提案は、各自が「できる医療」、「やりたい医療」をやるだけの状態から、本来の住民のニーズが反映され、よりよい地域医療体制を、地域住民とともに考え、育てていくための仕掛けが中心です。
--------------------------------------------------------------
2009年に高度医療センターの移転工事開始、2010年に移転を完了するために2007年度から本格的に組織、機構の再編成を始める。(様々な事情で少々前後するのは構わない。JFKのアポロ計画みたいに、とりあえず、そう決めちゃってそれにむけ準備をすすめていく。そうしないと絶対に実現できません)
●もはや情報化は避けて通れません。しかし上手にやらなくてはいけません。本格的な電子カルテ、院内情報システムの導入に向けネットワーク上での情報共有の仕組みを準次整備していく。2007年度から本格運用。全面電子カルテ化は移転後(ITシステムに予算を投入する。各職域にITスペシャリストをおき、そのための勉強、資格取得、情報交流を支援し職員のITスキルを戦略的に高める。電子カルテの規格統一をにらみながら、IT企業と組んで独自に斬新な電子カルテを開発する。)
●電子化の準備、医療の標準化、情報共有のためにクリニカルパスの作成、使用をさらに推進する。
●地域との連携、診療所や他院、開業の医師、職員との情報共有、勉強会、ヒューマンネットワークの構築を積極的におこなう。地域の限られたスペシャリストの技術、知識、経験を最大限活用するために、各専門科が中心となって、地域全体の医療のレベルアップをはかり、(連携室、各専門科)地域診療所や開業医と共通の電子カルテシステムを導入し、地域循環型医療連携システムを確立する。(これも移転再構築時に本格始動)
●地域住民や患者が主体的に自らの健康について考え、地域や医療のあり方を考えるのを支援するために、病院患者図書館、患者情報センター、総合的な窓口を行政と協力してつくり、患者会活動や地域活動を病院としてサポートしていく。(ハコは何でもいい。すぐに始める。ここが全てのカギとなると思います。)
●患者情報センターとも協力しながら、病院、地域からの情報発信、交流のために病院としてのメディアをもつ。IT部門、出版社、放送センター等、WEBももっと活用していく。専門職員を配置したシンクタンクをおき農業問題、保険医療福祉、プライマリヘルスケア、国際問題等の情報収集、アセスメントをおこない、政策提言し政策決定に反映させる。(・・・保健医療福祉政策に翻弄される受身の姿勢ではなく積極的にデータをだして発信していく。S総研、通称レモン)
●高齢害、障害をかかえて暮らす人の増加に備え、年をとっても障害があっても自分らしく安心して地域で住みつづけ、天寿をまっとうできるようにするために、地域ケア、リハを戦略的に充実させ、福祉の充実を図る。
そのために病院、厚生連、JAの支援のもと、別組織をつくり、職員OBや、やる気のある職員にノウハウや医療、資金を提供し小規模多機能の居住福祉(できれば診療所や訪問看護ST、ヘルパーステーションなどと一体化して)、グループホーム、授産等、をつくる仕組み(ケアベンチャー支援体制)をつくる。(明日はわが身、今すぐにでも必要。ここまでいってこそ地域ケア)
●次世代を担う人材育成のために、看護大学、医科大学等の教育機関の設立。(これはすでに公表されている。農村医科看護大学)
●S病院にくる学生、インターンシップ生、研修生、就職希望者、医局派遣医師等を受け入れる窓口を一本化し、病院、地域の事情、歴史について学ぶプログラム、短期研修制度を作る。 (共通の認識、目標をもてるように。)
●地域医療を担える人材をそだて、僻地医療や農村医療のネットワーク作りのコンサルタント事業部をつくり全国の過疎地、それから中国をはめとする途上国の医療体制づくりを支援する。
これらのプロジェクトは全職員の中からやりたい人を公募し組織編成上、院長直属とし、期限を区切り成果をもとめる、組織横断的なプロジェクトチームで行う。そのための他の業務から開放される時間の確保が保証されなくてはならない。 またプロジェクトの進捗状況は全体に公表される。
一方、地域に必要な様々な技術の移転に関しては外部からのヘッドハンティングも積極的に行う。(目的をもった年俸性、予算をつける。)スカウト部門もつくる。(すぐに始める。)
それぞれの事務局機能を担える優秀な事務の人材が不可欠である。
これらのことは、基本的に南部、K分院を中心にモデルケースとして行い、そこで得たノウハウ、データを本院、新病院に移転する。(南部に優秀な人材を投入して自由にやってもらう。)
あとはリーダーのGOサインがでるのを待つのみ。










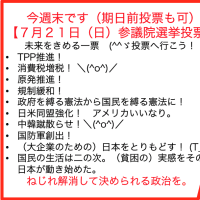
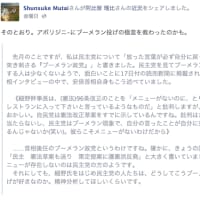




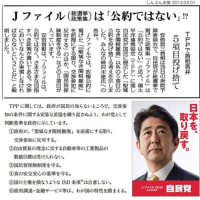

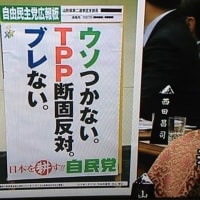

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます