
かつて、尊敬する指導医の先生に「おまえの問題はパニクることだ。」と指摘されたことがある。
いまになってなるほどと思う。
パニックこそ自閉系の特徴なのだ。
いまでも、さまざまなことがこなしきれずに情報や仕事がオーバーフローするとしょっちゅうパニクっている。
特に構造化(わかりやすく、間違いにくい環境にすること。)が遅れている医療現場では間違えないように仕事を行うために注意力をもとめられるから辛い。
なにか判断をするには十分な情報に基づいてやらないと不安なたちなのだが、情報技術が活用されておらずカルテや資料がバラバラな病院では、情報はあちこちに四散しており集めるだけで一苦労。
そんな不十分な情報のまま瞬間的な判断を求められることも多い。
理不尽な要求も多い。
感情を揺さぶられるような出来事も多い。
患者さんや家族の心情にも配慮しなくてはならない。
アリバイ的な書類、保険の書類など書類も山のよう。
そんななかで優先度をつけて、一つ一つこなしていくのみなのだが、どうしてみんなそんなことができるの?と思ってしまう。
外来、病棟と数多くの患者さんを少ない人数でみて、不平や不満も言わず淡々と日常業務をこなす先輩たち。
すばや医学的にも最善の対応を、疲れを知らぬタフネスさで行い、キビキビ動き的確な指示をテキパキだすことのできる同僚。
さまざまな手技や知識を次々とものにし、患者さんのところにもこまめに足を運び、信頼を得ている後輩。
劣等感の嵐が吹き荒れる。
自分でも精一杯、理想と現実のギャップに悩みながらつねにベストエフォートで頑張るのみなのだが。
あるキャパ(限界)を超えると、オーバーフローし頭はフリーズして(凍りつき)パニックになる。
たとえば、さまざまなことに追い立てられながら患者さんと深刻な話をしているとき、緊急の対応をしているときなどに限って電話がかかってきて判断をもとめられる。
こういった状況では容易にパニックになる。
電話(PHS)はかけるのも受けるのも嫌いだ。
気を使うし、気を使わせる。
こっちの都合などお構いなしに飛び込んでくる。
秘書でもおいていったんバッファーとするか、緊急度別に判断できるような仕組みがあればいいのだが・・・。
電話が鳴り、電話を受けて、
「いま電話いいですか?」
といわれても、電話をうけた時点でやっていたことの流れが中断されてしまう。
(心の中で「イライライラ、もういいよ、で?」)
そして電話をきると、今までしていたことを忘れてしまう。
集中力がチャージされるまでしばらく時間がかかる。
能率はあがあずイライラは増幅される。
対応としては
朝、夕のミーティングで必ず顔をあわせるなど、コミュニケーションをよくする。
スタッフの緊急度判断の域値、対応能力を上げる。
あいまいな支持を出さない。
自分の予定を明示する。
これらのことで電話の使用を減らすことはできそうだ。
さて、パニックにとは「恐怖や混乱による一時的なコミュニケーションレベルの低下、さらにそれによる不適切な行動」と定義してみる。
だからパニックのときは人と話さずに、引きこもる。
うっかりそんなときに余計なことを言わないほうがいい。
怒ったり、泣いたり、周りの人からみると何をしているのかわからないだろう。
わけのわからないことを口走ってしまうかもしれないし
逆ギレして無用の怒りを買って傷口をひろげてしまうかもしれない。
じっと嵐が過ぎ去るのをまつ。
そんなとき泣きつらに蜂で、例のアレルギーバーストもおこりやすい。
すると目はかゆくて涙はでるは、胸とおなかはワサワサするわ、体は湿っぽくなって痒く、血が出るまでかきむしるわ、気分はわるくなっておきていられないわで大変である。(アナフィラキシー)
あわてて頓服の薬をのんでなだめる。
冷たい缶ジュースを買って、火照った体にあて冷やす。
落ち着くまで、しばらくはコミュニケーションも低下し、体の具合も悪く血だらけなので人のいないところに引きこもる。
しかしそうもいっていられないこともある。
そんなときは深呼吸する。
「スーハ、スーハー」
荒れ狂う自律神経をなだめ、こころを落ち着かせる。
つくづく自分をコントロールするのは難しい。
まわりをコントロールするのはもっと難しい。
自分を操縦法を身につけるとともに、環境の構造化をすすめていきたい。
いまになってなるほどと思う。
パニックこそ自閉系の特徴なのだ。
いまでも、さまざまなことがこなしきれずに情報や仕事がオーバーフローするとしょっちゅうパニクっている。
特に構造化(わかりやすく、間違いにくい環境にすること。)が遅れている医療現場では間違えないように仕事を行うために注意力をもとめられるから辛い。
なにか判断をするには十分な情報に基づいてやらないと不安なたちなのだが、情報技術が活用されておらずカルテや資料がバラバラな病院では、情報はあちこちに四散しており集めるだけで一苦労。
そんな不十分な情報のまま瞬間的な判断を求められることも多い。
理不尽な要求も多い。
感情を揺さぶられるような出来事も多い。
患者さんや家族の心情にも配慮しなくてはならない。
アリバイ的な書類、保険の書類など書類も山のよう。
そんななかで優先度をつけて、一つ一つこなしていくのみなのだが、どうしてみんなそんなことができるの?と思ってしまう。
外来、病棟と数多くの患者さんを少ない人数でみて、不平や不満も言わず淡々と日常業務をこなす先輩たち。
すばや医学的にも最善の対応を、疲れを知らぬタフネスさで行い、キビキビ動き的確な指示をテキパキだすことのできる同僚。
さまざまな手技や知識を次々とものにし、患者さんのところにもこまめに足を運び、信頼を得ている後輩。
劣等感の嵐が吹き荒れる。
自分でも精一杯、理想と現実のギャップに悩みながらつねにベストエフォートで頑張るのみなのだが。
あるキャパ(限界)を超えると、オーバーフローし頭はフリーズして(凍りつき)パニックになる。
たとえば、さまざまなことに追い立てられながら患者さんと深刻な話をしているとき、緊急の対応をしているときなどに限って電話がかかってきて判断をもとめられる。
こういった状況では容易にパニックになる。
電話(PHS)はかけるのも受けるのも嫌いだ。
気を使うし、気を使わせる。
こっちの都合などお構いなしに飛び込んでくる。
秘書でもおいていったんバッファーとするか、緊急度別に判断できるような仕組みがあればいいのだが・・・。
電話が鳴り、電話を受けて、
「いま電話いいですか?」
といわれても、電話をうけた時点でやっていたことの流れが中断されてしまう。
(心の中で「イライライラ、もういいよ、で?」)
そして電話をきると、今までしていたことを忘れてしまう。
集中力がチャージされるまでしばらく時間がかかる。
能率はあがあずイライラは増幅される。
対応としては
朝、夕のミーティングで必ず顔をあわせるなど、コミュニケーションをよくする。
スタッフの緊急度判断の域値、対応能力を上げる。
あいまいな支持を出さない。
自分の予定を明示する。
これらのことで電話の使用を減らすことはできそうだ。
さて、パニックにとは「恐怖や混乱による一時的なコミュニケーションレベルの低下、さらにそれによる不適切な行動」と定義してみる。
だからパニックのときは人と話さずに、引きこもる。
うっかりそんなときに余計なことを言わないほうがいい。
怒ったり、泣いたり、周りの人からみると何をしているのかわからないだろう。
わけのわからないことを口走ってしまうかもしれないし
逆ギレして無用の怒りを買って傷口をひろげてしまうかもしれない。
じっと嵐が過ぎ去るのをまつ。
そんなとき泣きつらに蜂で、例のアレルギーバーストもおこりやすい。
すると目はかゆくて涙はでるは、胸とおなかはワサワサするわ、体は湿っぽくなって痒く、血が出るまでかきむしるわ、気分はわるくなっておきていられないわで大変である。(アナフィラキシー)
あわてて頓服の薬をのんでなだめる。
冷たい缶ジュースを買って、火照った体にあて冷やす。
落ち着くまで、しばらくはコミュニケーションも低下し、体の具合も悪く血だらけなので人のいないところに引きこもる。
しかしそうもいっていられないこともある。
そんなときは深呼吸する。
「スーハ、スーハー」
荒れ狂う自律神経をなだめ、こころを落ち着かせる。
つくづく自分をコントロールするのは難しい。
まわりをコントロールするのはもっと難しい。
自分を操縦法を身につけるとともに、環境の構造化をすすめていきたい。










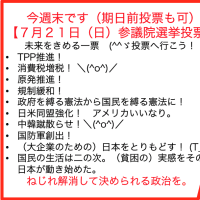
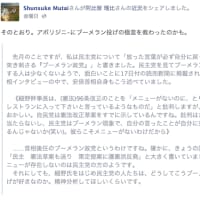




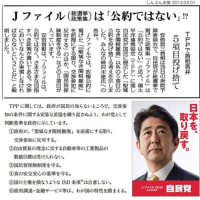

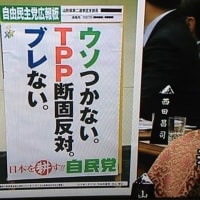

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます