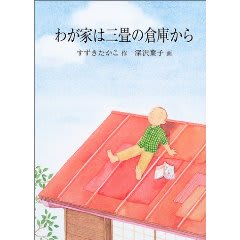
先月「沖縄」で慰霊祭がありました。
小学生の男の子が書いた詩の朗読がありました。
自分のおばあさんが、紙一重で命を落とした家族を思って涙する、
その姿を見て、平和を祈る思いを強くしたことをつづったものでした。
戦争を生き抜いて来た人は、誰もがみな、たくさんの悲しい思い出を持ってます。
「戦争でみんなつらい思いをしたからねぇ」と、
一言でまとめて語られてしまうけれど、そのひとつひとつは、
それはもうとてつもなく悲しくてつらい思い出です。
着物にかかわることをしていても、あの戦争というものが、
人の暮らしというものに、どれだけ多きな重しや枷をかけたことかと、
どれだけさまざまな影響を与えたことかと、本当にびっくりします。
戦争がなかったら、着物は今とは違う残り方をしていたはずだと思います。
トップの写真の本は、作者の三部作のひとつです。
作者の「すずきたかこ」さんは、戦争について「衣・食・住」にわけて、
本を作られました。これはそのうちの「住」の本。
ご紹介はこちら。
東京でお米屋さんを営んでいた一家の物語。
戦争がきびしくなり、お米の配給もなくなり店も立ち行かなくなる…
やがて子供たちは疎開へ、父親は戦場へ…。
終戦になって、主人公の男の子はお母さんと家に戻りますが…。
何もかもなくした家族が、時には人にだまされ、
それより何倍もの人の助けによって「家」を作っていくお話しです。
お身内の実話が元になっているのだそうです。
もう一冊、こちらも持っていますが、アマゾンでのご紹介もかねて…
夫が亡くなり、残された奥さんは、三人の子供を育てるために、
昔やっていたお針子さんの仕事をはじめます。
納屋の奥に毛布で包まれて隠されていたミシン、
戦争中「金属はすべて供出」といわれたときに夫が「これはお前の宝物だから」と
毛布にくるんで隠してくれていたものでした。
古い着物や帯を解き、それで子供たちの服を作る…
彼女は、プロの仕立て屋になり、子供たちを育て上げる、
そのミシンは末の娘に引き継がれ、彼女もまたミシンでいろいろなものを縫う…
というお話です。
私の両親は、元々が家土地を持っていませんでしたから、
横浜に来て、まずはどこだったかの二階に間借りしたり、
バラックのようなところに住んだりしたそうです。
何度かの引越しはいつも借り物のリヤカーで事足りたといってました。
そしてやっと「被災者住宅」のようなところに入り、
そこから、ようやく急ピッチで作られた市営住宅に入りました。
私は覚えていませんが、被災者住宅は、トイレも台所も共同、
洗濯は外の共同水道、部屋は一間きりで、
親子三人猫のように身を丸めて寝ていたと…。
そんな暮らしをしていた母には、安普請でも台所があり、トイレがあり、
畳の部屋が二つ、小さな玄関、ゲタを脱げる勝手口、
そして好きな花を植えられるちいさいけれど自宅の庭…そんな市営住宅に入れて、
まるでお城に引っ越してきたようだったと、いっていました。
その狭い家の台所のかたすみに、ミシンがありました。
いつごろからなのか記憶がありません。
大人になってから「あれは、いっしょけんめやりくりして、
月賦で買うたんや」と母から聞きました。
あの時代ですからおそらくは、毎月300円とか500円とか、
そんな額だったのではないでしょうか。当時としては毎月それだけ払うのも
たいへんだったと思います。
その足踏みミシンで、母もやっぱり、自分の古い着物や洋服を解いて、
私の服を作ってくれました。
「なにもないところから始まったんや」と母はよくいいます。
でも「命まではなくさんかった、それがいちばんやった」ともいいます。
幸いにも、両親と今の養父の身内で、戦死した人や、
戦災で亡くなった人はいなかったようです。
それでも、数年前までずっと行われていた「母の小学校のクラス会」は、
集合場所はいつも「お寺」、まずは戦死した同級生の供養から始まりました。
年をとり、白髪頭ばかりになり、やれ孫がどうの年金がどうのと、
話題がそんなことばかりになっても、
「戦死した○○ちゃんも☓☓ちゃんも、思い出してもいっつも21のまんまやねん、
写真は軍服姿でなぁ、さみしいやら申し訳ないやらなぁ」と。
人にはだれだって「その人の歴史」があります。
よく「平凡な人生」というような表現がありますが、
私は「人の生きた道程」というのは、どんな人のものであっても、
全てドラマチックだと思います。
ほんの数年、生まれた年が違うだけで、どこに生まれたか、
男だったか女だったか、それが違っただけで、
命が左右されてしまった母の年代。「戦争」というもののあった時代。
今の自由な時代は「あって当たり前」ではないのだということを、
しっかりと知らねばなりません。
実際に戦争の時代を経験していない私たち以降の年代のものは、
いったい何を考え、何をすることができるのか…。
私の息子は、残念ながら言葉を理解できませんから、
私の「又聞き」の話すら語り伝えることができません。
せめて…と思い、毎年夏には「戦争」にかかわることを
何かしら書いて、皆様に読んでいただいています。
積極的なことはたいしてできなくても、
一言でも「戦争はいやだね、戦争はだめだね」と
言葉にして文字にして、残していきたいと思っています。
追記…二冊とも、大人が読んでも時代についてよくわかります。
お子さんにも読み聞かせをしたり、少し大きい子でしたら、
読むように勧めてあげてください。戦争で直接戦ったひとではなく、
この国で、兵隊さん以外の戦争と戦後を経験した人たちのお話です。
小学生の男の子が書いた詩の朗読がありました。
自分のおばあさんが、紙一重で命を落とした家族を思って涙する、
その姿を見て、平和を祈る思いを強くしたことをつづったものでした。
戦争を生き抜いて来た人は、誰もがみな、たくさんの悲しい思い出を持ってます。
「戦争でみんなつらい思いをしたからねぇ」と、
一言でまとめて語られてしまうけれど、そのひとつひとつは、
それはもうとてつもなく悲しくてつらい思い出です。
着物にかかわることをしていても、あの戦争というものが、
人の暮らしというものに、どれだけ多きな重しや枷をかけたことかと、
どれだけさまざまな影響を与えたことかと、本当にびっくりします。
戦争がなかったら、着物は今とは違う残り方をしていたはずだと思います。
トップの写真の本は、作者の三部作のひとつです。
作者の「すずきたかこ」さんは、戦争について「衣・食・住」にわけて、
本を作られました。これはそのうちの「住」の本。
ご紹介はこちら。
 | わが家は三畳の倉庫から (鈴の音童話―平和を祈る三部作)すずき たかこ,深沢 葉子銀の鈴社このアイテムの詳細を見る |
東京でお米屋さんを営んでいた一家の物語。
戦争がきびしくなり、お米の配給もなくなり店も立ち行かなくなる…
やがて子供たちは疎開へ、父親は戦場へ…。
終戦になって、主人公の男の子はお母さんと家に戻りますが…。
何もかもなくした家族が、時には人にだまされ、
それより何倍もの人の助けによって「家」を作っていくお話しです。
お身内の実話が元になっているのだそうです。
もう一冊、こちらも持っていますが、アマゾンでのご紹介もかねて…
 | 『ミシン』それは宝物 (鈴の音童話―平和を祈る三部作)すずき たかこ,横松 桃子銀の鈴社このアイテムの詳細を見る |
夫が亡くなり、残された奥さんは、三人の子供を育てるために、
昔やっていたお針子さんの仕事をはじめます。
納屋の奥に毛布で包まれて隠されていたミシン、
戦争中「金属はすべて供出」といわれたときに夫が「これはお前の宝物だから」と
毛布にくるんで隠してくれていたものでした。
古い着物や帯を解き、それで子供たちの服を作る…
彼女は、プロの仕立て屋になり、子供たちを育て上げる、
そのミシンは末の娘に引き継がれ、彼女もまたミシンでいろいろなものを縫う…
というお話です。
私の両親は、元々が家土地を持っていませんでしたから、
横浜に来て、まずはどこだったかの二階に間借りしたり、
バラックのようなところに住んだりしたそうです。
何度かの引越しはいつも借り物のリヤカーで事足りたといってました。
そしてやっと「被災者住宅」のようなところに入り、
そこから、ようやく急ピッチで作られた市営住宅に入りました。
私は覚えていませんが、被災者住宅は、トイレも台所も共同、
洗濯は外の共同水道、部屋は一間きりで、
親子三人猫のように身を丸めて寝ていたと…。
そんな暮らしをしていた母には、安普請でも台所があり、トイレがあり、
畳の部屋が二つ、小さな玄関、ゲタを脱げる勝手口、
そして好きな花を植えられるちいさいけれど自宅の庭…そんな市営住宅に入れて、
まるでお城に引っ越してきたようだったと、いっていました。
その狭い家の台所のかたすみに、ミシンがありました。
いつごろからなのか記憶がありません。
大人になってから「あれは、いっしょけんめやりくりして、
月賦で買うたんや」と母から聞きました。
あの時代ですからおそらくは、毎月300円とか500円とか、
そんな額だったのではないでしょうか。当時としては毎月それだけ払うのも
たいへんだったと思います。
その足踏みミシンで、母もやっぱり、自分の古い着物や洋服を解いて、
私の服を作ってくれました。
「なにもないところから始まったんや」と母はよくいいます。
でも「命まではなくさんかった、それがいちばんやった」ともいいます。
幸いにも、両親と今の養父の身内で、戦死した人や、
戦災で亡くなった人はいなかったようです。
それでも、数年前までずっと行われていた「母の小学校のクラス会」は、
集合場所はいつも「お寺」、まずは戦死した同級生の供養から始まりました。
年をとり、白髪頭ばかりになり、やれ孫がどうの年金がどうのと、
話題がそんなことばかりになっても、
「戦死した○○ちゃんも☓☓ちゃんも、思い出してもいっつも21のまんまやねん、
写真は軍服姿でなぁ、さみしいやら申し訳ないやらなぁ」と。
人にはだれだって「その人の歴史」があります。
よく「平凡な人生」というような表現がありますが、
私は「人の生きた道程」というのは、どんな人のものであっても、
全てドラマチックだと思います。
ほんの数年、生まれた年が違うだけで、どこに生まれたか、
男だったか女だったか、それが違っただけで、
命が左右されてしまった母の年代。「戦争」というもののあった時代。
今の自由な時代は「あって当たり前」ではないのだということを、
しっかりと知らねばなりません。
実際に戦争の時代を経験していない私たち以降の年代のものは、
いったい何を考え、何をすることができるのか…。
私の息子は、残念ながら言葉を理解できませんから、
私の「又聞き」の話すら語り伝えることができません。
せめて…と思い、毎年夏には「戦争」にかかわることを
何かしら書いて、皆様に読んでいただいています。
積極的なことはたいしてできなくても、
一言でも「戦争はいやだね、戦争はだめだね」と
言葉にして文字にして、残していきたいと思っています。
追記…二冊とも、大人が読んでも時代についてよくわかります。
お子さんにも読み聞かせをしたり、少し大きい子でしたら、
読むように勧めてあげてください。戦争で直接戦ったひとではなく、
この国で、兵隊さん以外の戦争と戦後を経験した人たちのお話です。




























父は召集され戦場へ荷物の運搬に行って
いたそうです。もともと無口な父は多くを
語りませんでしたが、弾をよけるため
トラックの下にもぐりこんだと言っていました。悲惨な戦場を目の当たりにした父は
口癖のように戦争中の事を考えたら贅沢は
言うなとよく言われました。
妊娠中の母は父が無事に帰るかどうかも
分からず、男だったら○○、女の子だったら
○○、と名前を言ったそうです。
思い出すのも辛いほどの戦争だったと思いますが、誰かが伝えていかなければいけない事ですね。
晩年の父は戦地の戦友の話を繰り返していました。
私の手元には父が戦地から小さい私にも判るように
絵手紙で戦地で出会った子ども達のけなげな様子を
伝えてくれています。
決して悲惨な状態を描いておりませんのは、
軍の墨消しがあったからだけではなく、
教育者としてのメッセージが込められていたのではと
毎年、この時期に眺めるたびにおもいます。
10数枚あり、結婚するときにアルバムにして
母へ送った子ども達への思いの短歌を筆で
したためて、贈ってくれました。
なによりの<戦争は絶対反対!!>の意思表示、
大切につないでいきますね、と、誓っています。
つらくて異常な体験ですよね。
最近、それまで話そうとしなかった
かなりのご高齢の方たちが、
やはり伝えておきたい…と、話したり書いたり
されています。つらいとは思いますが、
そうして残してほしいです。
私たちの子供や孫の時代に「徴兵」なんて、
ゼッタイにいやですし。
それはとても貴重な思い出であり、資料ですね。
手紙を書きながら、読みながら、
もしかしたら二度と会えないかもしれないと、
そんな思いだったのかもしれません。
二度とおこしてはならないと、
経験のない私でも、話を聞くたび思います。
朝顔のデキが悪い…なんて悩んでいられて、
ほんとにシアワセなんですよね。
blogへのご来訪ありがとうございました。
大変遅くなりましたが
まずはこちらで本を紹介していただいたお礼を、と思いまして。
戦後生まれで戦争は経験していなくても
その頃の人達がどんな思いで生きなければならなかったかを想像することは
とても大切だと思います。
自分は安全な場所にいて命令を下していた人達は
一人一人に尊い命があることを理解していたのでしょうか。
また、平和な今は同じように
つましい生活などしたことのない政治家に庶民の気持ちが
分かるとは思えないな~と、
選挙の日に思ったりしています・・・。
こちらこそ、ありがとうございます。
今年もさまざまな「終戦番組」を見ました。
戦争の現場でタイヘンな思いをした人の言葉も
「銃後の守り」と言われた人の言葉も、
時代にほんろうされ、人生を作られてしまった
そんな悲しみがあふれていました。
淡々と語れば語るほど、痛みが強い言葉でした。
ぬくぬくとしている人が政治をすることこそ
おかしいと、つくづく思います。