
この前、江戸小紋の記事を書いたときには、どこにあったか、
さーっぱり思い出せなかったというのに、今日突然あっ一番上の棚の左オク…。
やれやれ情けない…というわけで出してきました。
これは呉服屋さんがお客様にお見せする「染め見本」の反物です。
こんなふうになってます。

ヤ○オクでもたまに出てきますが、だいたい普通の反物の半分、
6~7メートルくらいで、小紋の見本柄が染められているわけです。
えーと、この「染め見本」のことについても書きたいのですが、
いつも長くなってしまうので、そのことについては「続く」で、明日に…。
とりあえず今日は、江戸小紋の柄と色をみていただきましょう。
といいながら、最初にお詫びなんですが、江戸小紋って柄が細かいので、
アップして写真を撮ろうとすると、私の腕ではなかなかきれいにできませんで…。
まぁ、こんな感じ…でご勘弁ください。
まずはこちらの反物は「鮫」と「角通し」と「鱗」…。
三役だと「行儀」なんですが、なぜか行儀がなくて「鱗」です。
こちらが「角通し」、絵で描けば要するに格子柄のネガポジみたいなものですから
白いところは四角なんですが、こうなると○になっちゃってますね。

この色違い、がこちら。
角通しの見本A

角通しの見本B

まぁあまりにも小さくて、イメージつかみにくいですが、
これで見るだけでも、同じ柄でもイメージが違いますね。
同じ柄で、母娘で色違いなんてのもステキでしょうね。
そしてこちらがお馴染みの「鮫」です。
鮫小紋の見本

上の段の一番左、鮫とはわかりにくいですよね。
かといってこの写真でもわかりにくいのですが…グレー地にピンクです。
実際にはもう少しピンクが鮮やかです。

通常の江戸小紋は白地に「残るところだけ」糊をかぶせて、
地を染める、つまり鮫の小さいドットや角通しの小さい四角は、
本来「白く」残るわけですが、これは先にピンクに染めたものに
型をおいて地を染める、のでしょうか、それとも型に色糊でしょうか、
そのアタリのことは私もわかりません。
とにかく、本来白く残るところに色がありますから、また違って見えます。
単純な柄なのに、こうなると「着物にしてみなきゃわからない」ですねぇ。
角通しの方にもありまして、例えばこちらはこげ茶の地、四角は黄色、

まぁそういう色もありかとびっくりですが…
でも、きをつけなくちゃいけません。
私は「こげ茶色と黄色」なんかけっこうおもしろいかなと思ったのですが、
ちょっと離れてみると、色がまざってただの茶色…。
さっきのグレーとピンクですが、もう一度出してみましょう、
こちら、よく見てくださいね、

そして1メートル半くらい離れると…

3メートルばかし離れたら…何か柄が見えますが、実際には無地です。
色の感じだけはこんな風です。

うそ画像じゃないんですよ、一番上のクローズアップは、
これ以上画像が小さくなると柄がわかりづらいため粗い画像ですが、
実物はピンクが浮き出てます。でもまだ回りの濃いグレーがきいています。
それが少し離れると、柄である「点」が多いですからすっかりピンクが勝ちます。
それでもまだ「鮫」の模様はわかるので、ああ江戸小紋だなと…。
それがもう少し離れるともう柄がわからず、なんといいますか
言葉に表せないような、にごったピンクといいますか…。
もうひとつ、こちらは地がグリーンで、点は実際にはもっときれいなオレンジ。
手にとって見ると、どっちもはっきりしたきれいな色です。

このグリーンは上の「角通しの見本B」の、右から二番目です。
あの写真は「接写」でとって切り取っているので、
まだグリーンが目立つのですが、これがちょっと離れますと…

まぁデジカメの画像ですから、かならずしも正確な色ではないし、
実物は、肉眼では細かい「点」が距離によって意識できますから、
ちょっと離れたら全部この色…というわけではありません。
とりあえず、3メートルばかり離れてぱっと見ると、茶色…なわけです。
考えてみれば当たり前の話で、細かい点々が組み合わさっているのですから、
当然その二色は離れればはなれるほど「溶け合う」わけです。
だから「江戸小紋は離れると無地のように見える」んですよね。
ただ、これが、テレビ画面の粒子のように、同じ形の丸い粒の集まりで、
規則正しく同じ割合で並んでいれば、黒と白ならグレー、
赤と白ならピンク、と単純に変わるわけですが、江戸小紋は地と柄です。
その柄によっての「点」の並びで、地が勝ったり点が勝ったり…。
それで全体の溶け合う感じがかわって、離れた視点での色目がかわるわけです。
これを注意しないと、手元で見本を見て決めてしまうと
遠目が全然違ったり、にごった色になったりしてしまいます。
普通は地色と白、ですが、その地色と白でさえ、
ただの地色の薄いものではなく、色の変化や雰囲気が違います。
こちらは先日の「やえ」と名前の入った「いわれ」のほうの小紋。
かなり柄が大きめでハッキリしています。
二番目が少し離れて…三番目は遠目、です。
松の輪郭がいつまでも残って、花みたいな雲みたいな…で、
とても無地にはなりませんね。
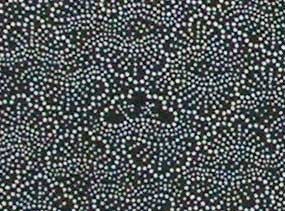


江戸小紋でも三役とか、似たようなごく細かい柄は、「溶け合う色」を、
いわれのような柄のものは、遠めに何が見えるか…、
そんなこともきをつけて選ばないと、なんだかもやもやの着物、
になってしまいます。
今日載せましたのは、あくまでデジカメの画像ですから極端に見えています。
柄が消えるわけではありませんから、肉眼ではもう少し違うニュアンスですが、
とりあえず、手に取ったときと遠目では全然違う雰囲気をもつもの、
江戸小紋ってそういうものだというお話です。
鱗柄やほかの小紋についても書きたいことがありましたが、
それも明日ということで…。
さーっぱり思い出せなかったというのに、今日突然あっ一番上の棚の左オク…。
やれやれ情けない…というわけで出してきました。
これは呉服屋さんがお客様にお見せする「染め見本」の反物です。
こんなふうになってます。

ヤ○オクでもたまに出てきますが、だいたい普通の反物の半分、
6~7メートルくらいで、小紋の見本柄が染められているわけです。
えーと、この「染め見本」のことについても書きたいのですが、
いつも長くなってしまうので、そのことについては「続く」で、明日に…。
とりあえず今日は、江戸小紋の柄と色をみていただきましょう。
といいながら、最初にお詫びなんですが、江戸小紋って柄が細かいので、
アップして写真を撮ろうとすると、私の腕ではなかなかきれいにできませんで…。
まぁ、こんな感じ…でご勘弁ください。
まずはこちらの反物は「鮫」と「角通し」と「鱗」…。
三役だと「行儀」なんですが、なぜか行儀がなくて「鱗」です。
こちらが「角通し」、絵で描けば要するに格子柄のネガポジみたいなものですから
白いところは四角なんですが、こうなると○になっちゃってますね。

この色違い、がこちら。
角通しの見本A

角通しの見本B

まぁあまりにも小さくて、イメージつかみにくいですが、
これで見るだけでも、同じ柄でもイメージが違いますね。
同じ柄で、母娘で色違いなんてのもステキでしょうね。
そしてこちらがお馴染みの「鮫」です。
鮫小紋の見本

上の段の一番左、鮫とはわかりにくいですよね。
かといってこの写真でもわかりにくいのですが…グレー地にピンクです。
実際にはもう少しピンクが鮮やかです。

通常の江戸小紋は白地に「残るところだけ」糊をかぶせて、
地を染める、つまり鮫の小さいドットや角通しの小さい四角は、
本来「白く」残るわけですが、これは先にピンクに染めたものに
型をおいて地を染める、のでしょうか、それとも型に色糊でしょうか、
そのアタリのことは私もわかりません。
とにかく、本来白く残るところに色がありますから、また違って見えます。
単純な柄なのに、こうなると「着物にしてみなきゃわからない」ですねぇ。
角通しの方にもありまして、例えばこちらはこげ茶の地、四角は黄色、

まぁそういう色もありかとびっくりですが…
でも、きをつけなくちゃいけません。
私は「こげ茶色と黄色」なんかけっこうおもしろいかなと思ったのですが、
ちょっと離れてみると、色がまざってただの茶色…。
さっきのグレーとピンクですが、もう一度出してみましょう、
こちら、よく見てくださいね、

そして1メートル半くらい離れると…

3メートルばかし離れたら…何か柄が見えますが、実際には無地です。
色の感じだけはこんな風です。

うそ画像じゃないんですよ、一番上のクローズアップは、
これ以上画像が小さくなると柄がわかりづらいため粗い画像ですが、
実物はピンクが浮き出てます。でもまだ回りの濃いグレーがきいています。
それが少し離れると、柄である「点」が多いですからすっかりピンクが勝ちます。
それでもまだ「鮫」の模様はわかるので、ああ江戸小紋だなと…。
それがもう少し離れるともう柄がわからず、なんといいますか
言葉に表せないような、にごったピンクといいますか…。
もうひとつ、こちらは地がグリーンで、点は実際にはもっときれいなオレンジ。
手にとって見ると、どっちもはっきりしたきれいな色です。

このグリーンは上の「角通しの見本B」の、右から二番目です。
あの写真は「接写」でとって切り取っているので、
まだグリーンが目立つのですが、これがちょっと離れますと…

まぁデジカメの画像ですから、かならずしも正確な色ではないし、
実物は、肉眼では細かい「点」が距離によって意識できますから、
ちょっと離れたら全部この色…というわけではありません。
とりあえず、3メートルばかり離れてぱっと見ると、茶色…なわけです。
考えてみれば当たり前の話で、細かい点々が組み合わさっているのですから、
当然その二色は離れればはなれるほど「溶け合う」わけです。
だから「江戸小紋は離れると無地のように見える」んですよね。
ただ、これが、テレビ画面の粒子のように、同じ形の丸い粒の集まりで、
規則正しく同じ割合で並んでいれば、黒と白ならグレー、
赤と白ならピンク、と単純に変わるわけですが、江戸小紋は地と柄です。
その柄によっての「点」の並びで、地が勝ったり点が勝ったり…。
それで全体の溶け合う感じがかわって、離れた視点での色目がかわるわけです。
これを注意しないと、手元で見本を見て決めてしまうと
遠目が全然違ったり、にごった色になったりしてしまいます。
普通は地色と白、ですが、その地色と白でさえ、
ただの地色の薄いものではなく、色の変化や雰囲気が違います。
こちらは先日の「やえ」と名前の入った「いわれ」のほうの小紋。
かなり柄が大きめでハッキリしています。
二番目が少し離れて…三番目は遠目、です。
松の輪郭がいつまでも残って、花みたいな雲みたいな…で、
とても無地にはなりませんね。
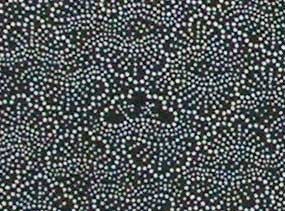


江戸小紋でも三役とか、似たようなごく細かい柄は、「溶け合う色」を、
いわれのような柄のものは、遠めに何が見えるか…、
そんなこともきをつけて選ばないと、なんだかもやもやの着物、
になってしまいます。
今日載せましたのは、あくまでデジカメの画像ですから極端に見えています。
柄が消えるわけではありませんから、肉眼ではもう少し違うニュアンスですが、
とりあえず、手に取ったときと遠目では全然違う雰囲気をもつもの、
江戸小紋ってそういうものだというお話です。
鱗柄やほかの小紋についても書きたいことがありましたが、
それも明日ということで…。




























ねずみ色にピンクのがいいなぁと思いました。
販売はされないのでしょうか?気になりました。
すみませーん、写真一枚忘れてました。
染め見本なので、ちょっとずつしか
ないんですよー。ごめんなさい。
久々にお邪魔して、なるほどと読ませていただいています。
また、時々お邪魔させていただきますね。
鮫小紋には『向き』があるから、追い裁ちで、と習いましたが、見た感じ、向きがなさそうですね。型を彫る方によって少しずつ違うんでしょうか?不思議です。
向きというのは、点々が、なんとなく扇型に同じほうを向いて並んでいるように見える。ということなのですが。
コメントありがとうございました。
いや、ブログってほんと不思議、じつはですね。
昨夜のことです。
品物の名前がわからなくて、とんぼさんの記事をさかのぼってすごく探したんですよ。
なんか感じましたか?
このところずっとご無沙汰していましたのに、コメントいただいてびっくりしました。
聞きたかったのは、花嫁衣裳で丸帯の下にだらりと下げて結ぶ房のついた真っ赤なしごきのようなもの、あれはなんと言うものでしょうか?
母が60年以上前に使ったものがあるんですよ。真っ赤なのでマフラーに使おうかと思いますが、本式の呼び名を知りたいと思いまして。
強させて貰います。鮫小紋・角通し・行儀が三
役。今日は鮫小紋と角通し。明日は行儀です
か?他に万筋なんてのもあるそうですね。
持ってる着物は、譲り受けたもの、リサイクル
物などで、着丈がばらばらですが、ウールは着
ているとどうもずり上がるみたいで、着丈が少
し短めだと、着ているうちに、相当短くなる気
がしますが、絹物特にお召し系だとそういうこ
とは無い様な気がします。
ネットショップの男の江戸小紋の専門店の品物
は、縮緬ともう一つ材質が選べる仕組みになっ
ていますが、縮緬を選んだ方が良いですかね?
今日の写真からすると、鮫小紋より角通しの方
が僕に合いそうです。
鮫などの小さな丸を彫る彫刻刀は半円形であったり真ん丸に作ったものですが、その彫刻刀自体を作る人が少なくなっていると思います。
型紙を使って白糊や写し糊を置いて染める昔ながらの江戸小紋はどうしても型継ぎが出て、反物を伸ばした時に段付きや段の染めムラが出ています。
一流の職人さんが染めた江戸小紋は何となく段継ぎが出ている物。
一方機械捺染の江戸小紋はローラーで染めるので型継ぎは出しようが無く、全くのムラ無し。
つまり染めムラが少しは有った方が高級品と言えるのです、がしかし敵はさるものそれを見越してわざと段継ぎをこしらえている物もあるとか。
ずいぶん変りますね。
江戸小紋は、やっぱりいいですね~。
見ているだけでも楽しいわぁ。
お久しぶりです。
ジュリアちゃんもお元気のようですね。
拙い記事ですが、お楽しみいただければ
さいわいです。
先日の大島、ステキですね。
私もこの見本の鮫はなんか崩れている気がして
自分のものとくらべてみました。
ちょっと違うようです。
明日の記事に書く予定でしたので、
またお越しください。ちなみにこれも
書く予定ですが、青海鮫は「基本裁ち」が
多いように思います。私のもそうです。
こればっかりは和裁素人の私には、
詳しいことはわからないのですが。