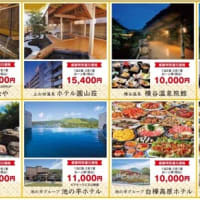9月21日(木)ガイドのリハーサルから学ぶ
<コース>陣屋(浅間会館)→中山道古道・探索→大田山龍雲寺→成田山円満寺→住吉神社→(善光寺道)→陣屋戻り
岩村田宿案内看板(佐久教育委員会作成)
拡大版

中山道古道沿い「おひょうきさま」江戸時代から受け継がれているものと推測されます。これは貴重なものです。
お顔の表情が和やかなように見えていいですね。
でもこれが、魔除けの意味もあるようですよ。
一方、こちらはお隣に家に載っていた「おひょうきさま?」
こちらは、新しそうです。手を広げた形は前のとは違っています。
でも、これはこれでなかなかいいのではないでしょうか。
この通りは、荒宿通りと呼ばれています。祇園に合わせた祭礼「おふね様」の山車を保管する屋敷やその山車に飾られるサギを作る職人のお宅が存在する歴史ある場所です。
ここから、通称「なべか小路」と呼ばれる道を抜け、大田山龍雲寺まで進みます。
龍雲寺の山門の丸窓は鎌倉時代の様式で、楼上には、お釈迦様の弟子の十六羅漢の像が安置されています。また、屋根瓦と4つの戸には武田紋が施されています。
ここには、武田信玄公の霊廟があり、遺骨の分骨と袈裟が収められています。
山門の左には、別の門があり「東山法窟」と記された勅額がかけられています。かつて、東山道の学習どころであったとのことです。
<言葉の意味>寺院について使われる、開基と開山について
開基:金銭を提供した人
開山:寺を開いた人
龍雲寺を出て、東側の小路を成田山円満寺に向かいます。途中にはかつて子院が六院あったといわれる六供と呼ばれる場所があります。もとは十二院あったとことろが、小諸に六供、荒宿に六供と分かれたとのことです。(ご住職談)
円満寺は、参道奥の左に滝不動、右に菅谷と呼ばれる目の病に効くという像が置かれています。
寺の裏側には、施無畏堂(観音堂)は1747(延享4)年の再建によるもの。中には、十一面観音立像が安置されています。また、カナダ人宣教師キャンベル夫妻の供養塔があります。
境内には、この他に満開時には花房が地面まで届きそうな砂ずりに藤(野田藤)と呼ばれる見事な藤棚があります。
ここから裏道を、住吉神社向かいます。
住吉神社は、文明年間(1469~1487)にこの場所に祀られたといわれています。
境内には、樹齢800年といわれる大きな欅の木があります。この木の側面に回るとわかるのですが、大きいが故に幾度か落雷の被害を受けており中は焼け空洞化しています。また、ここには明治以降に周辺の庚申塔、道祖神や石祠が幾基も合祀され置かれていています。前庭の隅にある「依是善光寺道」の道標は、交通災害で破損したものをつなぎ合わせ、本来の設置場所からここに移されたものです。
ここから南下した場所に、中山道から枝道で北国街道につながる善光寺道の場所に、二代目になる「依是善光寺道」道標があります。
この後は、出発点の陣屋跡に戻りました。
食事は、「三月九日食堂」のボリウム満点の定食でした。