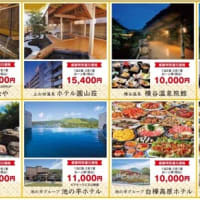11月17日(土)10:00~12:00 晴れ
一般参加者38名
<トップ映像>武重本家酒造付近から、大澤酒造方面に向かう登り坂

ツアールート
茂田井学校跡(公民館)駐車場→諏訪神社→無量寺→<新道(バス道)>→茂田井間の宿京方入り口→一里塚→石割坂→上組高札場→<宿内散策>→馬頭観音→大澤酒造→武重本家酒造→神明社→茂田井学校跡(公民館)駐車場
最初に、間の宿の概要説明(坂田孝三先生より)
10名くらいのグループに分かれ、ガイドの説明を受けながら街道のポイントを見ながら歩きます。
茂田井は水質も良く、良米に恵まれ古くから人々が住み着き集落があった。
茂田井間の宿は、望月宿と芦田宿の間に位置し、「間の宿」と呼ばれるようになった。小諸藩牧野遠江守領分で、江戸から45里26町(約183㎞)、望月宿から26町(2.8㎞)、芦田宿から18町(約2㎞)往還10町12間(約1.1㎞)の集落である。
”茂田井”の名前は、10世紀「和名類聚鈔」によると、信濃10郡の一つで佐久群8郷の一つ「茂理」「茂田理」が転じたものらしい。「甕」「母袋」「毛田井」などの姓は、この地と所縁のあるものと思われる。
幕府の宿場制度の中で、本宿保護のため宿場として認められず、1715(正徳5)年以来度々禁令が出され、厳しく取り締まっている。
石高は、1617(元和3)年=1,230石、その後、江戸中期には967石余りに減少しているが、理由は不明である。
良水、良米の産地ゆえに、2軒の造り酒屋がある。このうち大澤酒造は1689(元禄2)年創業と古く、下組(江戸側)の名主を勤めている。
諏訪神社・・・イチョウの落ち葉が輝く。
諏訪の諏訪神社の分社であるが、創建は不明。現在の建物は、1818(文化5)年、茂田井の宮大工田中圓蔵(諏訪の立川和四郎子弟)により、再建された。彫刻は鋭く見ごたえがある。
境内には、各所から移設された双体道祖神、倉見寺から掘り出された日の出地蔵がある。
石割坂
勾配がきつい道の中央に大きな石があり、通行の妨げとなっており、その石を割って街道にしたと伝わる。
なお、石割坂の西側には一里塚があって、高さは、現在の跡の数倍の高さがあったという。
馬頭観音付近から京方への道
大澤酒造中庭
1689(元禄2)年創業。3階建ての屋根が込み入って、5階のようにも見える。内部にある民俗資料館や美術館、書道館がありその作品は逸品。
街道側には下組高札場がある。
大澤酒造の書道館二階の窓からの風景
武重本家酒造方面に向かう下り坂になる。
武重本家酒蔵
武重本家酒造は、創業1868(明治1)年創業。広大な敷地内には33棟の建屋があるとされる。
街道脇にこの地に滞在していたといわれる若山牧水の歌碑があることで知られる。以下は、歌碑の3首です。
「しらたまの歯にしみとほる秋の酒は静かにのむべかりけり」
「ひとの世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ」→この句がいい!
「よき酒とひとのいふ御園竹われもけふ飲みつよしと思えり」→これは宣伝か?
田中本家酒造南の水田と落ち着いた家並みのマッチングが美しい。
武重本家酒造並びに周辺は、山田洋二監督の「たそがれ清兵衛(真田広之主演)」「家族はつらいよ・妻よ薔薇のように(夏川結衣主演)」のロケ地である。
東側の高台(バス道)から、西側に宿を見下ろすと懐かしい里風景