
週末は、奈良の春日ホテルで近畿弁護士会連合会刑事弁護委員会の夏期研修会でした。
近畿各地から、刑事弁護に取り組む弁護士80名が終結して熱心な討論が行われました。
テーマのひとつは「接見の際のIT機器の利用」
パソコン、スマホ、タブレット、デジカメ、ICレコーダーは生活に欠かせないアイテムですが、弁護士の仕事でも大いに活躍しています。
ところが、拘置所の接見室でこうしたIT機器を使おうとしても、持ち込みを制限されたり、録画した画像の消去を求められたりすることがあります。
酷い事例では、録画したデータを消去するまで帰さないと言われて、南京錠で部屋に鍵をかけられていたとか。
接見の際に、会話した内容をボールペンでノートにメモにとることは何の問題もありません。
メモをとることも、録音することも、写真撮影することも被疑者から情報を受け取ると言うことでは何の違いもありません。
接見の際に、持ち込んだ紙資料や証拠書類を見せることにも何の問題もありません。
ところが、接見室でネット検察した結果を画面上で見せることは規制されるのです。
捜査機関側は携帯の通話記録を精査したり、DNA型鑑定、通信傍受、ネットでの情報収集、取調べの録画などIT機器を駆使して捜査をしています。
それなのに弁護側はIT機器を使えないというのはアンフェアです。
拘置所、留置施設に、接見の際のIT機器の利用を認めさせる為にどのように戦っていくかの作成会議が行われました。
もう一つのテーマは、
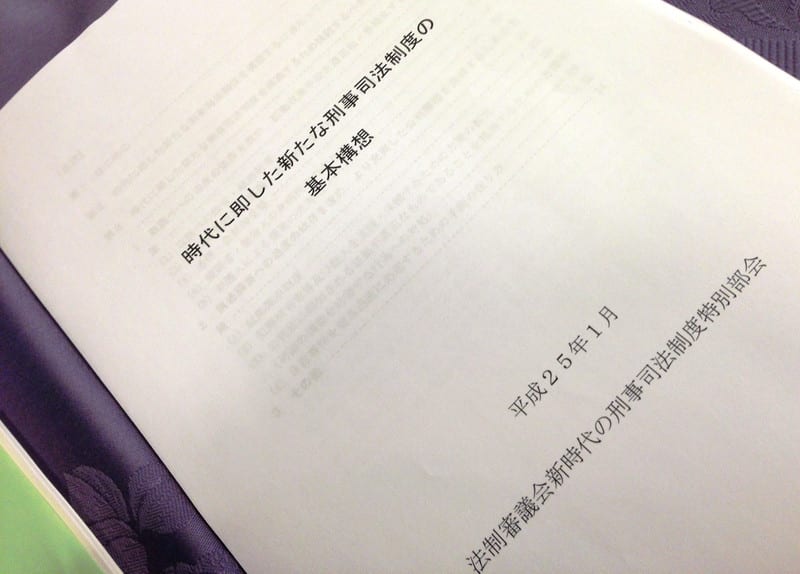
法制審議会で議論されている
「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」
厚労省の村木厚子さんや映画監督の周防正行さんの怒りのコメントが新聞各紙に掲載されていましたが、問題だらけの基本構想です。
違法な取り調べをなくし、冤罪を防ぐために始まった検討会なのに、捜査機関に新たな操作方法を付与するばかりの基本構想に成り下がってしまっています。
こんな方向性で改革が行われるぐらいなら、今のまま、ずっと可視化を実現させないで、可視化を求める運動を続けていた方がよほどマシな弁護活動ができます。
この問題については、京都弁護士会で秋に予定している
「憲法と人権を考える集い」で取り上げます。
周防正行監督にゲスト出演していただける予定です。
11月17日(日)午後、シルクホール(四条烏丸)です。
ぜひ、ご期待下さい。










