今日は夏至ですね。
キャンドルナイトのイベントが各地で行われるようです。
以前にも書きましたが、僕は二酸化炭素による温暖化説には納得していません。
また、樹木を増やすと二酸化炭素が減り、酸素が増え温暖化が回避できると単純には思いません。
山や、凍土、北極の氷は溶けているといいますが、一方で海面水位にもっとも関係のある南極の氷は厚さを増しているといいます。
ネットは様々な情報を伝えますが、最近は特に、結論だけを伝えているような気がします。
どんな根拠でその結論に至ったのか、などの詳細を知るのはかなり面倒なものです。
ネット辞書で、語句を調べても、意味だけが出てきて、由来などは出てきません。
そこから先は有料だったりしますし。
詳細がわからない僕らは発表者の社会的立場で、ことの真偽の判断をしようとします、国の機関だからとか、国際的な組織だからとか。
しかし、政治、国家は詐欺師並にウソツキです。
科学よりは、国際関係、ビジネスの都合、利権が優先ですから。
第一、去年の暖冬、今年の梅雨を予測出来なかった人たちが、温暖化は確実と、なにやら数値を出して主張しているのです。
競馬の予想屋や、古くはぶどう畑に雹を降らせるのが魔女のせいだと言っていた人たちとどれほどの差があるのやら。
僕らは今も、わからないことだらけの世界で、理由を求めて、不安を抱えて生きているのです。
その時々の科学や、人の都合は、物事に見栄えの良い理由や結論を与えます、それを受け入れれば不安の一部は解消されますが、それはあくまで一時的なものにしか過ぎません。
僕らは、理由や結論のわからぬ不安、もどかしさ、苦しみに耐えなければなりません。
安上がりな安心感を求めてはいけません。
そして、それぞれの場面で良いと考えられる選択をするしかありません。
ベストなんてありません、ベターの積み重ねしかないのです。
で、僕の立場はというと…。
木や緑を増やすのには賛成です。
CO2削減が理由ではありませんが、燃料の無駄使いはすべきではないと思います。
もったいないからです。よって、植物由来の燃料であっても、大切に使うべきだと思います。
電気は作り方によっては良いエネルギーだと思いますが、現在の日本のそれはクリーンだとは思いません。
本当は使いたくないのですが、やむを得ないところです。出来るだけ無駄に使わないように、他の手段を模索し続けることは忘れないつもりです。
結局、CO2悪玉派と、大体行動方向は同じなのです。
ただし、このCO2削減策には、原子力推進という裏の顔があります。
環境を守ろうだの地球にやさしいだのと言っている人たちにも正反対の立場があるのです。
今晩は、ろうそくを燈していろいろなことに思いを馳せてみるのも良いと思いますよ。
大事な人のこと、その人との未来のことなんかね。
火の用心でどうぞ。
僕はろうそくの火を見ながら貧困を嘆きます。トホホ。
キャンドルナイトのイベントが各地で行われるようです。
以前にも書きましたが、僕は二酸化炭素による温暖化説には納得していません。
また、樹木を増やすと二酸化炭素が減り、酸素が増え温暖化が回避できると単純には思いません。
山や、凍土、北極の氷は溶けているといいますが、一方で海面水位にもっとも関係のある南極の氷は厚さを増しているといいます。
ネットは様々な情報を伝えますが、最近は特に、結論だけを伝えているような気がします。
どんな根拠でその結論に至ったのか、などの詳細を知るのはかなり面倒なものです。
ネット辞書で、語句を調べても、意味だけが出てきて、由来などは出てきません。
そこから先は有料だったりしますし。
詳細がわからない僕らは発表者の社会的立場で、ことの真偽の判断をしようとします、国の機関だからとか、国際的な組織だからとか。
しかし、政治、国家は詐欺師並にウソツキです。
科学よりは、国際関係、ビジネスの都合、利権が優先ですから。
第一、去年の暖冬、今年の梅雨を予測出来なかった人たちが、温暖化は確実と、なにやら数値を出して主張しているのです。
競馬の予想屋や、古くはぶどう畑に雹を降らせるのが魔女のせいだと言っていた人たちとどれほどの差があるのやら。
僕らは今も、わからないことだらけの世界で、理由を求めて、不安を抱えて生きているのです。
その時々の科学や、人の都合は、物事に見栄えの良い理由や結論を与えます、それを受け入れれば不安の一部は解消されますが、それはあくまで一時的なものにしか過ぎません。
僕らは、理由や結論のわからぬ不安、もどかしさ、苦しみに耐えなければなりません。
安上がりな安心感を求めてはいけません。
そして、それぞれの場面で良いと考えられる選択をするしかありません。
ベストなんてありません、ベターの積み重ねしかないのです。
で、僕の立場はというと…。
木や緑を増やすのには賛成です。
CO2削減が理由ではありませんが、燃料の無駄使いはすべきではないと思います。
もったいないからです。よって、植物由来の燃料であっても、大切に使うべきだと思います。
電気は作り方によっては良いエネルギーだと思いますが、現在の日本のそれはクリーンだとは思いません。
本当は使いたくないのですが、やむを得ないところです。出来るだけ無駄に使わないように、他の手段を模索し続けることは忘れないつもりです。
結局、CO2悪玉派と、大体行動方向は同じなのです。
ただし、このCO2削減策には、原子力推進という裏の顔があります。
環境を守ろうだの地球にやさしいだのと言っている人たちにも正反対の立場があるのです。
今晩は、ろうそくを燈していろいろなことに思いを馳せてみるのも良いと思いますよ。
大事な人のこと、その人との未来のことなんかね。
火の用心でどうぞ。
僕はろうそくの火を見ながら貧困を嘆きます。トホホ。















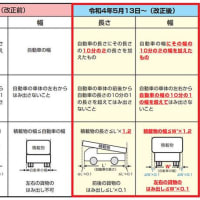




ですが、最近それを否定する傾向があります。
経済効率性とか言ってね。
人生において長い眼でみると、それは得るものを失っていくことなので、損なことなんですよね。
ロウソクの灯、蛍光灯に比べると暗くて不便ですけれど、心を動かす何かがあります。不思議ですよね。
気象学者や海洋学者の研究によれば、CO2の増加で温暖化が起きているのではなく、まず気温の上昇があってその後にCO2が増加しているというデータがあるんだそうです。そのことを報告したイギリスのドキュメンタリー番組『ザ・グレイト・グローバル・ウォーミング・スピンドル』がYou Tubeで観られるようですよ。
そうそう、お話していた「えんたつ」さん、今年北杜市にキャンプに行くとか、即行で決められてました(笑)。風琴屋さんのブログや、リンクされてたアルファブログを見て、何か感じるものがあったようでしたよ。
絵画というバックライト無し、自ら光を放つことのない表現手段で「光」を表現するために、実に多くの努力がなされて来ていますね。
そのものズバリを示すことなく何かを伝えるというのは、芸術家が長らく挑戦してきたことですよね。
例えば、音楽で海を表現するとか、「愛」という言葉を使わず「愛」を表現するとか。
映像や、直接表現以上に、そのものを強く感じさせること。これもまた、昨今衰えてしまったような気がします。
効率主義なんていっても、楽をした分、わざわざスポーツジムで体力を消費したりしないと病気になるっていうんですから、まあ非効率なこと!
オランダ人は背が高いです。
それは、洪水になった時、少しでも生き残りやすいようにそうなった…、というジョークがあります。
国土のかなりが海面下の国、南の島国などにとっては、海面上昇は理屈抜きの恐怖です。
シベリアの永久凍土が溶けて、氷の中からマンモスが出てきているといいます、つまり、マンモスが氷の中に閉じ込められる以前は凍っていなかったわけですし、もともと地表は高熱のガスに包まれていた時期もあるのに、それに永久凍土などと名付けたのがおかしい。
人から恐怖や思い込みを取り除くことは出来ませんが、それらに駆られてあせって行動すると、たいていはひどく悪い結果に繋がります。
結局のところ、僕らに出来ることは、消費(浪費)生活をどこまで抑えるかということしかないと思います。