今日、子供を学校に迎えに行った帰り、見ました、小海線のハイブリッド車両。
世界初というけど、なにが世界初なのか良くわからなかったのです。
エンジンで発電してモーターを駆動する方式は古~くからある方式ですしね。
19世紀末には出てます。
自動車、鉄道ほか、有名どころじゃポルシェの戦車“ティーガー(P)"駆逐戦車(P虎なんていう人も)がありますね。
あれは、使い物にならなかったと聞いていたけど、実は結構イケタらしいと最近では再評価されているそうですね。
日本の鉄道車両でも古い言い方をすれば、電気式気動車と呼ばれていました。
小海線のどこが画期的なのかというと、優秀なバッテリーや、モーター、高電圧大電流の制御=パワーエレクトロニクスの組み合わせということのようですね。
でも、基本的な考え方は前々世紀からあったわけです。
どうも最近は、科学というと便利で簡単で手っ取り早いものというイメージがあるようですが、それは先人たちの何世代にもわたる積み重ねの結果だけを見ているからで、本当は科学というのは、「急がば回れ」的な、遠回りだけど確実で誰でも理解出来る手順を踏んで積み重ねてきたものだと思います。
僕が今修復しているオルガンは1930年(昭和5年)に日本に来たものです。
電気と空圧を利用して、パイプでの風を制御しています。
この制御方法は、可燃性ガスの弁を電気で制御するとか、さらに身近なところでは、洗濯機の水を出したり止めたりする弁も同様の原理です。
ちゃんと現代にもその子孫を遺しているのです。
ちなみに、オルガンのパイプ=笛がなぜ鳴るのかということさえ、実は科学的にはまだはっきりしていないそうです。(以前はカルマン渦説だったようですが、どうも違うらしい)
僕らは、科学的には未確認のことを、伝承された経験値と試行錯誤で扱っているのです。
錬金術師の系譜に連なる生き方ですね。
先日、修復チームの仲間と話していた時のこと。彼は、この作業を若手の楽器メーカーの技術者(職人とはちと違う)に体験させたいと言うのです。
そのとおりなのです、こういった仕事は今後日本で何回あるかわからない(向こう数十年で、5回には満たないでしょう)ので、若手に見せるべきなのです。
でもねえ、納期を切られてしまったので、余分な時間や、まして失敗してやり直しというリスクは負えないのです。
今回は無理でも、同様の形式のオルガンを一台保有しているので、それを使って「オルガン修復体験講座」でもやってみようかな。
そろそろ次の世代の人達のために何かしないといけないと思うのです、自分が生活するだけで精一杯なんですけどね。
世界初というけど、なにが世界初なのか良くわからなかったのです。
エンジンで発電してモーターを駆動する方式は古~くからある方式ですしね。
19世紀末には出てます。
自動車、鉄道ほか、有名どころじゃポルシェの戦車“ティーガー(P)"駆逐戦車(P虎なんていう人も)がありますね。
あれは、使い物にならなかったと聞いていたけど、実は結構イケタらしいと最近では再評価されているそうですね。
日本の鉄道車両でも古い言い方をすれば、電気式気動車と呼ばれていました。
小海線のどこが画期的なのかというと、優秀なバッテリーや、モーター、高電圧大電流の制御=パワーエレクトロニクスの組み合わせということのようですね。
でも、基本的な考え方は前々世紀からあったわけです。
どうも最近は、科学というと便利で簡単で手っ取り早いものというイメージがあるようですが、それは先人たちの何世代にもわたる積み重ねの結果だけを見ているからで、本当は科学というのは、「急がば回れ」的な、遠回りだけど確実で誰でも理解出来る手順を踏んで積み重ねてきたものだと思います。
僕が今修復しているオルガンは1930年(昭和5年)に日本に来たものです。
電気と空圧を利用して、パイプでの風を制御しています。
この制御方法は、可燃性ガスの弁を電気で制御するとか、さらに身近なところでは、洗濯機の水を出したり止めたりする弁も同様の原理です。
ちゃんと現代にもその子孫を遺しているのです。
ちなみに、オルガンのパイプ=笛がなぜ鳴るのかということさえ、実は科学的にはまだはっきりしていないそうです。(以前はカルマン渦説だったようですが、どうも違うらしい)
僕らは、科学的には未確認のことを、伝承された経験値と試行錯誤で扱っているのです。
錬金術師の系譜に連なる生き方ですね。
先日、修復チームの仲間と話していた時のこと。彼は、この作業を若手の楽器メーカーの技術者(職人とはちと違う)に体験させたいと言うのです。
そのとおりなのです、こういった仕事は今後日本で何回あるかわからない(向こう数十年で、5回には満たないでしょう)ので、若手に見せるべきなのです。
でもねえ、納期を切られてしまったので、余分な時間や、まして失敗してやり直しというリスクは負えないのです。
今回は無理でも、同様の形式のオルガンを一台保有しているので、それを使って「オルガン修復体験講座」でもやってみようかな。
そろそろ次の世代の人達のために何かしないといけないと思うのです、自分が生活するだけで精一杯なんですけどね。















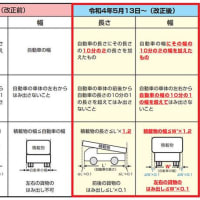




やっぱり、公開した方が良いですよね。
そのオルガンも「シアターオルガン」で、本来、無声映画のBGMや効果音(車のクラクションや、ピストルの音が出るのもあります)、劇場や競技場(ハーフタイムの演し物の伴奏とか)の音楽効果のために出来た楽器です。
自動演奏装置付もよくあります(紙のロールに穴を開けたメディアね)。
なので、ケースを分割して運べるようにして、劇場の舞台などに持っていけるような形にしたいと思っています。
ハイブリッド技術って結構昔からあるんですよね。ただ、なんでもかんでもハイブリッドってのはどうかと・・・特に北杜市ではね・・・。
技術史って面白いですよね。エピソードやドラマ満載です。
昔のドイツのメカは凝り過ぎなのがマニア心をくすぐります。
自動車でも、毎週数十カ所の給脂だの、数ヶ月毎のオーバーホールだのとんでもないデリケートな機械を驚異の整備能力で運用していたそうですね。
そこそこの性能ながらシンプルで壊れにくいアメリカのメカとは対照的です。
ハイブリッド車両の試験を小海線でやるのは、やはり高低差でしょうね。
回生ブレーキの効果が良く現れて通常のディーゼル車両との差がアピールし易いですから。
うまい(ズルい?)作戦です。
うちのあたりは急坂ですからね、坂を下りる度にこのエネルギーを蓄積できたらなあ、と思います。