アムステルダム、ひろにゃん20代のある日。
その古本屋は確か水曜の午後から営業して夜は5時頃まで、木金は一日中(朝10時から夜5時)土曜は午前のみと営業時間が短いのです。
水曜の朝、遅い朝食を摂って、トラム(路面電車)に乗って、まずはコンセルトヘボウへ。
昼過ぎだったかな、無料の公開リハーサルが行われます。
普段着でリラックスした雰囲気ではありますが、世界の一流の演奏家によるコンサートを楽しめます。
リハーサルなので、途中で曲を止めて調整することもあります。
これはこれで興味深いものです。
コンセルトヘボウからまたトラムで、ダム広場近くのマーケットへ戻ります。
たっぷりマヨネーズのフライドポテトなんぞを食べながら、古本屋へ歩きます。
僕は、方向感覚は良い方だと思うのですが、このお店に行くときは何故かよく道を間違えたものです。
放射状のヨーロッパの旧市街の道は碁盤の目の感覚に慣れた頭では、具合が悪いのです。
お店は老夫婦が店番をしています。家族で音楽教室もやっているようで、店には、調子っぱずれの楽器の音が聞こえてきます。でも、あの調子っぱずれが、もしかしたらその後スヴェーリンク音楽院に行って、一流の演奏家になっているかもしれません。
僕は、軽く会釈をして置いてある脚立を持って書棚に向かいます。
僕の興味の対象であるオルガン関係の書籍は、書棚の高いところにあるのです。
かつて間口の大きさが課税基準だったアムステルダムの家は、背が高くうなぎの寝床のような奥行きの深い細長い建物が多いのです。その奥行きの深さと間取りは他国者の常識を越えます。それで、アンネ・フランクも隠れていられたのですね。
そんな建物の作りなので、書棚も高く作られ、幅の狭さを補っているのです。
ひとしきり眺めて、新しい発見がないことを確認すると、僕は店番のおじいさんのところに行きます。
ポケットから、くしゃくしゃになったメモを取り出します。図書館で見つけた本の名前です。
その本の古本を取り寄せられるか、値段はいくらなのかを調べてもらうのです。
届いた本は内容を見てみて、要らなければそのままお店の在庫となります。
別に料金は取られません。
しばらくおじいさんと雑談をしていると、おばあさんがコーヒーを持って来てくれます。それから3人でまたひとしきり話をして僕は店を出ます。
冬のオランダは午後4時頃でもう真っ暗です。
行き付けのカフェでビールを飲んで帰ります。
収穫があった日はまっすぐに部屋に戻って、わくわくしながら本を開きます。
と、こんな感じです。
あー、なんか優雅。
古本屋の話は続きます。
その古本屋は確か水曜の午後から営業して夜は5時頃まで、木金は一日中(朝10時から夜5時)土曜は午前のみと営業時間が短いのです。
水曜の朝、遅い朝食を摂って、トラム(路面電車)に乗って、まずはコンセルトヘボウへ。
昼過ぎだったかな、無料の公開リハーサルが行われます。
普段着でリラックスした雰囲気ではありますが、世界の一流の演奏家によるコンサートを楽しめます。
リハーサルなので、途中で曲を止めて調整することもあります。
これはこれで興味深いものです。
コンセルトヘボウからまたトラムで、ダム広場近くのマーケットへ戻ります。
たっぷりマヨネーズのフライドポテトなんぞを食べながら、古本屋へ歩きます。
僕は、方向感覚は良い方だと思うのですが、このお店に行くときは何故かよく道を間違えたものです。
放射状のヨーロッパの旧市街の道は碁盤の目の感覚に慣れた頭では、具合が悪いのです。
お店は老夫婦が店番をしています。家族で音楽教室もやっているようで、店には、調子っぱずれの楽器の音が聞こえてきます。でも、あの調子っぱずれが、もしかしたらその後スヴェーリンク音楽院に行って、一流の演奏家になっているかもしれません。
僕は、軽く会釈をして置いてある脚立を持って書棚に向かいます。
僕の興味の対象であるオルガン関係の書籍は、書棚の高いところにあるのです。
かつて間口の大きさが課税基準だったアムステルダムの家は、背が高くうなぎの寝床のような奥行きの深い細長い建物が多いのです。その奥行きの深さと間取りは他国者の常識を越えます。それで、アンネ・フランクも隠れていられたのですね。
そんな建物の作りなので、書棚も高く作られ、幅の狭さを補っているのです。
ひとしきり眺めて、新しい発見がないことを確認すると、僕は店番のおじいさんのところに行きます。
ポケットから、くしゃくしゃになったメモを取り出します。図書館で見つけた本の名前です。
その本の古本を取り寄せられるか、値段はいくらなのかを調べてもらうのです。
届いた本は内容を見てみて、要らなければそのままお店の在庫となります。
別に料金は取られません。
しばらくおじいさんと雑談をしていると、おばあさんがコーヒーを持って来てくれます。それから3人でまたひとしきり話をして僕は店を出ます。
冬のオランダは午後4時頃でもう真っ暗です。
行き付けのカフェでビールを飲んで帰ります。
収穫があった日はまっすぐに部屋に戻って、わくわくしながら本を開きます。
と、こんな感じです。
あー、なんか優雅。
古本屋の話は続きます。















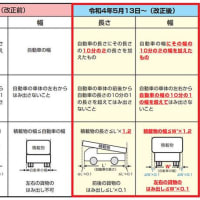




過ごしたなんて・・・
その光景をじっと見つめていたい
こういうお話を永遠に聞いていたい
そんな気持ちです
あなたはフランスで学生をされていたのでしょう。
いいなあ!
今は田舎で民家もまばらなところで暮らしているので縁がないけれど、整った町並みというのも好きなのです。
小さいけれど、学生が多くて活気のある町も良いなあと思います。
デルフトの旧市街の中世の面影の残る町並み、運河沿いに小さなパイプオルガン工房がありました。
それはそれは素敵なところで、あんなところで暮らすのもいいなあと思ったものです。
まだまだわからないよ。
ン十年後、どこかの町の修道院の廃墟の一角で風琴屋工房を構えていたりしてね。
>届いた本は内容を見てみて、要らなければそのままお店の在庫となります。
>別に料金は取られません。
え~
進んでいるなぁ…。
やっぱり本は手にとって内容を見てみたいですよね。
あのやり方がシステムとしてあったのかはわかりません。
お店のおじいさんの好意かもしれません。
交渉してみた結果です。
あの頃は事前情報なしに行動することが多かったので(今もか!)、思い立ったらとにかくまず交渉してみるというやり方でした。
ほんとはシャイなので、そういうことはあまり得意ではないのですが。
やってみると、ドイツでバイク(250cc)の所有、登録も住所なしの外国人でも出来ましたし、オランダでは博物館の出入り自由(書庫や修復工房も)の許可ももらえました。
結果を恐れずにやってみるということは大事です。