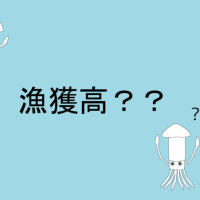多自然川づくりをされている長良川(岐阜県)。
「水のみちの連続性を確保」を目指し、魚道を670箇所設置されています。
長良川は、岐阜県の長木曽川三川の一つで、伊勢湾に流れる一級河川。
116㎞、流域面積1985k㎡。
日本三大清流の一つ。明治の工事で、木曽川と分流。

長良川は鵜飼が有名。
皇室御用達の鮎の御料場がある川です。
環境省の名水100選。
魚道がそれほどあるのもうなづけます。
まちづくりのうちの一つの取り組みとして、「清流の国ぎふ」として、自然共生の普及と推進に取り組まれています。
中でも、長良川の魚道の遡上の取り組みが研究されています。
国土交通省HP
「岐阜県における河川魚道の機能回復事業
~水のみちの連続性を目指して!~」 より 引用をしています
「水のみち」の連続性の取り組みに対しての状況
水のみちの連続性を確保することを目指して、「魚がのぼりやすい川づくり事業」を進めている。
・魚道の点検体制の確立
魚道のカルテを作成し、きめ細かく状況の把握をしている
機能不全となった魚道には、改築・修繕を実施

岐阜県民からなるボランティア等によって点検体制を実施し、維持管理も行う
機能不全や不具合のある魚道は機能回復、修繕を実施する
平成24年度より、豊かな自然環境の保全と再生のための税(県民一人あたり1000円/年)(清流の国ぎふ森林・環境基金税)も利用している
・取り組みの成果
過去5年間の魚道の点検と把握と修繕により、A判定が増え、C判定が減った
・今後の課題
今後の5年間で、96%の魚道が遡上可能となる予定
C判定を対策後、再び機能不全になる例がある
県管理以外の魚道の対策に、他の管理者との情報の共有が必要等
・・・・
こうした取り組みを続けられ、改善を重ねられて、とても優良なところと思います。
また、岐阜県は川と農業用水路をつなぐ「水のみち」の取り組みも忘れていません。
・・・・・
岐阜県河川課HP
清流の国ぎふ 水みちの連続性確保にむけた取組み~河川環境と農村環境の生態系ネットワークの再生~
・・・・・・
こうした取り組みは、
川ー農業水路ー水田の「水のみち」の連続性の確保
=
生態系ネットワークの再生
につながります。
こうした取り組みをすることにより、農作物のブランド化、イメージ良好により、効果が上がる可能性も持っているとのこと。
「水のみちの連続性」を確保し、一度の工事で終わりではないようにしたいですね(多自然工事や魚道は売り切り型ではなく、その後も継続して調査が必要、随時改善も必要)
また、逆効果にならないようにも(魚に傷をつけたり、遡れない、絶滅させる)
農業用水路、田畑ともつなぐことも合わせて忘れないようにしたい。
 (写真ACより)
(写真ACより)
長良川は伊勢湾にそそぐ平野は都市化が進んだ都市です。
魚たちがする本来の活動のように、自由に行き来できるような川になれば、すごいことです。
川は大きく、清流、いろいろな魚が遡上したり、生きる可能性は大きく秘めていると思います。
しかし、またこうした取り組みは試行錯誤の段階と思われます。
果たして、川なり、魚道なりワンドなり、全国的にこうした均一なもので良いのかと、疑問も沸きます。
昔は、そこに特質、偶然出来たものが、ワンドなり魚道だったりして、そこに鮎でもフナでもそこだけの固有の鮎などがいたでしょう。
その川や地形独特のものがあっても良いのでないでしょうか。
江戸時代ぐらい前の写真が残っていればと思うのですが・・・なかなか難しいでしょうね。
とりあえず、いきなり大自然まで持って行くのは・・・?
今すぐは難しい話なのかもしれません。
長良川は今までも5年取り組まれ、その後も継続して5年間また取り組む方針でおり、魚道も管理する仕組みを市民も入れて作り、だんだんと改善を重ねておられます。
地上の陸上部であっても同じで、生態系ネットワークをつなげるなり、多様性を確保するとしても、ずっとその後も絶滅へ進んでないか?うまく行っているか、の観察は必要になってくるでしょう。
ですから、まだどこも川とか水路や、生物多様性に取り組んでない市町村などは、今すぐでも何かしら取り掛かかってもらいたいですね。
今回は長良川周辺の情報が多くあったので調べましたが、他にもいろいろ頑張って取り組まれているところがあると思います。
今後も、生物多様性、生態系ネットワークの構築などの取り組みや事業について見ていきたいと思います。