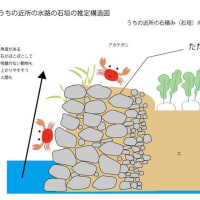広島大学にオオサンショウウオ研究センターが出来ました。
在来種の保全・調査
在来種と交雑種の遺伝子判定が以前は2日かかったものが、1,2時間で出来るようになるとのことです。
オオサンショウウオというのは、在来種と交雑種が見分けがつきにくいものだそうです。
1970年代に、食用のためか、何かのためか理由ははっきりしませんが、日本に入り、外に定着したようです。
近年、その外来種と日本の在来種の交雑が、各地でかなり広がっていることが発覚しました。
このまま交雑し続ければ、日本の在来種が近いうちになくなり、絶滅するかもしれないと言われています。
しかし、交雑種といえ、簡単に殺していいのか。もう多くて水槽がいっぱいで、放流はしたくないのだが、殺して捨てていいのか。一つの同じ命。捕らえたイノシシとも同じ。島の人は、漁をしても食べる量だけしか漁をしない・・というのが以前にも「オオサンショウウオ」の記事でも書いた人です。
その広島大学総合博物館・清水則雄准教授が、初代センター長に就任されたそうです。
オオサンショウウオの未来ついて、明るいニュースと思います。
これからもオオサンショウウオのことを見て行きます。
オオサンショウウオ 日本の在来種を守れ 広島大学に研究センター設立 | TBS NEWS DIG
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/home_tv/region/home_tv-20230501205725