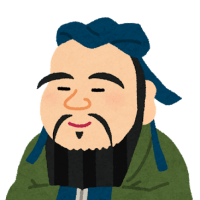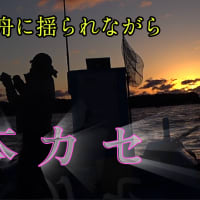論語を現代語訳してみました。
述而 第七
《原文》
子曰、自行束脩以上、吾未嘗無誨焉。
《翻訳》
子 曰〔のたま〕わく、自〔みずか〕ら束脩〔そくしゅう〕を行〔おこ〕なう以上〔いじょう〕には、吾〔われ〕 未〔いま〕だ嘗〔かつ〕て誨〔おし〕うる無〔な〕くんばあらず。
《現代語訳》
孔先生はつづけて、次のように仰られました。
ある程度の責任や義務を果たすことの "意義" を知った人であれば、私は〈誰であろうと等しく〉心を込めて教えなかったことはない、と。
〈つづく〉
《雑感コーナー》 以上、ご覧いただき有難う御座います。
束脩とは、『脩』は干し肉のことで、当時では入門する際に干し肉10束を納める慣習があったようですから、孔子もまた、この慣習にならって、弟子となる人から束脩を納められていたんだと思われます。
なお、ここでは束脩を納めることの意味を「責任と義務を果たすこのと "意義" を知る」と捉え、語訳してみました。このことによって、孔子塾の門をたたくにあたっては、それなりの覚悟を有していなければならず、また、『自ら』という翻訳についても、両親などから束脩を用意してもらうのではなく、自らの意志でもって束脩を用意し納めることが大事なんだよ、と孔子は言っているようにも思えてきます。
そうした意味において、弟子となるからには「ある程度の責任と義務を果たすことの "意義" を知った人」と語訳してみた次第です。
※ 関連ブログ 束脩を行う
※ 孔先生とは、孔子のことで、名は孔丘〔こうきゅう〕といい、子は、先生という意味
※ 原文・翻訳の出典は、加地伸行大阪大学名誉教授の『論語 増補版 全訳註』より
※ 現代語訳は、同出典本と伊與田學先生の『論語 一日一言』を主として参考