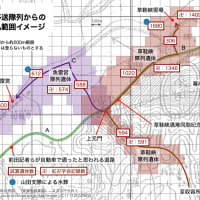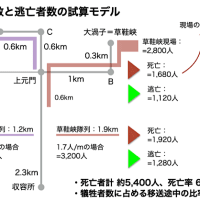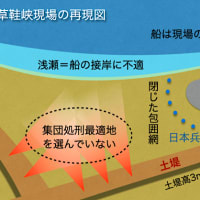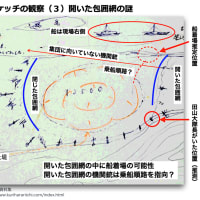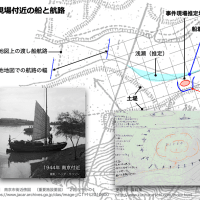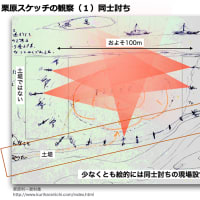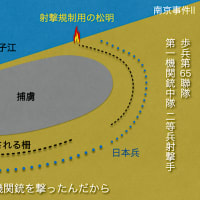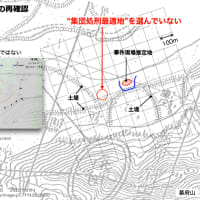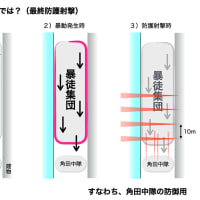被災地では、震災から時間を経ると必要な支援物資の種類が増える。
当初:水と食料、毛布など
以降:日用品、衣類、雑貨、衛生用品、など
従って、支援物資の支給を継続する場合、御用聞きあるいは注文リストでの発注が必要になる。被災者側のニーズを聞き取りもせずに一方的に送ると必ず迷惑になる。
また、熊本地震の被災地では、車中泊避難者などが支援物資支給の対象から漏れている問題も指摘されている。
そこで、東日本大震災のある自治体ではどうしていたかの実例を紹介する。
・仮設住宅、在宅被災地域に限らず、被災地区の代表者を決定
・地区代表者は、被災者の代表者の場合もあるが、その地区を継続的に支援してるNPO団体の場合もある
・地区代表者は、行政に登録(建前)
・行政は、支援物資の在庫管理と搬出入管理をNPOに委託
・実務的には、地区代表者は地区内の被災者から要望を取りまとめて必要物資の注文リストを作成
・注文リストを元に、物資管理NPOと折衝(在庫との調整)
・日時を調整のうえ、配送または引き取り
・以上の作業を、数日~10日程度のルーティーン作業で繰り返す
熊本地震被災地においても、今後も物資支給を継続するなら似たような体制を組む必要があると考える。
在宅であれ車中泊であれ、被災者個人がバラバラでは支援の手は届かないだろうと思われる。

(追記)
Q1:被災者個人が取りに行ったらどう?
A1:私がお手伝いした東北のある自治体では、支援物資倉庫(集積所)へ被災者個人が自分の分の物資を取りに行くことは禁止(拒否)しました。
なぜなら被災者個人の身元までいちいち判別していられませんし、個人が倉庫内で欲しいものを好き勝手に物色されても対応できません。多くの地区に限られた物資を公平に配分する意味でも、調整が必要です。また、大型トラックでの搬入日に個人が来られても危険です。
そういった理由から、あくまで事前登録した地区代表に限定しました。
Q2:行政は、なぜ支援物資の在庫管理と搬出入管理をNPOに委託するの?
A2:行政職員は復旧や各種事務手続き業務に忙殺されています。行政職員が支援物資の在庫管理や配送計画、さらには物資の積み下ろしや集配作業をすることは実務的に不可能です。こういった業務は経験のあるNPOに丸投げした方が効率的です。
以上。