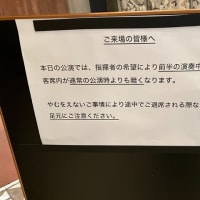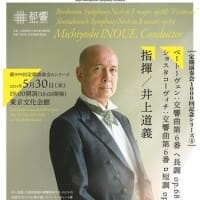(承前)
- 1940年に三国同盟を締結し、日独伊ソの四国が提携し米英にあたるという日本の方針があったとき、1941年6月にドイツはソ連に進攻を開始した、もし、この時、チャーチルがいうように日本が本気で自国のことを考え全体を見極めていたら、ドイツが約束を破ったのを理由に三国同盟から離脱して中立となり、戦争不参加を決め込むこともできたのです。ドイツの勝利を信じていた日本は三国同盟に固執した
(コメント)
半藤氏のいうとおりでしょう、一度決めるとその決定に都合のよい事実しか見なくなるのが今に続く日本人の習性でしょう - 昭和16年4月、日米交渉打開のため新鋭米派の野村吉三郎海軍大将を駐米大使に赴任する、これをこころよく思わなかったのが反英米だった外務省でした、それは昭和14年9月に野村さんが外務大臣に就任して反英米派の幹部を交代させる人事をやったことがすごい反発を招き、当時の阿部内閣が貿易省を作る構想を打ち出したとき外務省の全部局が猛反対し、キャリア130人が全員辞表を出して大騒動になった経緯があったからです、その野村さんが中米大使になった時にまた反野村でかたまっていく
(コメント)
外務官僚でありながら国際情勢を観る眼がなく、さらに気にくわない外務大臣に反発して国家を危うくする、こういった過去をしっかり書いたことは高く評価できる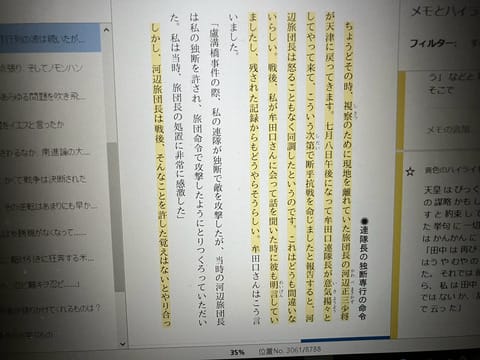
- 日米開戦の攻撃30分前に交渉打ち切りの最後通牒が手渡されることになったが、大使館外交員どもの怠慢というか無神経が災いし、結果的に通告が1時間遅れとなった、これは野村大使に対する外務省エリートたちの反感、不信、不協力の態勢がなしたことでしょう
(コメント)
本書の中で、違う理由で遅れたという議論も紹介されているが、私も半藤氏の外務官僚に対する怒りに同意したい、そしてさらに呆れるのは、本書には書いてないが、戦後この日本大使館のキャリア外交官たちが公職追放された来栖三郎以外ほとんど出世することだ - 真珠湾攻撃を多くの作家、評論家も万歳万歳の声を上げた、評論家の中島健蔵、小林秀雄、亀井勝一郎、作家の横光利一など、ただ一つだけ注意しておかないとならないのは、開戦の詔書には今までの3つの大戦(日清、日露、第1次大戦)は国際法遵守を述べていたが、今回はそれがないことです。真珠湾攻撃に宣戦布告がなかったことと、開戦布告前に開戦の意図を隠しマレー半島に上陸しタイ国に軍隊を送っていたからだ
(コメント)
開戦の詔書の問題点については知らなかった - ミッドウェイ海戦から10日ばかりたった6月18日、日本の文学者が大同団結し、「日本文学報国会」を作りました、会長徳富蘇峰、菊池寛、太田水穂、川上徹太朗、深川正一郎、尾崎喜八が各部門の代表になり、吉川英治が「文学者報道班員に対する感謝決議」を唱和して朗読した、自分たちもまた、この戦争に勝つために大いなる責任を与えられ、頑張ろうじゃないか、というのです。日本の文学者はどんどん戦争謳歌、戦意高揚の文学になります
- 昭和20年8月9日、日ソ中立条約を破りソ連軍が満洲に進攻して来た、8月14日ポツダム宣言受諾を通知したのだからソ連もわかっているだろうと思い込んだがこれが浅はかだった、ポツダム宣言受諾は降伏の意思表示でしかなく、降伏の調印がなされるまでは戦闘は継続されることを知らなかった、満洲の悲劇が始まるのです
(コメント)
こういうことは知らなかった - 昭和史の20年がどういう教訓を私たちに示したか、その一つは何か起ったときに、複眼的な考え方がほとんど不在であったというのが昭和史を通じて日本人のありでした
(コメント)
その通りでしょう、リーダーたちのみならず、新聞がそれを助長していたでしょう、半藤氏も述べているが、昭和史20年の教訓は今でも通用するでしょう - 昭和史全体を見てきて結論として一言で言えば、政治的指導者も軍事的指導者も、日本をリードしてきた人々は、なんと根拠なき自己過信に陥っていたことか、ということでしょうか。そして結果がまずくいったときの底知れぬ無責任です、今日の日本人にも同じことが見られて、現代の教訓でもあるようですが。
(コメント)
その通りでしょう。そして新聞が何をしてきたのかについても総括してほしかった
いろいろ勉強させられた良い本でした。
(完)