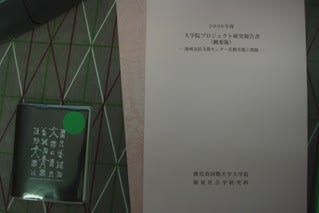
【プロジェクト研究】
大学院の中では、「プロジェクト研究」といっています。研究に必要な通信費や印刷費用は、大学院の事務費に計上されています。
鹿児島国際大学→大学院→(福祉社会学研究科)
【厚生労働省の手引きから】
この「地域包括支援センター」とはどういうものなのか?以下のサイトは、実務家向けのものですが、事例紹介(9件)などもありますのでリンクします。
地域包括支援センターの手引き
【現場からは批判が相次ぐ】
masaの介護福祉情報 2006.10.19付け記事など
現場から、この地域包括支援センターの運用に関する膨大な批判記事がエントリーされています。
*ブックマークしているブログでは、「岩清水日記」のカテゴリ「地域包括支援センター」には58エントリーがアップされています。
【研究論文】
この地域包括支援センターは、新しい制度ですが、すでに多くの実態調査が行われ、研究論文もインターネットで読むことができます。最近の山口県立大学内田充範氏の論文を例に挙げます。
包括支援センターにおける社会福祉士の役割
【鹿児島県の実情】
2008年度、鹿児島国際大学の調査は、大学院生(研究生なども含む)7人+教員3人で構成され、郵送法で、得られた回答は、施設で54、スタッフで322でした。
この結果は、報告書で詳細に分析紹介されています。
概要版では、要点をまとめています。
以下、「概要版」の末尾に記載されている「全体的考察」pp.29-31の要点をあげておきます。
○ 介護予防に追われて本来の業務ができない。
○ 「権利擁護」業務の達成度は低い。
○ 要支援者のマネジメントを地域包括支援センターにさせた結果、それまでの居宅介護支援事業者を要介護担当にしてしまったのは構造的な問題点だ。
○ 現在の業務に対するスタッフの満足度は低い。
○ 今後求められるスタッフとしては、精神保健福祉士や認知症の専門家が挙げられている。
大学院の中では、「プロジェクト研究」といっています。研究に必要な通信費や印刷費用は、大学院の事務費に計上されています。
鹿児島国際大学→大学院→(福祉社会学研究科)
【厚生労働省の手引きから】
この「地域包括支援センター」とはどういうものなのか?以下のサイトは、実務家向けのものですが、事例紹介(9件)などもありますのでリンクします。
地域包括支援センターの手引き
【現場からは批判が相次ぐ】
masaの介護福祉情報 2006.10.19付け記事など
現場から、この地域包括支援センターの運用に関する膨大な批判記事がエントリーされています。
*ブックマークしているブログでは、「岩清水日記」のカテゴリ「地域包括支援センター」には58エントリーがアップされています。
【研究論文】
この地域包括支援センターは、新しい制度ですが、すでに多くの実態調査が行われ、研究論文もインターネットで読むことができます。最近の山口県立大学内田充範氏の論文を例に挙げます。
包括支援センターにおける社会福祉士の役割
【鹿児島県の実情】
2008年度、鹿児島国際大学の調査は、大学院生(研究生なども含む)7人+教員3人で構成され、郵送法で、得られた回答は、施設で54、スタッフで322でした。
この結果は、報告書で詳細に分析紹介されています。
概要版では、要点をまとめています。
以下、「概要版」の末尾に記載されている「全体的考察」pp.29-31の要点をあげておきます。
○ 介護予防に追われて本来の業務ができない。
○ 「権利擁護」業務の達成度は低い。
○ 要支援者のマネジメントを地域包括支援センターにさせた結果、それまでの居宅介護支援事業者を要介護担当にしてしまったのは構造的な問題点だ。
○ 現在の業務に対するスタッフの満足度は低い。
○ 今後求められるスタッフとしては、精神保健福祉士や認知症の専門家が挙げられている。

























