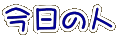【きょうの人】 0531 祐天上人(明蓮社顕誉) 生誕 江戸の呪術師 浄土宗大本山増上寺36世法主
![]()
独善的な判断で、気になる人を選んでご紹介しています。
そこに歴史や思想、人物、生き方などを感じ取って、日々の生活やビジネスに活かしてくださると幸いです。
■ 祐天上人(明蓮社顕誉) 生誕 江戸の呪術師 浄土宗大本山増上寺36世法主
ゆうてん
寛永14年4月8日(1637年5月31日)- 享保3年7月15日(1718年8月11日)
浄土宗大本山増上寺36世法主で、江戸時代を代表する呪術師、字は愚心、号は明蓮社顕誉です。
徳川五代将軍綱吉の命により正実大厳寺に住み、飯沼広経寺や、東京小石川の伝通院を経て、増上寺に住し、三六世の法席を継ぎます。
密教僧でなかったにもかかわらず、強力な怨霊に襲われていた者達を救済、その怨霊までも念仏の力で成仏させたという伝説があるほどです。
祐天の除霊伝説は存命中に書かれた『死霊解脱物語聞集』など、大衆向けに書かれた出版物によって広まりました。
その後、当時盛んだった説教節や、18世紀半ばになって書かれた『祐天大僧正御伝記』などの伝記の中で祐天の除霊譚は地蔵菩薩の化身として語られ、後々まで庶民の間で信じられてきました。
八十二才で歿しています。

◆ 【きょうの人】 バックナンバー
歴史上で活躍したり、仏教など宗教関係の人であったり、ジャンルはいろいろですが、彼等から、学ぶところが多々ありますので、それをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b57a13cf0fc1c961c4f6eb02c2b84c9f
◆ 【今日は何の日】は、毎日発信しています。
一年365日、毎日が何かの日です。 季節を表す日もあります。 地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。 誰かの誕生日かも知れません。 歴史上の出来事もあります。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b980872ee9528cb93272bed4dbeb5281
◆ 【経営コンサルタントのひとり言】
経営コンサルタントのプロや準備中の人だけではなく、経営者・管理職などにも読んでいただける二兎を追うコンテンツで毎日つぶやいています。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a0db9e97e26ce845dec545bcc5fabd4e
【 注 】
【きょうの人】は、【Wikipedia】・当該関連サイトを参照・引用して作成しています。