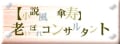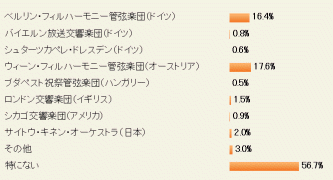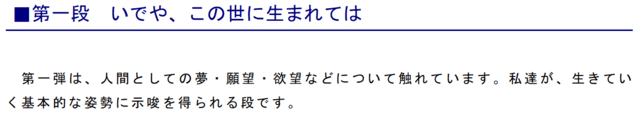【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 3月29日 「仁義」とは 本来の意味は?
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
3月29日(金)
小林製薬製の「 紅麹 」成分入りのサプリメントで死者が5名と、被害者が増えてきています。想定していない、天然化合物の一種「プベルル酸」が含まれていることがわかったそうですが、それが原因かどうかは不明のようのです。
プロ野球が開幕しました。今年から新たに監督になったチームもあり、サッカーに押され気味を盛り返すことができるのでしょうか。
知人からビデオ通話のコンタクトがありました。
わたくしのブログの話になり、「仁義」とは、暴力団や寅さんをイメージしていたけど、本来の意味を知ることができて良かったと、リップサービスを残してくれました。

■ 仁義とは
毎年4月25日に開かれる孔子祭では、孔子や儒教の先哲を祀る儀式が行われます。中国で儒教が国教となったときに、釈奠(せきてん/しゃくてん)と呼ぶようになりました。
孔子は紀元前5~6世紀の春秋時代における中国の思想家、哲学者で、儒家の始祖でもあります。幼くして両親を失い、孤児となってからも苦学をつづけたそうです。しかし、生きている間は無冠で、一人の学者であったようです。しかし、後の漢代(前漢)に司馬遷は『史記』の中ででは、孔子の功績を「王に値する」と記述しています。
孔子は、それまでにあった原始宗教を今日の儒教に体系化しました。孔子の考えの基本は「仁(じん)」です。「仁が貫かれるところに道徳が保たれる」と説いています。
「仁」は徳の一つで、人間関係の基本、人間愛をさす倫理規定でもあります。主に「他人に対する親愛の情、優しさ」をさし、仁と、人間の行動に関する概念である義を合わせて、「仁義」という表現もよく知られています。
仁義というと、ある種の世界の言葉のように思われがちですが、人間のあり方の基本のことです。むしろその世界だけに限定すると、映画などでの情報でしかありませんが、一般の人よりもむしろ仲間意識、結束感は強いのではないでしょうか。
今の日本は、残念ながら他人に対する思いやり、気配りがあまりにも希薄になっていると平素思っています。ところが、東日本大震災のような時には、眠っている「仁」が呼び起こされるのか、義援金やボランティア活動などへの参加という形で現れてきます。
「まだまだ日本は捨てたものではない」とテレビでどなたかが言っていましたが、「仁」ということを考え直す時間を各自がとっても良いと思います。もちろん、私自身も実行します。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】などをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930
■【今日は何の日】 3月30日 ■ ひまわり落札 ■ 白隠祭 一年365日、毎日が何かの日

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
■ 竜安寺石庭を囲む壁の向こう側はどうなっている? 329
史跡・特別名勝として知られます竜安寺の方丈庭園を知らない人はいないというほど日本でも代表的な石庭です。
その幅は、わずか22メートル、奥行きに至っては10mに過ぎませんが、そこに大宇宙を感じます。
お恥ずかしながら、そのように説明されますので、そういうものなのだろうと思っています。
15個の石が無造作とも思える配置にあるだけです。
その大宇宙を囲む壁の向こう側はどうなっているのか・・・
宇宙の果ては、どうなっているのでしょうか・・・
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/611f7991762eae7a53b9bbddf7b037ed
■【管理職】転職流動化時代の管理職の心得
「グローバル」というのは境界をなくすことでもあります。企業間の境目が薄くなり、人の流動化時代は、経験やスキルを重視する「ジョブ型雇用」の普及もあり、ますます一般化してくるでしょう。管理職として、せっかく育てた部下ですが、それも有能な部下ほど流出してしまう時代です。
部下に転職されないためには、転職の理由をまず理解していなければならないでしょう。
転職の理由はいろいろありますが、かつては人間関係に起因する退職が多かったようです。近年は、キャリアアップ思考で、更なる成長の機会を求めて転職する人が多いようです。また、期待していることと現実との乖離や、自分に対する評価が不充分である等も理由となっています。若手の場合には、仕事が多すぎる、仕事の範囲が広すぎる等々、レベルが比較的低いものもあります。
管理職として、転職気運を事前に察知しておきたいですが、部下の気持ちを読むことは難しく、適切な対応をとれないことからやめられてしまうことは避けたいです。そのためには、あまりにも月並みですが、平素の対応、コミュニケーションに腐心すべきです。
転職を考えるようになった部下は、何らかのシグナルを発信しているものです。それを見落とさないことが肝要です。
社員から転職しそうな雰囲気を感じ取ったときに、私は、「最近、君の○○のようなことが気になっているのだけれど・・・」とぶつけるようにしてきました。この時に肝要なのは、「○○」というように具体的なことで声をかけることです。「最近、どう?」などという抽象的な声かけでは、相手は、何と答えたら良いのかわかりませんし、こちらが期待することとは異なる局面の回答がかえってきて、会話の歯車が合いません。
声をかけたら、懸念課題について、一緒に問題対処に取り組みたいことも伝えることが必要です。この方法が成功するのは、平素の信頼関係づくりが必要です。平素から、話しやすい雰囲気を醸し出して、実践し、真摯に話し合うことの積み重ねです。
平素から、部下のキャリアプランについて話し合っていますと、事前予知も可能になりますし、部下にとっても、社内での今後の展望にも繋がります。しかし、人事というのは自分ひとりで決められる問題ではないだけに、「コミットしてもらえた」と部下が感ずるような表現は厳に慎まなければなりません。
平素から、部下の夢や目標、身に着けたいスキルなどを聞き出し、それをアップデートして行くことをします。この会社で働くことのメリットを、感じ取ってもらえるような話し方も必要です。部下の存在感を知ってもらう話も必要ですし、会社として、その人を必要としていることを、部下の成功事例などを挙げながら伝えることも良いでしょう。
また、転職理由が、会社側や管理上の課題であれば、それを改善する機会でもありますので、その改善・変革の担当を当人にしてもらうことを提案しても良いでしょう。
一方で、時代が時代ですから、転職をすべて防ぐことはできません。転職者があることを常に前提にしていることも欠かせません。そのためには、誰かが抜けても立ちゆくようにたら立ちゆかないようなことがないように、平素からの備えも必要です。
「特定の人しかできない業務」を作らず、誰もが代替できるようにしておくことです。ダブルシフトにより、ひとりが休んだり、やめたりしても、誰かが対応できるように市、並行してマニュアルの整備をしておきます。
人手不足の時代に「ダブルシフト方式はムダ」という考えもあります。ダブルシフトの重複によるムダ感はありますが、後進の育成などを並行して進めますと、長いスパンではメリットが大きいと考えます。
転職しようとしている人は、こちらが気がつく前に、それなりに考えていますので、引き留めを実現できる確率は低いです。「引き留めは困難」と悟ったら、気持ちよく送り出すようにします。
業務に支障がでないよう、後任を誰にするか決め、引き継ぎをさせることです。引き継ぎを沿革にするために、転職までのスケジュールを聴き出します。
会社としての対応
私自身、商社マンから経営コンサルタントとしてスピンアウトした人間ですので、その時に私の体験も参考にしていただけると幸いです。私は、上述した「正当な評価をされていない」ということとともに、上のポストが詰まってしまっていますので、今以上のポストに就けるまでには時間がかかりそうだという気持ちがありました。上昇意識が強かったというよりは、「上司が上司としての仕事をしていない」という不満が強かったのです。
高い評価の部下に対して与えられるポストがないなら、ないなりのことをしなければ転職されてしまうことは必定と考えるべきです。給与体系をフレキシブルな運用ができるようにしたり、休暇や留学等々、福利厚生面でのメリット感を持たせたりするなど、まだまだ工夫の予知はあるのではないでしょうか。
「転職」という面では逆行するかも知れませんが、すでに一部の大手企業が実施している「副業可能」などを思い切って導入することも考えるべきです。その制度により、対外的な評価が高まり、より良い人材が入ってくる可能性もあります。マイナス面ばかりを見ないで、別の面もみる必要があります。
転職があたりまえのように行われる時代です。会社も管理職も、平素から部下をよく観察し、管理のあり方に工夫を加える姿勢が必要ですね。

■【小説】 竹根好助の経営コンサルタント起業
「【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記」から独立して、最初から発信していたします。
私は、経営コンサルタント業で生涯現役を貫こうと思って、半世紀ほどになります。しかし、近年は心身ともに思う様にならなくなり、創業以来、右腕として私を支えてくれた竹根好助(たけねよしすけ)に、後継者として会社を任せて数年になります。
竹根は、業務報告に毎日のように私を訪れてくれます。二人とも下戸ですので、酒を酌み交わしながらではありませんが、昔話に時間を忘れて陥ってしまいます。それを私の友人が、書き下ろしで小説風に文章にしてくれています。
原稿ができた分を、原則として、毎週金曜日に皆様にお届けします。
【これまでのあらすじ】
竹根好助は、私の会社の後継者で、ベテランの経営コンサルタントでもあります。
その竹根が経営コンサルタントに転身する前、どのような状況で、どの様な心情で、なぜ経営コンサルタントとして再スタートを切ったのかというお話です。
1ドルが360円の時代、すなわち1970年のことでした。入社して、まだ1年半にも満たないときに、福田商事が、アメリカ駐在事務所を開設するという重大発表がありました。
商社の海外戦略に関わる人事案件なので、角菊貿易事業部長の推薦する三名を元に、準備は水面下で慎重に進められていました。その中に竹根の名前が含まれていることは、社員の誰もが思いもよりませんでした。
討議を重ねた結果、福田社長は、海外戦略にも関わる高度な人事の問題なので、専務と社長に一任してほしいと言って三者会談を終えることにしました。しかし、後日、角菊事業部長は、最終的に、自分が推薦した佐藤君ではなく、竹根に決まったと聞かされます。
一方で、角菊は、自分の意図とは異なる社長の結論に納得がいかないのですが、かといって、それをあからさまにすることはしませんでした。他方、竹根は角菊からの内示なしに、社内には竹根に白羽の矢が立っていることを知りました。海外経験のない竹根は戸惑うばかりです。
空港で家族や長池の見送りを受け、初めての飛行機に搭乗。シートに座っても落ち着きません。次々と出てくる機内食にも戸惑います。初めてのカルチャーショックを味わう竹根です。
雲と海だけの長いフライトの末、ようやく地上が見えてきました。サンフランシスコの上空から滑走路に向かうのです。着陸の不安、着地後の安堵、アメリカという新天地への期待などが入り混じっていました。
アメリカ生活、最大のショックが訪れました。戦後25年も続いてきた1ドル360円が崩壊したのです。そのような経済環境にもかかわらず、一方で竹根の胸にはひとりの女性が悩まし続けています。しかし、会社は次々と新たなミッションを命じてきます。
【過去のタイトル】
1.人選
1ドル3 6 0円時代 鶏口牛後 竹根の人事推理
下馬評の外れと竹根の推理 事業部長の推薦と社長の思惑
人事推薦本命を確実にする資料作り
有益資料へのお褒めの言葉 福田社長の突つ込み
竹根が俎上に上がる 部下を持ち上げることも忘れない
福田社長の腹は決まっていた
2. 思いは叶うか
初代アメリカ駐在所長が決定 初代所長の決定に納得できず
竹根に白羽の矢
竹根の戸惑い 長池係長のアドバイス 急ごしらえの出張準備が始まる
3.アメリカ初体験
いよいよ渡米、初のカルチャーショック
キュンとしたりトロトロしたり
心細いサンフランシスコ上空 生まれて初めて外国の地に降り立つ
ニューヨーク事務所で準備が始まる
ニューヨークで稼働開始
ニューヨークの時計はカネ次第で回る速度が変わる!?
ニューヨーク生活もカネ次第
4.迷いの始まり
初めてのアテンドも吹き飛ぶ事態発生 これって”恋”?
新しいミッションはCIA?
4 迷いの始まり 4-5 新しいミッションの中味
<最新版> 毎週金曜日正午頃発信
■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。
明細リストからだけではなく、下記の総合URLからもご覧いただけます。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17
>> もっと見る
■バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a8e7a72e1eada198f474d86d7aaf43db