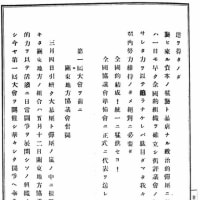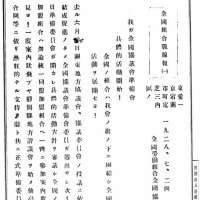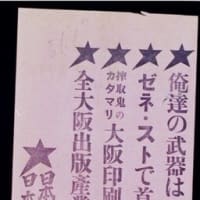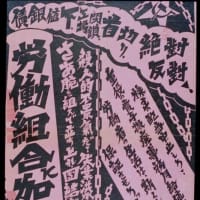『溶鉱炉の火は消えたり』浅原健三著(四~六)
―八幡製鉄所の大罷工記録—
四 労友会生る
十月十六日、中町の弥生座で「日本労友会」の発開式。会員六百名は、製鉄所、旭ガラス、安川電気、安田製釘等、八幡市の大工場を網羅する鉄工場労働者である。会則によって選挙の結果、会長浅原健三、副会長西田健太郎、理事四人は田崎、吉村、伊藤、相原。中央委員三十名。会費は月額十五銭。
この夜、八幡警察署は全力を挙げて厳戒し、乗ずべき間隙(すき)を狙っていたが、記念演説会も無事に済んだ。日本労友会万歳の声は、八幡市の労働界を震撼した。斯(か)くて我等の牙城は成った。
気運に乗じた労友会は破ちくの勢いをもって伸び、十一月末には会費完納会員が三千になった。全員の意気はあがり、闘志は次第に昂っていった。戦時手当の本給繰入による賃金の値上、八時間労働制の実施等は中央委員会その他の会合に於ける論議の中心問題となった。
十二月初旬には、いよいよ要求運動を開始せざるを得ない状勢になったが、尋常の手段で要求を貫徹し得る見込はもとよりない。製鉄所当局の態度は極めて強硬である。更に当局の計画せる労友会破壊の画策が次第に具体化しつゝありとの情報は、我々の戦意をいやが上にも唆り立てた。労友会の誕生、その躍進的な成長振りに脅威せられた当局は、十一月下旬から、工手、筆工、組長、伍長等の上級職工を中心に、御用団体を作って我等――労友会に対抗せしめんと、着々準備を進めている。この長官始め幹部総掛りの労友会破壊策に抗争するためにも、我々は一戦を覚悟しなければならぬ。しかも、開戦は一日も早いが有利である。
この見通しの上に、十二月初め、我々の戦意はもはや動かし難きものになった。しかし、労友会結成後、日は浅く、組合の基礎は未だ十分に固まっていない。具体的な戦闘準備も不充分だ。私は要求運動の具体化を尚早と見て、半月ばかりは、軽燥(けいそう)な爆発の抑制につとめた。が、二十日頃になると、奔流の勢いは区々たる人力で堰き止めらるべくもないことが明瞭になった。十二月二十五、六日、歳暮大売り出しの広告幟が朔風にハタめく頃、最後の腹はきまった。突進!
全組合員を挙げて、嵐の前の静寂裡に、具体的戦闘準備が音もなく整え続けられて行った。
八年は暮れ、九年(1920年)を迎えた。
一月上旬、私は、理事会の決議に基いて、単身上京した。製鉄所長官白仁武に会って、「その腹を探る」役目を帯びて。
五 長官に会う
江戸川の終点で電車を棄て、関口台町に向かって坂道を登ってゆくと、樹立に包まれた屋敷町に、黒板塀をめぐらす長官邸はすぐみつかった。門を入ると植込。突き当りが玄関。十六・七の小娘が私の名刺を運んで奥に消えると間もなく、玄関から狭い階段を二階の客間に導かれた。何の飾気もない、十畳の部屋、中央の四畳敷きぐらいの敷物の上には、約束どうり紫檀の応接机。建物は古びて、天井は低く、すべてが簡素、少年時代によく見かけた田舎の中流郷士の旧宅か、近郊の小寺院の庫裏(くり)とでもいったような感じの家だ。近代重工業の精髄たる大製鉄所長官の邸宅らしい臭いは何処にもない。私は、八幡市――製鉄所――八幡の広壮な長官々舎とこの古色蒼然たる邸宅との対照に苦笑いした。
余り永くは待たないうちに、地味な和服の小男が、チョコチョコと出てきて、私と対座した。イガ栗頭、半白のチョビ髭、体も小さいが、顔も小さくて円い、温和な相貌。官僚風な尊大さも政治家らしい豪快さもない。
長官との初対面だ。
「前から一度お目にかかりたいと思っていましたが……。御演説は一度拝聴しました……。」
「この老爺(おやじ)、なかなか喰えぬわい」と思いながら、単刀直入用談に入る。
「労友会の創立、現状等に就いては長官もほぼ御承知のことゝ思いますが、会は最初から闘争団体として組織し、また訓練されて来ました。」
「今、全会員の間に待遇改善の要求を起す計画が熟しています。我々は当局の意向や予算の関係から要求運動を差し控えたり、加減したりする意志は毛頭ありませんが、しかし、組合の創立後日が浅い、できるならば、十分の闘争力を蓄積するまで待ちたいと思って、一時は爆発を抑えてみました。が、永年累積の火のような要求熱は、誰の力でも抑えきることは到底不可能です。で、愈々(いよいよ)決行と決まったのです。」
「私は素直に申します。職工の要求は十分に容れてやらるべきです。貴下は、部下や警察の報告に基いて、ナァに、大したことではないとタカをくゝつておられるでしょうが、そんな報告だけで見当をつけて居られることは、いかがでしょう? 万全を期すればこそ、準備が足らぬと危ぶみもしたのですが、イザとなれば、全国を震撼するに足る大争議の基礎工事は出来上がっています。私には深い自信があります。貴下の職工も、何時までも従順(おとな)しい羊ではありません。」
「私は貴方を威嚇(いかく)するために、こんなことを云っているのではない。誇張でも、カラ元気でもない。私のような青二才に威嚇される貴下でもなく、私も亦心にもない、口先の恫喝で事を成そうとするような、そんな下劣な人間でも、弱者でもないつもりです。で、貴下も、私の言葉を素直に受け容れて、慎重に考慮して頂きたいのです。」
「しかし、お断りしておきますが、私は長官に嘆願に出たのでもなく、また、断じて妥協に参った者でもありません。私の使命は、一種の宣戦布告です。たゞ、正式に要求書を提出して、戦いの火蓋を切る前に、一応誠意ある御考慮を求め、この危機に善処せられんことをお勧めするために参ったのです。」
「で、製鉄所としては、どうせ、屈服するなら、今のうち、要求書の出ない前に、自発的に、進んで職工の要求を容れ、労働条件を改めたが得策でしよう。」
「如何でしょう? 二万の生命を預かる長官として、くだらない誇りや術策を捨てゝ、静かに御熟考なさっては……」
語り続けてゆくうちに、勃々たる戦意は胸底に湧き上る。だが、言葉は至極平穏だ。妥協的でさえもあった。しかり。実は、刃(やいば)に衂(ちぬ)らず、一兵をも損せずに戦功を収め得ないとは限らない。もし、戦はないで獲得しうるならば、頼むベからざる頼みではあるけれども、二万五千の労働者と十万のその家族のために、私は身を粉にもせねばならぬ。舌の根の続くかぎり、私の全心根を打ちこんで、長官の心を動かさねばならぬ。私は必死である。辞(ことば)を低うし、心をこめて、長官の誠実な省慮を求めたのである。
元来、敵に対する場合、私は、全然心にもない嘘、出鱈目を並べて、相手を翻弄し、述中に陥れて敵を屈服させようとする場合と、百パーセントの真実を相手の胸奥に投げこんで、その心服を得ようとする場合とがある。今日はその後者である。重き責任を負う自分だ。相手は苟(いやしく)も大製鉄所長官であり、事は十万人の死活に懸けての大事である。今、私に用ちうべき区々の術策はない。かけ引は無用だ。嘘もなければ、飾り気もない。たゞ、真裸になって長官に飛びついたのであった。
六 腹は読めた
しかし、長官は老獪な官僚であった。加うるに、彼は状勢を軽視しきってゐる。職工の力を軽蔑しきっている。下僚や警察署の報告のみで目算を定めている長官は、私の言葉に別段の注意を払はないらしい。幾十年の官僚生活に馴れきって、抜き難き支配者意識に凝り固まっている老官僚である。労働者のセッパ詰った心理が理解できよう道理がない。彼は本質的に私の言葉――労働者の心を諒解し得ない存在なのだ。
「ご親切は誠に有難う……。しかし、今のところ、私には御希望にそうような意志はない。」
長官の言葉はつめたい。
「もっとも、年度代りには、何とか考慮してもいゝが、それも、今から御約束出来ない。」
態度は挑戦的ではないが、底意は明瞭だ。
(製鉄所は職工の要求運動を怖れて折れて出るわけには行かない。それに、一部職工の蠢動はあるらしいが、全部は微動だもしまい。僅か数百名で、何事も起せるものでもなく、起し得たところが、大したことはない)
長官は腹のなかで私語している。
「それよりも、浅原君!」
長官は訓話口調である。
「私は君の倍以上の年長だから言うのだが、君一つ考えなおしてみてはどうだ。西郷南洲翁は偉人には相違ないが、西南戦争を起したのは確かに大失策であった。大西郷ほどの人物にも、時勢を達観する明がなかったのだ。郷党子弟の友愛に殉ずると言えば、如何にも美しいが、時勢に逆行する軽挙であった。翁に今少し時勢を見る明があったら、あんな無用の大騒動も起さず、有為の子弟を犬死にさせないでもすんだ筈である。人生意気に感ずるもよい。しかし、君のような有為な青年が労働運動の指導者になって、労働者に心中だてをするのは、いわば、大西郷の西南戦争と同じことだ。バカバカしいじゃないか。」
私は黙々と聞く。長官はゆるやかに語り続ける。
「聞けば、君は官界や政治界に相当知人も多いという話だから、君さえその方面で身を立てる気なら十分に引き立てゝ貰えると思うが、どうです、一つ考えてみませんか、及ばずながら私も力を添えてやるが……」
長官と私、言い廻しは違うが、何だかお互いに勧告ゴツコをしているようで、危く吹き出しそうになった、が、私は老人に対する敬意を失わないように、ひと通り忠告を謹聴した。
しかし、私は言下に、
「御懇篤(ごこんとく)な御忠告は親身に承りましたが、見解は貴下と全然違います。私は時勢を見違えてはいないと確信しています。西郷さんが不明であったかどうかは別問題として、時勢に逆行する者は、私でなくて、長官ではないかと思います。誰が何と言おうとも、未来は労働者のものです。私は労働者です。金持の卵でもなければ、お役人のお玉杓子(じゃくし)でもない。私の望むところは、立身出世ではありません。労働者解放運動の一兵卒として、斃(たお)るれば、それで満足です。」
長官の腹のなかは、わかりすぎるほどわかった。この上、無用の折衝を続ける必要はない。長官がまた何か言い出さない前にと思って、私が腰を上げかけると、彼は肩に手をかけて抑えつけんばかりに私を引止めて、今度は見違えるほど真剣に話しかけた。
「一体、君等はこれからどうするんです!」
「要求運動を起します。」
「どんな要求か話してくれませんか。」
「時間短縮、賃金値上げ、其他二三項です。」
「八時間労働にしろというのかね。」
「そうです。」
「でも、八時間制は無茶だ。官設工場で実施しているところはまだ一つもない。製鉄所が先走りするわけには行かないじゃないか。」
「よい先例は率先してお作りになるべきでしょう。」
「それに賃金の方も、予算が決まっているから私設工場のようなわけにはゆかぬ。」
「予算なんてものは、我々の眼中にありません。」
「そんな乱暴な……。もし要求が容れられないとなると、どうなるのだろう?」
「溶鉱炉の火が消えます。」
「ハァ……それで、結局、勝てるかね。」
私の態度、語調が、多少癪に触ったものか、長官の言葉にもトゲがある。
「勝敗は問題ではない。やむを得ず戦うのです。」
「お勝てになりますか?」
長官は繰り返す。唇頭には冷笑が漂う。(五百か千の職工が動いたところが、何が出来るものか)、長官の胸はセゝラ笑う。
「勝てゝも、勝てなくても、やりまっせじゃ」
覚えず国訛(なまり)が出た。長官の冷嘲に対する軽い昂奮からである。
私は間もなく長官邸を辞去した。
江戸川の終点へ歩きながら私語する。
「要求は、容れられるどころか、受け付けられもしないだらう。だが、当局は油断している。大した戦備はない。開戦は早いがいゝ。疾風迅雷にやっつけるんだ。」
最後の決意は電車に乗るまでにハッキリとついた。
神田錦町の下宿屋に戻ると、暗号電報で八幡の同志に開戦の準備を命じ、その夜十一時発の列車で東京を去った。