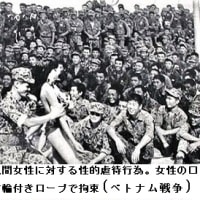一条が死んで五年後の1016年、彰子の息子敦成(あつひら)が即位した。後一条天皇である。秋の新嘗祭は一代一度の大嘗会(だいじょうえ)として大々的に開催された。
帝が賀茂川で潔斎(けっさい)なさる「御禊(ごけい)」の日となった。先例にならわず諸事万端が一新され、殿方・公達の馬や鞍、弓や矢筒の飾りに至るまで特別である。選ばれて女御の代わりを務められる女御代の役には、道長殿の明子腹の姫君寛子様があたった。その車からは、収まりきらぬ装束の袖口が外にこぼれ出て、何枚を重ね着したとも数え切れぬ豪華さで輝いている。帝が御幼少なので、輿には彰子皇太后が同乗なさる。何とも描きようのない素晴らしさだ。(栄花物語)
行列に同行する近衛大将は、左大将が彰子の弟頼道、右大将は例の実資。二十五歳の若い頼道に負けず六十歳の実資はかくしゃくとし、微笑みをたたえて馬を歩かせたという。道長の倫子腹の次男教道と明子腹の長男頼宗はともに衛門府の長官で、華麗な武官姿にみずみずしい若さを匂わせてゆく。女房たちの車が四、五十台も続く。右大臣、内大臣も馬で行く。すべての行列の最後を行くのは、貴族の中では一人だけ牛車に乗った道長だった。選りすぐりの美形ばかり三、四十人を共とし、摂政ゆえに許される十人にさらに異例の二人を加えた十二人の警護騎馬隊を前に立て、大声で先払いをさせながら、道長の牛車は進んだ。それは道長の栄花の実現を人々の目に見せ付ける光景だった。
だが、彰子はその父さえ及びもつかない場所、鳳輦(ほうれん 天皇の乗物の美称)の上にいた。母が帝と同乗するのは、一条の大嘗会に一条の母詮子が同乗した例にならっている。それはちょうど三十年前、一条は七歳だった。いま敦成は九歳である。息子を抱きながら彰子は、父を含め貴族官人のすべてを見下ろす位置にいた。それは、これから天皇の母として権力の一角を担ってゆく彰子の人生を象徴するかのようだった。
敦成が後一条天皇となって二年目、三条天皇の長男で東宮だった敦明が東宮の位を返上した。『大鏡』は道長の圧力に屈したともいうが、史料に従う限り、自発的に位を降りたというほうが事実に近いと考えられている。もとより人望がなく、何度も乱闘事件を起こすなど、政治向きでない性格でもあった。新東宮は彰子の下の息子敦良となった。後の後朱雀天皇である。冷泉・円融兄弟に始まった両統迭立(てつりつ 交互にたつこと)状態はこれで終わった。一条の皇統が残ったのだ。
天皇と東宮を擁した彰子を『大鏡』は「天下第一の母」と呼ぶ。後一条の治世は足かけ二十一年、後朱雀は十年。彰子は息子たちを後見し、父を、また父を継いで摂政・関白となった弟頼道を支え、積極的に政治に介入した。その間、1026年、出家し法名(ほうみょう)「清浄覚」となる。と同時に、通常は天皇経験者に与えられる称号「院」を授けられて、その後の彰子は「上東門院」と呼ばれた。天皇家に血を受けない人間でありながら、当時において人としての地位を極めたのである。
出家のあくる年、1027年にはすぐ下の妹の姸子が亡くなった。三十四歳であった。お洒落の好きな姸子だったが、最期は虫の息の下で髪を切る仕草をして、父の道長に出家の意志を伝えた。道長は遺髪を捧げ、「一緒に連れて行ってくれ」と泣いたという。
その言葉どおり、道長も同年十二月四日、他界した。姸子の四十九日に床に就き、十日ほど後には重体となった。彰子は父道長のために僧百人を動員して『寿命経』を読ませたが、容態は悪化、震えを繰り返し、背中の腫れ物の毒気が腹部に回ったと診断された。治療は及ばず、うめき声をあげながら衰弱して、自らが建立した法成寺阿弥陀堂内で六十二歳の生涯を閉じた。偶然同じ日に藤原行成も急逝した。五十六歳だった。
息子たちも彰子より先に逝った。後一条は1036年、享年二十九歳。また後朱雀は1045年、享年三十七歳。後朱雀の後は彼の子の後冷泉が足かけ二十四年間、同じく後三条が五年間、相次いで帝を務めた。そしてそれぞれ、五十歳になる前に世を去った。時代がどう遷ろうと、彰子は自らの血を分けた天皇たちを、母としてまた祖母として見守り、見送った。その間もそしてその後も、摂関家と天皇家を支え、摂関制を見守る存在として彰子は生きた。それは権威であることを自ら引き受けた、長い長い人生だった。彰子の崩御は1074年。父道長と同じ法成寺阿弥陀堂内で、八十七年の天寿を全うした。彼女のひ孫、白河天皇の代のことだった。
その白河によって、間もなく時代は院政期へと遷った。が、彰子にまつわる話は以後も語り継がれた。キサキの入内につけても、出産につけても、彰子の例こそがあやかるべき先例とされて見習われたのだ。摂関家の黄金時代を築いた女性、天皇家の家長のように君臨した国母として、彰子は伝説のように尊敬され慕われ続けた。
彰子が話した昔語りも、聖典のように伝えられた。平安時代の最末期を生きた関白、藤原忠実はこう語る。
天皇や摂政・関白は、慈悲の心をもって国を治めなくてはならないものだな。これは私が祖父の故関白師実(もろざね)公(頼道の子)から伺った話だ。
昔祖父に、上東門院(彰子)様がこうおっしゃったという。
「かつて一条院は、寒い夜には、わざと暖かい夜具を脱いでいらっしゃいました。どうしてですかとお聞きすると、『日本国の人民が寒がっているだろうに、私がこうして暖かく居心地よく寝ているのでは、良心が痛むのだ』。そうおっしゃいましたよ」
彰子の心の目には、ほほえましいほど真面目な一条の姿がいつまでも焼きついていた。
おわり(全編の終わりです。読んでいただいた方々に感謝いたします)
参考 山本淳子著 源氏物語の時代 一条天皇と后たちのものがたり