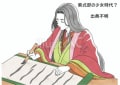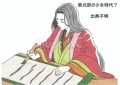15-5.紫式部の育った環境 惟規(のぶのり) 客死 (紫式部ひとり語り)
山本淳子氏著作「紫式部ひとり語り」から抜粋再編集
**********
惟規(のぶのり) 客死
一条院の御葬儀は七月八日。そして同じ秋に、越後で惟規が死んだ。帝とそう変わらぬ歳だから、男盛りの死だ。臨終の様子は、父から手紙で知らされた。実に胸に迫る、見事な死に様だったと私は思う。やがてその一部始終は、父自身の言葉に基づいて、世に語り伝えられることになる。
惟規がいよいよ助からないと見た父は、もう往生を願うしかないと覚悟して、彼の地の高僧を呼んだ。惟規が心を鎮め、末期の念仏を唱えるように、導いてもらおうとしたのだ。僧は惟規の遠くなった耳に口を押し当て、死後の世界のことを説いた。
死んで最初に行くのは「中有(ちゅうう)」という世界だ。生まれ変わる先が定まらぬ間は、そこにとどまらねばならない。鳥も獣もいない荒涼とした広野に一人ぼっちで置かれる心細さ、またこの世に遺してきた者たちへの恋しさが、どれほど耐えがたいか。すると惟規は、苦しい息の下で、ためらいながらも僧にこう聞いたのだという。
「その中有の旅の空には、嵐に類(たぐ)ふ紅葉、風に随(したが)ふ尾花などのもとに、松虫などの声などは聞えぬにや」
[「その「中有」という所の旅の空には、嵐に運ばれてくる紅葉や、風になびく薄の穂などはありますか。その根元で鳴く松虫などの声は、聞えてきたりしないのでしょうか」]
(「今昔物語集」巻三十一第二十八話)
なんと惟規らしい、間抜けな質問だろうか。神妙であるべき臨終の床でこんなことを聞かれるとは、僧は思ってもいなかった。むっとして「何のためにそんなことを聞く」と問い返した。すると惟規は、息を休めながら途切れ途切れに「もし、そうしたものがあれば、それらを見て、心を慰めながら参ります」と答えたという。僧は怒って帰ってしまった。
だが、私には分かる。惟規は大真面目だった。本当に知りたかったのだ。自分が向かうという死後の世界に、大好きな歌の種はあるのだろうか。向こうでは、紅葉を愛で虫の音をいとおしみ、歌を詠むことはできないのだろうか。
しばらくして、じっと見守る父の前で、惟規は朦朧としつつ両の手を持ち上げ、寄せ合うような仕草をした。何がしたいのか。父には分からなかった。だが傍らの者が思いついて、「もしや、何か書きたいのですか」と聞くと、惟規はかすかにうなずいた。父が筆を湿らせ、紙と共に持たせると、惟規は書いた。辞世の歌だ。
都にも わびしき人の 数多(あまた)あれば なほこのたびは いかにとぞ思
[ここで死ねば父上に看取ってもらえるけれど、都にも、僕が死んだら寂しがってくれる人が、たくさんいる。だから、今回はやっぱり生きて帰りたい。生きてこの旅を終えて、もう一度都に行こうと思う。]
(「今昔物語集」巻三十一第二十八話)
ここまで書いて、息が絶えた。惟規は歌の最後の文字、「思ふ」の「ふ」の字を書ききることができなかった。父は「「ふ」なんだろう、そうだろう」と言って、自ら弟の辞世に「ふ」の字を書き加えたという。
惟規の遺筆を、父は形見としてずっと傍らに置いていた。出しては見て泣いて、ぼろぼろに破れて無くなるまで持っていたという。
この項、終わりです。