
この記事が役に立つと思われましたら、クリックをお願いします。

ランキングに参加
しています。
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
第四章 JR体制への移行と国労の闘い
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
第二節 新会社への職員採用差別・配属差別と配転・出向攻撃
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
国鉄を分割・民営化し、その従業員らを新事業体に移行させるについては、国鉄改革法第23条は、まず国鉄が国鉄職員から新会社等の新事業体への採用を希望する職員を募集し、それら応募者の中から採用基準に従って職員となるべきものの名簿をつくり、その名簿の中から新事業体の設立委員等より採用通知を受けたものが新事業体の職員として採用されることになるという、はなはだ手の混んだ手続きを採った。要するに、国鉄職員は全員いったん解雇し、それらの中から必要な職員だけを採用するという仕組みである。新事業体の募集する人員は、全体としてみると現役の国鉄職員数よりは少なく、とくに北海道と九州の新旅客鉄道会社の募集予定人員は少なく、多くの不採用者の出ることが見通された。
この規定は、立法過程でも国会その他で議論をよんだ。問題はなぜ国鉄の分割・民営化にあたってこのような手の混んだ手続きが採用されたのかということである。議論の中でもっとも強く指摘されたことは、採用にあたっての職員の選別であり、この方法が国鉄改革=分割・民営化の主目標とみられた?国労つぶし?に利用される可能性であった。政府答弁ではもちろん、そのような意図はまったくないとされ、また国鉄改革法成立にあたっても付帯決議がそのことを否定していた。しかし、この問題の規定の執行過程は、国労を敵視した選別と採用差別以外のなにものでもなかった。そのことは、国労組合員の不当労働行為救済申し立て事件において、すべての労働委員会が認めたところであった。
いま一つ看過できないことは、1986年12月から翌87年3月にかけて、新会社などへの採用を希望する国鉄職員の中から「採用候補者名簿」を作成し、採用通知と配属先通知が行われた時期こそ、国労が大規模な組織分裂に見舞われつつあったさなかであり(本章第4節参照)、この国労分裂は一見いわば「労・労問題」のようであったが、分割・民営化をすすめる側はこの状況を国労つぶしの目的のために最大限利用したという点である。
続く










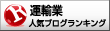
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます