
![]() にほんブログ村
にほんブログ村
この記事が役に立つと思われましたら、クリックをお願いします。 
ランキングに参加
しています。
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
第四章 JR体制への移行と国労の闘い
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
第五節 JR体制下での賃金・労働諸条件をめぐる取り組み
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
二 JR各社等に対する国労の対応と団体交渉
JR体制下の国鉄労働組合の団体交渉の実態
公労法適用下にあった国鉄時代の国労の団体交渉は、国鉄本社?国労本部間はもとより管理局・地方機関?地方本部間そして事業所?支部間、さらには地域単位・職域単位や「現場」での協議・交渉が行われていた。たしかに公労法は、「管理運営事項」を団体交渉の対象にすることを禁じたり、「予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容」とする協定の法的意味を否定していた。しかし実際には、長年の闘いとその成果のうえにたって、国労はそうした公労法上の制約をのりこえて団体交渉をすすめ、また協定を締結するまでに労使関係を成熟させていたといえよう。だが、このような長年にわたって培われてきた労使関係を全面的に否定したのが、まさに国鉄「分割・民営化」であった。
「現場協議に関する協約」は、国鉄分割・民営化を提言した第二臨調第三次答申(1982年7月)と前後して破棄されたが、国鉄改革=分割・民営化の過程でそれ以前の労使間協定などは一部が清算事業団に引き継がれただけで、新会社等の発足と同時にそれらのすべてが白紙となり、新会社などから提案された新労働協約案には会社ー労働組合関係を定めたいわゆる債務的部分しかなく、労使間の新しい協議・交渉制度としては①経営協議会、②団体交渉、③苦情処理(会議)の三制度が規定されていた(東日本旅客鉄道の場合)。
新労働協約によれば、これら三制度は次のような内容になっていた。
1、経営協議会
目 的 会社は企業の繁栄を目的として、組合と相互の意志疎通を図り企業運営の円滑を期して、 組合との間に経営協議会を設ける。
設置単位 経営協議会は、本社及び地方において行う。地方における経営協議会とは、東京圏エリ ア、東北地域本社、新潟支社、長野支社、盛岡支店、秋田支店。
付議事項等 ①業務の合理化ならびに能率の向上に関する事項、②福利厚生に関する事項、③事故防止に関する事項、④その他会社側と組合側とが必要と認めた事項、⑤その他会社は必要に応じて事業計画、営業報告及び決算等につき組合側に説明する。
2、団体交渉
原 則 団体交渉は、信義誠実の原則に従い秩序を保ち平和裡に行う。
設置単位 団体交渉は、本社及び地方において行う。地方における団体交渉とは、東京圏運行本部、東北地域本社、新潟支社、長野支社、盛岡支店、秋田支店、高崎運行部、水戸運行部、千葉運行部。
交渉委員 団体交渉は専ら交渉委員がこれを行う。
交渉事項 ①賃金、賞与及び退職手当の基準に関する事項、②労働時間、休憩時間、休日及び休暇の基準に関する事項、③転勤、転職、出向、昇職、降職、退職、解雇、休職及び懲戒の基準に関する事項、④労働に関する安全、衛生及び災害補償の基準に関する事項(以上「の基準」はのち削除)、⑤その他労働条件の改訂に関する事項、⑥この協約の改訂に関する事項。
協約等の調印 団体交渉において妥結した事項については、双方の機関を代表する者で記名、押印を行う。
3、苦情処理
苦情処理会議 会社と組合は、苦情処理機関として中央苦情処理会議と地方苦情処理会議を設ける。会社を代表する苦情処理委員は会社が、組合を代表する苦情処理委員は組合が、それぞれ対応の機関ごとに指名する(労使同数)。別に、簡易苦情処理会議を、地方苦情処理会議が設置される個所に常設する。
苦情処理の範囲 組合員が、労働協約及び就業規則の適用及び解釈について苦情を有する場合は、その解決を苦情処理会議に請求することができる。
当事者が、地方会議の解決に異議のある場合は、中央会議に対し異議の申立をすることができる。組合員が、本人の転勤、転職、降職、出向及び待命休職についての事前通知内容について苦情を有する場合は、その解決を簡易苦情処理会議に請求することができる。
効 力 会社並びに苦情申告者、異議申立者及びそれぞれの所属する組合は、苦情処理手続きによって最終的に決定された事項を、責任をもって実施しなければならない。簡易苦情処理会議の判定及び決定については最終のものとし、苦情申告者及び会社はこれに従わなくてはならない。
続く










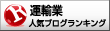
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます