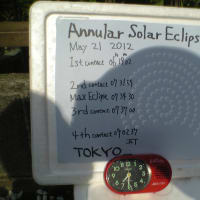第1章 暗号と戦争
第2章 ブレッチリー・パーク
第3章 一九四〇年―運命の年
第4章 大西洋の戦い
第5章 北アフリカとイタリア
第6章 レジスタンス
第7章 ヨーロッパでの勝利へ
第8章 太平洋戦争
最近のニュースに登場したブレッチリ―パーク。イギリス人らしい場所の選択でね。
機密指定解除後に関係者が続々と手記を公開したようで(さすが勝ち戦イクサ)、それらを巧みに引用。さらに著者が直接インタビューしたケースも、という。
半藤一利さんみたいな感じ?
巻末の索引も素晴らし!
かねて、邸宅としての美しさをまるで感じさせない、なんだか気色悪いなぁと思っていたブレッチリー・パークの由来などについて、本書で知るなどw
エニグマ・コードを解読せよ (VOICES OF CODE BREAKERS)
Voices of the Codebreakers: Personal accounts of the secret heroes of World War II
by Michael Paterson, Robert Harris (Foreword by)
第4章 大西洋の戦い
乳牛"Milchkuh/Milchkühe (pl.)"ことUボートの補給専用艦
Type XIV submarine - Wikipedia
German U-Boat Type XIV (Milchkuh Milk-Cows) - history, specification and photos
集中的に沈められたりしていて、なんか変だと思わなかったのかね?
連合国軍側も、「いやもう、たまたまです!」と思わせる工夫を必死でしたのだろうが。
第5章 北アフリカとイタリア
解読したUltra情報を各戦線の限られた司令官たちに伝えるのに、MI6から専門の要員Special Liaison Units (SLU) を派遣して常駐させていたというのはすごい。
そこまでやるべきものだとの本質の理解に基くわけね。客先常駐班。
お偉い将軍たちは、いくら念を押しても報告文書の処分が甘くなることは避けられない。
それを先方の部隊に委ねてしまってはダメだとわかっていたので、(指揮命令系統が別の)本国直属チームが見せてその場で回収し処分。
「これってもしかして暗号が解読されているかも」と敵方に思わせないために莫大なエネルギーを投入した~それだけの価値があり、バレたら苦労が水の泡なのでね。
Ultra - Wikipedia
Dissemination of Ultra intelligence to field commanders was carried out by MI6, which operated Special Liaison Units (SLU) attached to major army and air force commands. The activity was organized and supervised on behalf of MI6 by Group Captain F. W. Winterbotham.
確かに、司令官の副官たち(何も教えてもらえない!)にとっては、さぞ面白くないことだっただろうw
F. W. Winterbotham - Wikipedia
しばしば回顧著作が引用されているWinterbotham大佐。
昔、邦訳を読んだかもしれないのだが、地元図書館にはデータすらないという。
時代は下って、ドナルド・トランプのように、機密書類を自宅に持ち帰って退任後も抱えていたり、「俺のところにはこんなすごい機密情報が来てるんだぞ。ドーダ、すごいだろ」と友人に見せびらかす異常者は、それはそれで突出しているけど。
(公職に就く基本的資格がない。大統領という役職を、自分がオーナーである会社<カイシャの物はオレの物>と同様に考えていた/今でもいる。)
第6章 レジスタンス
特殊作戦執行部 - Wikipedia
独占領下の大陸に潜入した工作員の多くが捕縛されたという。
独が英国に潜入させた工作員も、英側が全員確保して、使える者は「XXダブルクロス/にじゅう(二十/二重)委員会」の指揮下で、慎重に整合性などを考慮の上用意された偽報告の送信に励んだことが知られているが、逆もかなり悲惨な展開だった。後方攪乱だからね、任務が。
Special Operations Executive | National Army Museum
Seven Stories from Special Operations Executive
第7章 ヨーロッパでの勝利へ
われらの大島将軍の連合国への比類ない貢献についても記載あるし(p300)。
解読された暗号電報の読者に感銘を与えていたのだそうでw
「駆け出しの歴史家として、私は大島の言葉を読むとき、世界の中心に立っているような気持になったものだ。」だって!
ヒトラーに傾倒した男 A級戦犯・大島浩の告白 増田剛 2022.7 - 真似屋南面堂はね~述而不作
p301の1943年1月に大島がベルリンで(ヨーロッパや中東駐在の日本の上級外交官を)招集した会議というのは、大島に直言した駐ハンガリー公使が実質格下げになった会議?
ハンガリー公使大久保利隆が見た三国同盟 - 株式会社芙蓉書房出版
第8章 太平洋戦争
対日戦で活躍した米海兵隊のナヴァホ族コードトーカー(各部隊に通信兵として配属されて、ブレイクされないネイティブアメリカンの部族語でトークした)の事績紹介にも及んでいる。
コードブレーカー(敵の暗号を解読する方)を主題とした本書に取り上げるのはやや異質な感じがしないでもないが、光が当たってこなかった勇士らの事績を広く紹介するという点では、まあよいのでしょう。
どこだっけ?
ジョーン・クラーク - Wikipedia
「クラークは2014年の映画『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』においてキーラ・ナイトレイによって演じられた」
Joan Clarke, woman who cracked Enigma cyphers with Alan Turing
とはいえ
第4章 大西洋の戦い
だけど、海軍用語の訳語はもう少し何とかならなかったものかね。
●戦艦がたくさん出てきてしまう戦艦祭り☆彡
そんなにたくさんの戦艦がちょこまか走り回るわけはないとイメージできなかったのか。
原文未確認だが、「HMSなんとか」と艦名が記載してあった個所で、いちいちそれを「戦艦なんとか」にしてしまったのは確実だろう。
巡洋艦だろうと、駆逐艦だろうと、果てはコルベット(なぜかコルベットのほか「コブレット」との珍妙なる記載ががが)まで「戦艦」だって。
英艦なんとか(以下は英国海軍の艦艇の名前ですよ)、と言っているだけなのにね。
エニグマ (暗号機) - Wikipedia
1940年5月、ドイツの偽装トロール漁船(trawlerに偽装して気象観測して報告していたweather shipのMünchen号)からの回収文書を利用して海軍エニグマを解読。
の作戦に従事した水兵の回想を引用紹介している個所。
Enigma Code Broken
5 May 1941 British Royal Navy's 18th Cruiser Squadron (HMS Edinburgh, Manchester and Birmingham with five destroyers) sailed from Scapa Flow, Scotland, United Kingdom and headed north. The operation (codenamed EB) had been mounted by the Admiralty with the specific aim of intercepting and capturing the German weather ship München. Using surprise and speed, Admiral Lancelot Holland intended to capture and board the enemy vessel and, all being well, secure a set of coding tables which would enable the German naval cipher system, Enigma, to be read immediately for the first time.
・戦艦エディンバラ(p159)⇒エディンバラ (軽巡洋艦) - Wikipedia
・同マンチェスター(同)⇒マンチェスター (タウン級軽巡洋艦) - Wikipedia
・同バーミンガム(同)⇒バーミンガム (軽巡洋艦・2代) - Wikipedia
・戦艦ネスタ―がヘインズ大佐をスカパフローまで高速で運ぶと(p160)⇒ネスター (駆逐艦) - Wikipedia
お!ちゃんと記載あるじゃん
5月5日に「ネスター」は第6駆逐群に加わり[6]、軽巡洋艦「エディンバラ」、「マンチェスター」、「バーミンガム」、駆逐艦「ベドウィン」、「ソマリ」、「エスキモー」と共に北極海でドイツの気象観測船の捜索に当たった[7]。5月7日、駆逐艦「ソマリ」によって気象観測船「ミュンヘン」が捕捉され、「ネスター」は捕虜となった「ミュンヘン」の乗員を乗せて5月9日にスカパ・フローに戻った[7][6]。
それにつけても、部族名を冠したトライバル級シリーズ、すごいわw
トライバル級駆逐艦 (2代) - Wikipedia
誠に意義深かったU-110の拿捕
9 May 1941 German submarine U-110 and U-201 attacked Allied convoy OB-318, sinking 3 British freighters. U-201 was damaged by 99 depth charges but was able to return to her home port for repairs. U-110 was forced to surface by 10 depth charges from British corvette HMS Aubretia, then shelled by destroyers HMS Bulldog and HMS Broadway. The German crew thought the submarine had already been fatally damaged and sinking, and abandoned ship. Recognizing the opportunity to capture the ship, the commanding officer of HMS Bulldog quickly rescued many of the German crew and put them belowdecks so they could not observe (but submarine commander Lemp died in the water, possibly shot as he attempted to swim back to the submarine), and sent a boarding party to capture her. The capture was completed at 1245 hours, yielding an Enigma cipher machine and code book.
そう!British corvette HMS AubretiaHMS Aubrietia (K96) - Wikipediaが
・戦艦オーブリーシャ(p161)だったり、
・コブレット艦[オーブリーシャ](p163)
・コブレット艦オーブリーシャ(p166)
などと不思議艦種に形を変えて登場する。
コブレットとは何ぞや???
アルバイトに下訳させてそのままです、みたいな?
フラワー級corvette なのでお花の名前なの🌸
オーブリエタとは|育て方がわかる植物図鑑|みんなの趣味の園芸(NHK出版)
番組になっておるのね(見た)
WW2: Hell Under The Sea - The Failed Sinking of U-110
沈めそこなった件ということで、独が自沈処理に失敗した(後刻、エニグマ暗号機他重要物件回収完了後に英が艦を曳航し始めたところ、沈んでいった)のがミソ。
手を加えなくても間もなく沈むと確信したのだろうが、その前に英海軍チームが乗り込んで機器&文書類を回収する時間があったという痛恨のミス。
それにしても、トホホなレンプ艦長フリッツ・ユリウス・レンプ - Wikipediaは、1939年に客船アセニアを撃沈するわ、1941年にU-110退艦の際に自沈処理にしくじって連合軍にエニグマ暗号機及び暗号書ほか関連資料一式を献呈するわで、散々だな。
アセニア撃沈騒ぎの際に潜水艦長から解任しておけばよかったのだろうが、猫の手も借りたい中で、せっかく艦長が務まるまでに育成した人物を外す決断はできなかったのかな。
その判断がとてつもなく高くついたのね、ドイツにとっては。
●UボートⅦ型をVとIIに分けないで!
縦書きでⅦC型のことを
V
II
C
型(p142)
などと書かれてしまうのは、Ⅶが「七」のことだとわかっていません!と宣言していることになるわね。