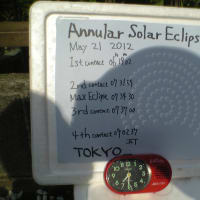序章 国民作家と傍流の昭和史
第1章 傍系の学歴と戦争体験―昭和戦前・戦中期
第2章 新聞記者から歴史作家へ―戦後復興期
第3章 歴史ブームと大衆教養主義―高度成長とその後
第4章 争点化する「司馬史観」―「戦後五〇年」以降
終章 司馬遼太郎の時代―中年教養文化と「昭和」
【ザ・インタビュー】「傍流」の視点で国民作家に迫る 歴史社会学者・福間良明さん著『司馬遼太郎の時代』
2023/01/27 05:20 金子拓(歴史学者・東京大准教授)評
「昭和の暗さ」を描くために明治の明るさを措定し『坂の上の雲』は書かれたが、作者の意図とは異なり、愛読者の主流であったビジネスマンたちは「明るい明治」を描いたと「誤読」し、その印象が広く受け入れられるようになる。
司馬作品は1960年代に普及したテレビとの親和性が高く、70年代半ばの「大衆歴史ブーム」により文庫化作品が多くの読者を獲得した。
司馬遼太郎を論じた本はこれでもかというほどあるけどね。
文庫化は通勤途上の細切れ読書にも便利だった、って?
その時期、本など車内で読めたんだっけ、というね。
皆さん、それなりに語りたくなるものなんだよね。
C7「司馬遼太郎の時代」 - 透明タペストリー
piccolo33さんの感想・レビュー
勤め人経験のある著者
福間 良明 FUKUMA Yoshiaki
ここの「職歴」というのは、学者になってからの、アカデミックなポストということね。
出版社に約10年間勤務したとあとがきに記載。
【著者インタビュー】福間良明さん著『第42回 福間良明さんインタビュー『戦後日本、記憶の力学〜「継承という断絶」と無難さの政治学』』