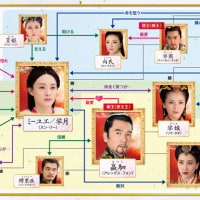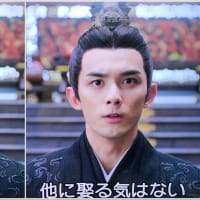実家の母は88歳になって7月に介護付きマンションに入った。
実家のうちの庭のこと、うちの中の色々な物の整理を私がほとんど任されている。
父は3年前に88歳で亡くなったが、この10年ほど前まで趣味で陶芸をしていた。
長年繊維関係の町工場を営んでいたが、55歳になる頃趣味で窯場を見て回る内に、自分で焼き物をしたくなり、その後工場の仕事も辞め、家の隣にある貸倉庫の隅に窯を設計して据えて、趣味で20年以上轆轤を回し作陶に没頭していた。
作品を作って窯に火入れをすると、火の温度などの確認のためにうちと窯とを一晩中行ったり来たりしていたのを、隣に住む我が家からでも気配で感じたのを思い出す。
また焼きあがった作品が満足いかないと、よく陶芸家がやるようにほとんどを割っていた。
私たちには何が悪いのかは分からなかった。色であったり形だったりと、こだわるものがあったのだろうと思う。
陶芸の技術は最初の基礎を教室で習った後はほとんど独学でやっていたようで、こういうものは人に教えてもらうのはほんの一部、そういうものなのだとよく言っていた。
乾燥した後、色々な色を出す釉薬(ゆうやく・表面にかけるうわぐすり)をかけて窯に入れ、予想した色が出たり出なかったりする中で、山に生えている木の葉を燃やした灰や、コバルトなどの科学的色素の配分、時にはコーヒー豆の抽出後の豆のカスなどでも試したりしているのを見て、応用物理専門の主人は、化学の専門家でもない父のその探究心にいたく感心していたものだった。
作陶を辞めるまでに3回ぐらい個展をして、陶器などが好きな方の元にたくさんその作品が行っていると思う。
いつだったか、下の妹が地元の山の方にある小さなカフェに入ったら、父の辰砂の大きな壺が飾ってあって驚いたらしい。
父の辰砂(元々は牛血紅という色を指したらしい)の壺は見るとすぐわかる。
直径4,50cmある壺と大皿、


少し小さめの壺

整理のために入った応接間の隣の部屋の棚に並べているのは二番手の物だと思っていた私は、今更だがどれひとつとして駄作はないのだと改めて気づいた。
陶芸作品は年数が経つほどに色に深みが出てくるものだということも知った。


この中で見つけた大小の作品を追い追いアップしようと思う。