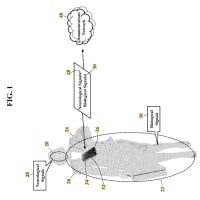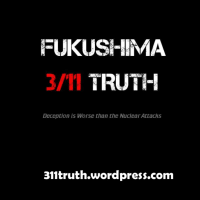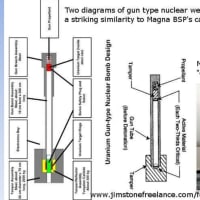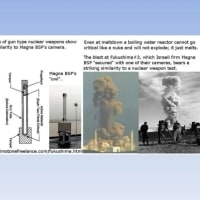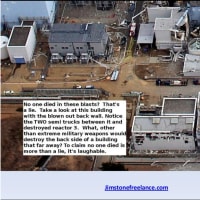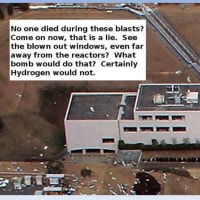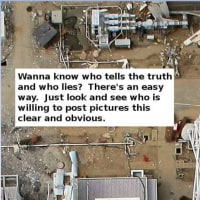「アジアには日本がいたが、アラブには日本がいなかった」エジプトの独立を果たしたナセル大統領の言葉です。
「旭日旗とは日章と旭光を意匠化した日本の旗。光線(光条)が22.5度で開く16条のもの(十六条旭日旗)がよく知られている。 1870年に大日本帝国陸軍の陸軍御国旗(軍旗)として初めて使用され、1889年に大日本帝国海軍の軍艦旗としても採用された。現在は、陸上自衛隊で自衛隊旗、海上自衛隊で自衛艦旗として旭日旗が使用されている。」とあります。
アジアの中にあって、日本は明治維新後、欧米の産業革命に遅れること約100年、国家が一丸となって「和魂洋才」で欧米先進国の文物や制度を日本風にアレンジしながら取り入れ、欧米列強の植民地支配の波にのみこまれずに独立を保ちながら、条約改正の努力によって国際的地位の上昇をはかり、官営工場を建設し、江戸時代から継続する三井・三菱・住友などの商業資本を土台に日清戦争期に軽工業を、日露戦争期に重化学工業を発達させた。
非欧米諸国としては唯一初めて憲法を制定。日清・日露戦争に勝利したことで、当時の先進国=列強の1つ(五大国)と呼ばれるようになった。第一次世界大戦時には日英同盟を基本とする姿勢で参戦し、勝利者の側に立って、国際連盟(1920年1月~1946年4月解散)では英、仏、伊と共に常任理事国にもなった。
日清戦争の日本の勝利後、下関条約で清からの独立が認めれた李氏朝鮮にとって、事大主義で儒学しか学んで来なかった朝鮮の支配階級の人々も、両班以外には学問の機会がなく文明国とは程遠い生活をしていた朝鮮の平民の人々にとっても「民族自決」より先にくるべきは、帝国主義列強の中で生き残るために、国家としての形や土台を築くことであった。彼らには欧米列強と対等な外交を行えるような国家の骨格(憲法、議会制民主主義、教育による国民の思想性など)が出来ていなかったのだ。その上、戦うための兵力(陸・海軍)も列強の前ではなきに等しかった。
「民族自決」という美名で「三・一節」を讃えるのは結構だが、その前に、何が併合の要因だったか、どちらの国に「併合」が必要だったかよく考えてみるべきだ。
そして、日本軍(=旭日旗)に関してひとつ例を挙げれば、第一次世界大戦で、日英同盟を外交の基本としていた日本とドイツは戦っているが、戦後に日独が急速に仲良くなっていったのは何故だと思いますか。英、仏、米、露への不満が共通していたから、もちろんそれもあったが、もっと大きい理由は捕虜となっていたドイツ人が国に戻ったとき、日本が敵としては手強く、しかし捕虜を軍人として丁重に扱う誇りある文明国だったからだ。日本軍は誇りある人々に支えられていたからだ。
第一次世界大戦当時、朝鮮出身者は帝国陸軍、海軍には兵として採用されることはなく、1910年の憲兵補助員制度で、朝鮮国内での憲兵補助員として帝国陸軍に採用され、1919年にこの制度の廃止により、朝鮮総督府の警官として転官されただけで、一般の朝鮮人は日本軍の軍人にはなれなかった。
一般の朝鮮人が日本兵になったのは、1938年陸軍特別志願兵制度、1943年海軍特別志願兵制度からで、それ以前の朝鮮人の日本軍人は洪思翊に代表される、陸軍士官学校を卒業して士官に任官した者、李秉武のように旧大韓帝国軍から朝鮮軍人として日本陸軍に転籍した者に限られていた。
しかし、海軍兵学校、海軍機関学校などの海軍の士官養成諸学校は、終始朝鮮人の入校を認めなかったそうだ。
日本統治下で軍務に関係する職に就き戦没者となった朝鮮半島出身者のうち、朝鮮人日本兵を含む約2万1000人が靖国神社に合祀されているそうだ。
下の表は朝鮮人志願兵の志望者数である。陸軍特別志願兵制度導入初年度には、募集人員約400人に対して志願者2946人で7倍、39年は20倍、40年には27.6倍、41年は45.1倍、42年には62.4倍、海軍特別志願兵制度が導入された43年は募集6000人に対して30万人もの志願者があり50倍だったのだ。日本兵になるためにはものすごい競争志願倍率だったのだ。
(下表参照)
当時の彼らにとって日本の軍人となって旭日旗をつけて戦地に赴くことは単に生活の為だけだったのだろうか。靖国神社に合祀されるということが、その当時の彼らにとてどういう意味をもっていたのか。それを本当に知りたければ、韓国・朝鮮の人々は、彼らの残した手紙を(漢字で書かれた文章を)曇りのない目で読んでみるべきだ。彼らは「戦犯旗」をつけて死んでいったのではないはずだ。
もちろん、戦争を礼賛しているわけではありません。だが、自分たちの国の平和は自分達で守るのが当然であり、武器を持って向かってくる相手とは戦わずして平和はない。だからこそ戦ったのだろう。その時代日本人として。
そもそも韓国・朝鮮の人々は旭日旗(日本軍)を相手に戦ったことなど一度もないのに旭日旗で火病るのは、よほど変な刷り込みが出来ているのか、卑怯で弱虫なのか。
朝鮮人の特別志願兵制度への志願者(帝国陸軍)
志願者 /入所者数/ 選抜率/ 志願倍率
年度:上から
1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年
2946人/ 406人/ 16.2%/ 7.3倍
12,348人/ 613人/ 4.9%/ 20.2倍
84,443人/ 3,060人/ 3.6%/ 27.6倍
144,743人/ 3,208人 2.2% 45.1倍
254,273人/ 4,077人/ 1.6% 62.4倍
303,394人/ 6,000人/ 1.9% 50.6倍

コメント
こんばんは
どちらの国が併合を必要としていて、その恩恵を受けたのはどちらだったか、韓国・朝鮮・日本の人々は、まずよく勉強して理解する必要がありますね。きちんとした事実を相互に共有できればもうすこし普通の付き合いができるように思います。
実は私もこんなに朝鮮人志願兵の志望者数が増加していたのは知りませんでした。
2018/9/16(日) 午前 0:38 泉城
> 石田泉城さん
こんばんは。韓国の人々、朝鮮の人々はまず歴史的な時代背景をきちんと知るべきですが、最近耳にしたことに、「朝鮮人は国家のよりも民族が先にくる人々」だという言い分。とにかく(国家を助けてもらったとしても)「朝鮮民族」としての誇りが傷つけられたことの方が「恨」なのだとか。だったら日本は彼らのプライドを尊重して無用な手助けをしないことですね。
終戦近くに殺到した朝鮮人の志願兵が多かった事実ですが、彼らが非常に情緒的でとにかく「日の丸」をつけて戦いたかったのか、ただ日本軍の志願兵になることで周囲に自慢したかったのか、何らかの実利があると考えたのか、その当時の空気がどうだったのか、その事実を彼らがどう考えているのか知りたいような気もします。
2018/9/16(日) 午前 0:54 kamakuraboy 返信する
おはようございます。
どんなことでもそうですが、自立のためには、あまり手を差し伸べずに見守ることですね。
志願兵がどういう状況でどういう気持ちだったのかは知りたいところです。
2018/9/16(日) 午前 9:46 泉城
> 石田泉城さん
子育てにもいえることですね。
2018/9/16(日) 午後 10:12 kamakuraboy
「旭日旗とは日章と旭光を意匠化した日本の旗。光線(光条)が22.5度で開く16条のもの(十六条旭日旗)がよく知られている。 1870年に大日本帝国陸軍の陸軍御国旗(軍旗)として初めて使用され、1889年に大日本帝国海軍の軍艦旗としても採用された。現在は、陸上自衛隊で自衛隊旗、海上自衛隊で自衛艦旗として旭日旗が使用されている。」とあります。
アジアの中にあって、日本は明治維新後、欧米の産業革命に遅れること約100年、国家が一丸となって「和魂洋才」で欧米先進国の文物や制度を日本風にアレンジしながら取り入れ、欧米列強の植民地支配の波にのみこまれずに独立を保ちながら、条約改正の努力によって国際的地位の上昇をはかり、官営工場を建設し、江戸時代から継続する三井・三菱・住友などの商業資本を土台に日清戦争期に軽工業を、日露戦争期に重化学工業を発達させた。
非欧米諸国としては唯一初めて憲法を制定。日清・日露戦争に勝利したことで、当時の先進国=列強の1つ(五大国)と呼ばれるようになった。第一次世界大戦時には日英同盟を基本とする姿勢で参戦し、勝利者の側に立って、国際連盟(1920年1月~1946年4月解散)では英、仏、伊と共に常任理事国にもなった。
日清戦争の日本の勝利後、下関条約で清からの独立が認めれた李氏朝鮮にとって、事大主義で儒学しか学んで来なかった朝鮮の支配階級の人々も、両班以外には学問の機会がなく文明国とは程遠い生活をしていた朝鮮の平民の人々にとっても「民族自決」より先にくるべきは、帝国主義列強の中で生き残るために、国家としての形や土台を築くことであった。彼らには欧米列強と対等な外交を行えるような国家の骨格(憲法、議会制民主主義、教育による国民の思想性など)が出来ていなかったのだ。その上、戦うための兵力(陸・海軍)も列強の前ではなきに等しかった。
「民族自決」という美名で「三・一節」を讃えるのは結構だが、その前に、何が併合の要因だったか、どちらの国に「併合」が必要だったかよく考えてみるべきだ。
そして、日本軍(=旭日旗)に関してひとつ例を挙げれば、第一次世界大戦で、日英同盟を外交の基本としていた日本とドイツは戦っているが、戦後に日独が急速に仲良くなっていったのは何故だと思いますか。英、仏、米、露への不満が共通していたから、もちろんそれもあったが、もっと大きい理由は捕虜となっていたドイツ人が国に戻ったとき、日本が敵としては手強く、しかし捕虜を軍人として丁重に扱う誇りある文明国だったからだ。日本軍は誇りある人々に支えられていたからだ。
第一次世界大戦当時、朝鮮出身者は帝国陸軍、海軍には兵として採用されることはなく、1910年の憲兵補助員制度で、朝鮮国内での憲兵補助員として帝国陸軍に採用され、1919年にこの制度の廃止により、朝鮮総督府の警官として転官されただけで、一般の朝鮮人は日本軍の軍人にはなれなかった。
一般の朝鮮人が日本兵になったのは、1938年陸軍特別志願兵制度、1943年海軍特別志願兵制度からで、それ以前の朝鮮人の日本軍人は洪思翊に代表される、陸軍士官学校を卒業して士官に任官した者、李秉武のように旧大韓帝国軍から朝鮮軍人として日本陸軍に転籍した者に限られていた。
しかし、海軍兵学校、海軍機関学校などの海軍の士官養成諸学校は、終始朝鮮人の入校を認めなかったそうだ。
日本統治下で軍務に関係する職に就き戦没者となった朝鮮半島出身者のうち、朝鮮人日本兵を含む約2万1000人が靖国神社に合祀されているそうだ。
下の表は朝鮮人志願兵の志望者数である。陸軍特別志願兵制度導入初年度には、募集人員約400人に対して志願者2946人で7倍、39年は20倍、40年には27.6倍、41年は45.1倍、42年には62.4倍、海軍特別志願兵制度が導入された43年は募集6000人に対して30万人もの志願者があり50倍だったのだ。日本兵になるためにはものすごい競争志願倍率だったのだ。
(下表参照)
当時の彼らにとって日本の軍人となって旭日旗をつけて戦地に赴くことは単に生活の為だけだったのだろうか。靖国神社に合祀されるということが、その当時の彼らにとてどういう意味をもっていたのか。それを本当に知りたければ、韓国・朝鮮の人々は、彼らの残した手紙を(漢字で書かれた文章を)曇りのない目で読んでみるべきだ。彼らは「戦犯旗」をつけて死んでいったのではないはずだ。
もちろん、戦争を礼賛しているわけではありません。だが、自分たちの国の平和は自分達で守るのが当然であり、武器を持って向かってくる相手とは戦わずして平和はない。だからこそ戦ったのだろう。その時代日本人として。
そもそも韓国・朝鮮の人々は旭日旗(日本軍)を相手に戦ったことなど一度もないのに旭日旗で火病るのは、よほど変な刷り込みが出来ているのか、卑怯で弱虫なのか。
朝鮮人の特別志願兵制度への志願者(帝国陸軍)
志願者 /入所者数/ 選抜率/ 志願倍率
年度:上から
1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年
2946人/ 406人/ 16.2%/ 7.3倍
12,348人/ 613人/ 4.9%/ 20.2倍
84,443人/ 3,060人/ 3.6%/ 27.6倍
144,743人/ 3,208人 2.2% 45.1倍
254,273人/ 4,077人/ 1.6% 62.4倍
303,394人/ 6,000人/ 1.9% 50.6倍

コメント
こんばんは
どちらの国が併合を必要としていて、その恩恵を受けたのはどちらだったか、韓国・朝鮮・日本の人々は、まずよく勉強して理解する必要がありますね。きちんとした事実を相互に共有できればもうすこし普通の付き合いができるように思います。
実は私もこんなに朝鮮人志願兵の志望者数が増加していたのは知りませんでした。
2018/9/16(日) 午前 0:38 泉城
> 石田泉城さん
こんばんは。韓国の人々、朝鮮の人々はまず歴史的な時代背景をきちんと知るべきですが、最近耳にしたことに、「朝鮮人は国家のよりも民族が先にくる人々」だという言い分。とにかく(国家を助けてもらったとしても)「朝鮮民族」としての誇りが傷つけられたことの方が「恨」なのだとか。だったら日本は彼らのプライドを尊重して無用な手助けをしないことですね。
終戦近くに殺到した朝鮮人の志願兵が多かった事実ですが、彼らが非常に情緒的でとにかく「日の丸」をつけて戦いたかったのか、ただ日本軍の志願兵になることで周囲に自慢したかったのか、何らかの実利があると考えたのか、その当時の空気がどうだったのか、その事実を彼らがどう考えているのか知りたいような気もします。
2018/9/16(日) 午前 0:54 kamakuraboy 返信する
おはようございます。
どんなことでもそうですが、自立のためには、あまり手を差し伸べずに見守ることですね。
志願兵がどういう状況でどういう気持ちだったのかは知りたいところです。
2018/9/16(日) 午前 9:46 泉城
> 石田泉城さん
子育てにもいえることですね。
2018/9/16(日) 午後 10:12 kamakuraboy