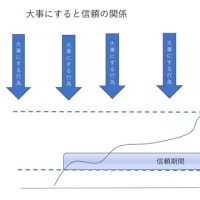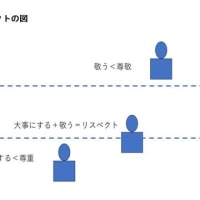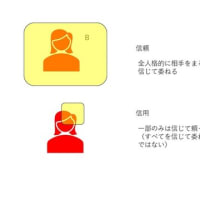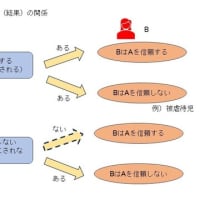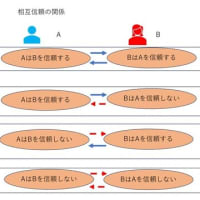2月5日(金)のNHK特報首都圏「学べない子供たち」
***番組webサイトより引用
小学校のときから学校の授業についていけず、学力を身につけることが出来ないまま大人になろうとする子どもたち。十代後半になっても将来の夢も見いだせずにいる。
こうした子どもたちは小さい頃から「学ぶ環境」が整えられていなかったという。大きな要因に貧困や家庭の崩壊などが挙げられ、「学べない環境」が「学べない」子どもたちを生み出しているという。
こうした負の連鎖を断ち切るためには何が必要なのかを考える。
******引用ここまで
番組概要(教育評論家 尾木直樹氏のコメント含む):
低学力は親の年収と無関係でなく、絵本の読み聞かせや新聞のニュースについて親子で話し合うなどができる家庭では子供の学力が高いことが示されました。
将来が描けない学べない子どもが急増しており、また子どもの低学力は社会の状況に大きく影響されるようになった。子どもが希望を持てない社会は問題。日本は学年主義で授業が進行し、未習得であっても進級していく。先進国の中でも1クラスあたりの人数40人というワーストな状況の中で、習得されているかどうかはほったらかしにされているのが日本の教育の現状である。ヨーロッパでは学年進行ではなく、習得したかどうかに比重を置いている。学びとっていくことを保証していく必要がある。学ぶことは子どもの権利である。ここが足りない。私費負担が高い国、日本。経済格差で不況の影響が子供の学力に直接きいてきてしまっている。低学力の子供は、勉強ができないというあきらめがある。
取り組みとして、学童保育の場所に教育機能を強化する事例がある。週に6日。指導は学年にとらわれずマンツーマンで行い、学生ボランティアや職員から基礎的な勉強を学年と関連なく受ける。すると、自分でも覚えられることに子供たちがきづいていった。
また、経済的な理由で勉強できない子どもについて、生活保護世帯が塾にいけるぎ行政支援なども例も。貧困の連鎖を断ち切るための試み。
学べるきっかけがあれば。政策として打ち出す時期。
子どもが学べなくなる背景は様々。経済事情、家庭環境により学ぶ権利がさまたげられ
る。今の学びは昔とは全然違ってきている。健康で人柄がよければよかったが、現代は知識基盤社会でIT社会。グローバリズム。学ぶ力がないと生きていけない。社会福祉からとらえていく必要がある。子ども学力・国家にとっても重要な要素であり、資源のないわが国としてはライフラインである。
感想:
子供の学力がもはや社会福祉的視点でバックアップしなくれはならないという発想に来ているなと思いました。そして、改めて思う日本の私費負担の高さ。私塾に行政負担をするよりも、良質の教員、学習環境を公立学校に確保していくことで、私費負担は減らせるはずです。もう一度、教育効果の高い学校づくりをシステムと資源(人、もの、お金)という視点で今、考えていく必要があります。緊急避難的には、番組で紹介された取り組みは有効かとは思いますが、同時に抜本的な方策(教育予算の比重を他のOECD先進国並みに高める。公立教育機関への投資、安い学費で良質な教育が受けられるようなシステムづくり)が必要ということです。
***番組webサイトより引用
小学校のときから学校の授業についていけず、学力を身につけることが出来ないまま大人になろうとする子どもたち。十代後半になっても将来の夢も見いだせずにいる。
こうした子どもたちは小さい頃から「学ぶ環境」が整えられていなかったという。大きな要因に貧困や家庭の崩壊などが挙げられ、「学べない環境」が「学べない」子どもたちを生み出しているという。
こうした負の連鎖を断ち切るためには何が必要なのかを考える。
******引用ここまで
番組概要(教育評論家 尾木直樹氏のコメント含む):
低学力は親の年収と無関係でなく、絵本の読み聞かせや新聞のニュースについて親子で話し合うなどができる家庭では子供の学力が高いことが示されました。
将来が描けない学べない子どもが急増しており、また子どもの低学力は社会の状況に大きく影響されるようになった。子どもが希望を持てない社会は問題。日本は学年主義で授業が進行し、未習得であっても進級していく。先進国の中でも1クラスあたりの人数40人というワーストな状況の中で、習得されているかどうかはほったらかしにされているのが日本の教育の現状である。ヨーロッパでは学年進行ではなく、習得したかどうかに比重を置いている。学びとっていくことを保証していく必要がある。学ぶことは子どもの権利である。ここが足りない。私費負担が高い国、日本。経済格差で不況の影響が子供の学力に直接きいてきてしまっている。低学力の子供は、勉強ができないというあきらめがある。
取り組みとして、学童保育の場所に教育機能を強化する事例がある。週に6日。指導は学年にとらわれずマンツーマンで行い、学生ボランティアや職員から基礎的な勉強を学年と関連なく受ける。すると、自分でも覚えられることに子供たちがきづいていった。
また、経済的な理由で勉強できない子どもについて、生活保護世帯が塾にいけるぎ行政支援なども例も。貧困の連鎖を断ち切るための試み。
学べるきっかけがあれば。政策として打ち出す時期。
子どもが学べなくなる背景は様々。経済事情、家庭環境により学ぶ権利がさまたげられ
る。今の学びは昔とは全然違ってきている。健康で人柄がよければよかったが、現代は知識基盤社会でIT社会。グローバリズム。学ぶ力がないと生きていけない。社会福祉からとらえていく必要がある。子ども学力・国家にとっても重要な要素であり、資源のないわが国としてはライフラインである。
感想:
子供の学力がもはや社会福祉的視点でバックアップしなくれはならないという発想に来ているなと思いました。そして、改めて思う日本の私費負担の高さ。私塾に行政負担をするよりも、良質の教員、学習環境を公立学校に確保していくことで、私費負担は減らせるはずです。もう一度、教育効果の高い学校づくりをシステムと資源(人、もの、お金)という視点で今、考えていく必要があります。緊急避難的には、番組で紹介された取り組みは有効かとは思いますが、同時に抜本的な方策(教育予算の比重を他のOECD先進国並みに高める。公立教育機関への投資、安い学費で良質な教育が受けられるようなシステムづくり)が必要ということです。