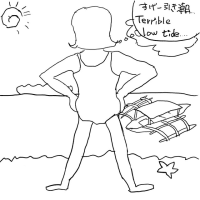Thus it came about that, three days later, I descended from the train at Styles St. Mary, an absurd little station, with no apparent reason for existence, perched up in the midst of green fields and country lanes. John Cavendish was waiting on the platform, and piloted me out to the car.
こういうわけで、3日後、私はスタイルズ・セント・メアリー駅に降り立った。なぜこんなところに駅があるのか、緑の草原の真ん中に立っていて、脇には田舎道がある。ジョン・キャベンディッシュがホームまで迎えに来てくれて、私はその車に乗りこんだ。
“Got a drop or two of petrol still, you see,” he remarked. “Mainly owing to the mater’s activities.”
「ガソリンを入れないとね」彼は言った。主におふくろが使うためだけどね。」
The village of Styles St. Mary was situated about two miles from the little station, and Styles Court lay a mile the other side of it. It was a still, warm day in early July. As one looked out over the flat Essex country, lying so green and peaceful under the afternoon sun, it seemed almost impossible to believe that, not so very far away, a great war was running its appointed course. I felt I had suddenly strayed into another world. As we turned in at the lodge gates, John said:
スタイルズ・セント・メアリーの村は小さな駅から3キロほどのところで、奥にスタイルズ荘が広がっている。7月の初めの暖かい日だった。午後の日差しのもと、エセックス州の緑に溢れた平和な広がりを見ていると、そんなに遠くないところで、大戦が進行しているとは信じ難い。別世界に迷い込んだかのような錯覚を覚えた。家の門に近づくと、ジョンが言った。
“I’m afraid you’ll find it very quiet down here, Hastings.”
“My dear fellow, that’s just what I want.”
「ここは君には静か過ぎるかもしれないね、ヘイスティングス。」
「いやぁ、それこそ私の求めていたものだよ。」
“Oh, it’s pleasant enough if you want to lead the idle life. I drill with the volunteers twice a week, and lend a hand at the farms. My wife works regularly ‘on the land’. She is up at five every morning to milk, and keeps at it steadily until lunchtime. It’s a jolly good life taking it all round—if it weren’t for that fellow Alfred Inglethorp!” He checked the car suddenly, and glanced at his watch. “I wonder if we’ve time to pick up Cynthia. No, she’ll have started from the hospital by now.”
「あぁ、のんびりしたいなら、ここは最高だよ。私はボランディアで週に2回農場で働くんだ。妻はそこで働いている。毎朝5時から昼まで乳搾りをしているよ。どう考えてみてもいい暮らしだよ。あのアルフレッド・イングルソープのことがなけりゃね!」そこで彼は突然我に返り、時計を見た。「シンシアを迎えに行けるかな。いや、今頃は病院を出たところかな。
“Cynthia! That’s not your wife?”
「シンシア! 君の奥さんかい?」
“No, Cynthia is a protégée of my mother’s, the daughter of an old schoolfellow of hers, who married a rascally solicitor. He came a cropper, and the girl was left an orphan and penniless. My mother came to the rescue, and Cynthia has been with us nearly two years now. She works in the Red Cross Hospital at Tadminster, seven miles away.”
「いや、母が面倒を見ているうちの一人だよ。母の級友の娘さんで、父親が死んで文無しの孤児になってね、母の手助けでうちに来てもう2年になる。11キロ余り先のタドミンスターの赤十字病院で働いてるんだ。」
As he spoke the last words, we drew up in front of the fine old house. A lady in a stout tweed skirt, who was bending over a flower bed, straightened herself at our approach.
“Hullo, Evie, here’s our wounded hero! Mr. Hastings—Miss Howard.”
彼がそう話すうちに、立派な古い家の前に着いた。恰幅のよい、ツイードのスカートを履いた女性が花壇の世話をしているところだったが、私たちに気づいて起き上がった。
「やぁ、エヴィ、英雄のおこしだよ。ヘイスティングス氏。ハワード嬢だ。」
Miss Howard shook hands with a hearty, almost painful, grip. I had an impression of very blue eyes in a sunburnt face. She was a pleasant-looking woman of about forty, with a deep voice, almost manly in its stentorian tones, and had a large sensible square body, with feet to match—these last encased in good thick boots. Her conversation, I soon found, was couched in the telegraphic style.
ハワード嬢は心のこもった、ほとんど痛いほどに私と握手をした。日焼けした肌に真っ青な目が印象的だ。40歳ぐらいの陽気そうな女性で、男のような野太い声をし、固太りの体に似合った足は丈夫なブーツを履いている。彼女の話は電報のようだと少し話してわかった。
“Weeds grow like house afire. Can’t keep even with ’em. Shall press you in. Better be careful.”
“I’m sure I shall be only too delighted to make myself useful,” I responded.
“Don’t say it. Never does. Wish you hadn’t later.”
「雑草は火事のようにすぐ大きくなる。ついていけないよ。家に入って。気をつけて。」
「私も喜んでお手伝いしますよ。」と私は返す。
「いいって。しないでいい。後悔するよ。」
“You’re a cynic, Evie,” said John, laughing. “Where’s tea to-day—inside or out?”
“Out. Too fine a day to be cooped up in the house.”
「皮肉屋だね、イヴィ。」ジョンが笑った。「お茶はどこで? 外か中か?」
「外。家にこもるにはもったいない日だよ。」