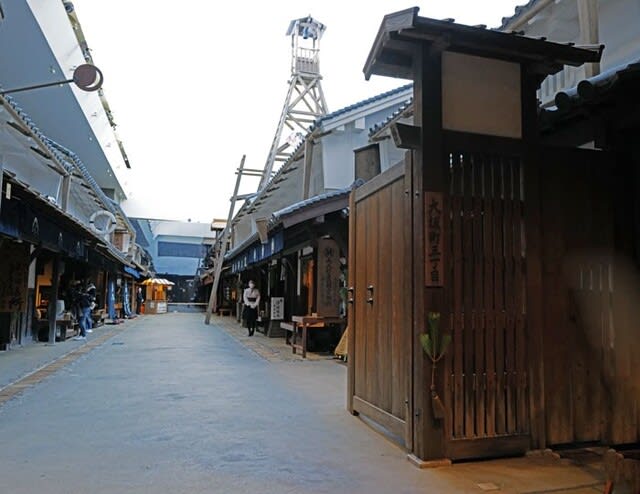咲きしより かねてぞ惜しき梅の花
ちりののわかれは 我が身と思えば
源実朝
梅の花が咲いたときには、もう既に
散る時を惜しまなければ
ならないのか私の未来と同じだ。
(我流訳)
大阪城公園梅林園の梅の木には
数枚の梅の和歌がぶら下がています。
その中の一句が源実朝
詠んだこの句です。
長男、源頼家は源頼朝と北条政子の間の生まれた
子で頼朝の死後、第2代征夷大将軍となりますが
実の祖父、北条氏に暗殺されます。この話は
、岡本綺堂作”修善寺物語”で
歌舞伎にも映画にもなりよく知られています。
次いで次男の源実朝が第3代征夷大将軍となり
さらに武士としては最初の右大臣の官位までの登りつめます。
しかし官位についた翌年27歳で暗殺されます。
これを考えると実朝が身を削って詠んだのが
この句かと思うとひときわ心打たれます。