12.兄弟相克
それにしても,儚いというか,呆気ないというか,真衡の生年を示す資料がないので,正確な年齢は分からないが,おそらく30代の壮年期であろう。
そうした時期に頓死とは,穏やかではない。
当然のことながら暗殺が考えられると云うことで,一番疑わしいのは何と言っても陸奥に野心を持つ義家であろう。
真衡を誅し,その養子であり妹婿の海道小太郎成衡を後継ぎに据えると,自分が清原氏を動かすことが出来るというものだ。
しかし,その後成衡は全く歴史から姿を消す。
おそらく,義家から利用価値無し,ということで,引導を渡されたからと思われるが,妻である義家の妹ともどもどうなったのか皆目分からない。
・・・ということは,清衡・家衡に肩入れすることにしたということだろうか・・・。
現に,真衡没後,清衡と家衡は義家に降伏する。
清原一族を一気に屠る絶好の機会だったが,義家はそれをせず,奥六郡の分割統治を,この兄弟に命じる。
兄清衡が肥沃な南三郡(胆沢,江刺,和賀)を領し,弟家衡は北三郡(岩手,稗貫,紫波)を領することになったのだが,当然のことながら家衡は不満であった。
生産力の高い南三郡に対し,北のそれは自然条件が厳しい。
やがてこの異父兄弟がぶつかることを,義家は意図的に煽ったのだろうか・・・。
そして,兄清衡を悉く贔屓したのは,何故だったのだろう。
周知の通り,義家父頼義は,清衡の父経清の仇である。
にも関わらず,その後も義家は清衡の肩を持つのである。
一説には,義家は清衡父経清を武人として尊敬していたので,息子の清衡に味方した,とも言われるが,義家はもっと現実的な男だ。
そんな情に流されるような男ではない。
逆に考えれば,清衡が義家を利用したという見方もできようが,果たしてどうなのだろう・・・。
家衡としても,義家に対して不満を訴えたであろうが,おそらく梨の礫だったことだろう。我慢の限界を感じたのか,家衡は突如として清衡舘を襲撃するという暴挙に出る。
応徳3(1086)年のことというから,最初の戦から3年が経過していた。
事前に察知していたのか,運良く外出中だったからか,清衡は物陰に身を潜めて難を逃れたが,清衡の妻子は哀れなことに犠牲になった。
父親が異なるとはいえ,兄の妻子を手に掛けるなど,尋常ならざる状況である。
家衡は,短期間のうちに清衡をそこまで憎むようになっていたのだろうか・・・。
或いは,誰かが清衡のことを讒訴したのだろうか・・・。
・・・とすると,そうしたことをして実を取るのは誰が有力だろう・・・。
後三年の役前半は,真衡vs清衡・家衡の争い,そして後半は家衡vs清衡+義家となっていく。
父頼義が10年以上かけても果たし得なかった陸奥の地が,義家のすぐ目前まで迫っていた・・・。
後半戦の行方や如何に・・・。
(続く)










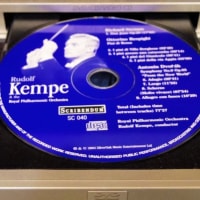
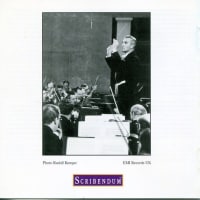
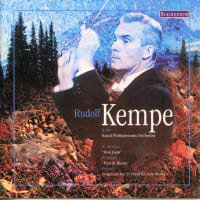







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます