『江戸名所図会』などで知られる考証家・斎藤月岑が天保15年(1844年)に著した『増補浮世絵類考』には、「写楽斎」の項に「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也」(通名は斎藤十郎兵衛といい、八丁堀に住む、阿波徳島藩主蜂須賀家お抱えの能役者である)と書かれている[10]。
長くこれが唯一の江戸時代に書かれた写楽の素性に関する記述だった。
当時の八丁堀には、徳島藩の江戸屋敷が存在し、その中屋敷に藩お抱えの能役者が居住していた。
また、蔦屋重三郎の店も写楽が画題としていた芝居小屋も八丁堀の近隣に位置していた。
“東洲斎”という写楽のペンネームも、江戸の東に洲があった土地を意味していると考えれば、八丁堀か築地あたりしか存在しない。
しかし、長らく斎藤十郎兵衛の実在を確認できる史料が見当たらず、また能役者にこれほどの見事な絵が描ける才能があるとは考えづらかったことから、「写楽」とは誰か他の有名な絵師が何らかの事情により使用した変名ではないか[注 3]という「写楽別人説」が数多く唱えられるようになった。
蔦屋が無名の新人の作を多く出版したのは何故か、前期と後期で大きく作品の質が異なるうえ、短期間で活動をやめてしまったのは何故か、などといった点が謎解きの興味を生んだ。
別人説の候補として絵師の初代歌川豊国、歌舞妓堂艶鏡[注 4]、葛飾北斎[注 5]、喜多川歌麿、司馬江漢[18]、谷文晁、円山応挙、歌舞伎役者の中村此蔵[19]、洋画家の土井有隣[20]、戯作者でもあった山東京伝、十返舎一九、俳人の谷素外[21]、版元の蔦屋重三郎[22]、朝鮮人画家金弘道[23]、西洋人画家[24]など、多くの人物の名があげられた。
しかし近年、以下の研究によって斎藤十郎兵衛の実在が確認され、八丁堀に住んでいた事実も明らかとなり、現在では再び写楽=斎藤十郎兵衛説が有力となっている。その根拠は以下の諸点である。
- 能役者の公式名簿である『猿楽分限帖』や能役者の伝記『重修猿楽伝記』に、斎藤十郎兵衛の記載があることが確認されている。
- 蜂須賀家の古文書である『蜂須賀家無足以下分限帳』及び『御両国(阿波と淡路)無足以下分限帳』の「御役者」の項目に、斉藤十郎兵衛の名が記載されていたことが確認されている。
- 江戸の文化人について記した『諸家人名江戸方角分』の八丁堀の項目に「写楽斎 地蔵橋」との記録があり、八丁堀地蔵橋に“写楽斎”と称する人物が住んでいたことが確認されている[注 6]。
- なお、国立国会図書館に所蔵される同書の写本には文政元年(1818)7月5日に書写された旨の奥書があるが、八丁堀地蔵橋の写楽斎の項には当該人物が故人であることを示す記号が付されており、斎藤十郎兵衛が文政3年(1820年)まで存命であったことと齟齬をきたしている[25][注 7]。
- 埼玉県越谷市の浄土真宗本願寺派今日山法光寺[注 8]の過去帳に「八丁堀地蔵橋 阿州殿御内 斎藤十良(郎)兵衛」が文政3年(1820年)3月7日に58歳で死去し、千住にて火葬されたとの記述が平成9年(1997年)に発見され、阿波藩に仕える斎藤十郎兵衛という人物が八丁堀地蔵橋に住んでいたことが確認されている。
- 斎藤十郎兵衛が住んでいた八丁堀地蔵橋は現在の日本橋茅場町郵便局の辺りになる。
以上のことから、阿波の能役者である斎藤十郎兵衛という人物が実在したことは間違いないと考えて良さそうだが、齋藤月岑の記した写楽が斎藤十郎兵衛であるという記述を確実に裏付ける資料は発見されていない[注 9]。
ただし、『浮世絵類考』の写本の一部[注 10]には「写楽は阿州の士にて斎藤十郎兵衛といふよし栄松斎長喜老人の話なり」とある。
栄松斎長喜は写楽と同じ蔦屋重三郎版元の浮世絵師であり、写楽のことを実際に知っていたとしてもおかしくはない(長喜の作品「高島屋おひさ」には団扇に写楽の絵が描かれている)。
なお八丁堀の亀島橋たもとにある東京都中央区土木部が設置した「この地に移住し功績を伝えられる人物」の案内板には、東洲斎写楽と伊能忠敬が紹介されている。










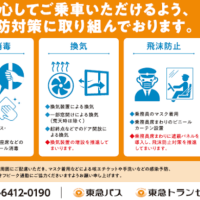






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます