〇評価
写楽は寛政6年5月の芝居興行に合わせて28点もの黒雲母摺大首絵とともに大々的にデビューを果たしたが、絵の売れ行きは芳しくなかったようである。特定の役者の贔屓からすればその役者を美化して描いた絵こそ買い求めたいものであり、特徴をよく捉えているといっても容姿の欠点までをも誇張して描く写楽の絵は、とても彼らの購買欲を刺激するものではなかったのである。
しかも描かれた役者達からも不評で、『江戸風俗惣まくり』(別書名『江戸沿革』、『江戸叢書』巻の八所収[4])によれば、「顔のすまひのくせをよく書いたれど、その艶色を破るにいたりて役者にいまれける」と記されている。
全作品の版元であった蔦屋重三郎と組んで狂歌ブームを起こした狂歌師の大田南畝は、「これは歌舞妓役者の似顔をうつせしが、あまり真を画かんとてあらぬさまにかきなさせし故、長く世に行はれず一両年に而止ム」(仲田勝之助編校『浮世絵類考』[5]より)、役者をあまりにもありのままに描いたからすぐに流行らなくなったと写楽の写実的な姿勢を評している。
ただし南畝の著した原撰本の『浮世絵類考』には岩佐又兵衛から始まって三十数名の絵師の名と略伝を記すが、そのなかで写楽のことを取り上げたのは、少なくとも南畝から見て写楽は無視できない絵師だったことを示しているという見方もある。
ドイツの美術研究家ユリウス・クルト(ドイツ語版)[注 12]はその著書『SHARAKU』(明治43年(1910年))[37]の中で、写楽のことを称賛し、これがきっかけで大正頃から日本でもその評価が高まった[注 13][注 14][注 15]。しかし写楽の役者絵が版行された当時においては、写楽よりも同時代の初代豊国描くところの役者絵が受け入れられたのであり、中山幹雄は勝川春英や初代豊国、歌川国政などの描いた役者絵と比べた上で、写楽を次のように評している。
「「「
江戸期当時の役者絵の流れは、勝川派から豊国へと移ってゆくのが主流で、
写楽は、あくまでも孤立した存在であったことを確認しておくべきであろう。(中略)これまで写楽の諸説を発表してきた人は、その役者絵を論じながらも江戸時代の歌舞伎にあまり造詣のない美術研究家かコレクターや好事家といった人たちで、一方、歌舞伎の専門家であっても絵を見る範囲の限られた人が写楽を追ってきた。
美術評論もすると同時に、歌舞伎の研究や舞台現場の経験もある者は、写楽をそれほど高く評価しないにちがいない。
(中略)写楽を捨て、豊国を選んだ江戸庶民の眼を、高く評価したい[39]
」」」
〇影響
写楽の役者絵は歌舞妓堂艶鏡、水府豊春、歌川国政などに影響を与えている他、栄松斎長喜も写楽に似た画風の役者絵を制作している。
かつてイギリスで制作された人形特撮番組サンダーバードでは、トレーシー家のラウンジでジェフが座る背後上部に「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人の妻やどり木」、向かって右壁面に「四代目岩井半四郎の乳人重の井」、更にデスク脇のサイドパネル部分には「中村勘蔵の馬子寝言の長蔵」が、それぞれ飾られている[40]。















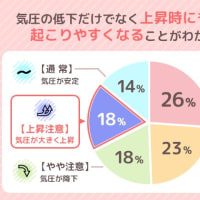
![【インド】ディープシークへの乗り換え、3割が前向き[IT]#2025/02/06#株式会社NNA](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/11/1a/01d2207db55c5a30a684d8fd5ddfe2de.png)
![【インド】ディープシークへの乗り換え、3割が前向き[IT]#2025/02/06#株式会社NNA](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/51/c7/37bbdc73aa1f8af24525ad2ab911f9c7.png)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます