
大学に入ってからは採集はほとんどいかなくなりました。ちょっと残念なことでしたが三浦でとれる魚の種類は限られていましたし房総までいくには遠かったからです。しかしあいかわらず魚は飼育していました。大学に入った頃1980年頃は90cm水槽で海水魚飼育をしておりました。いつも言いますが今から思うと実にいい加減な飼育方法でアンモニアの存在にはうるさかったですが硝酸塩などはほとんど無毒扱いで200mg/literなどはあたりまえだったかもしれません。当時の魚の急死は硝酸塩の蓄積といまでこそ判断できますが当時は急死などはわからずじまいなのでした。
90cm水槽は底面と側面サンプろ過方式でレイシーの毎分20lポンプと10lポンプでかなり強力に水流を起こし、ろ過していましたので水の輝き度はおおむね良好でした。側面ろ過には活性炭を主に使用し時々ゼオライトなども入れていたかもしれません。白点病になった記憶もほとんどなかったと思います。タンクメイツはチョウチョウウオやナンヨウハギ・ヒレナガハギ、クマノミ・コバルトなどで全部で10匹もいなかったと思います。気に入った少数の魚を飼うという私のスタイルはこのころからだったと今になって気がつきます。
採集友達の水槽はそのころからオーバーフロー方式がでてきており彼などはいちはやくそれを使用しサザナミヤッコやルリヤッコなどを飼育していました。ルリヤッコなどはいまでこそ1,000円もしない小型ヤッコのスタンダード版ですが当時はかなり高価で
当時3000円はしておりました。(今の貨幣価値ではその倍以上だったと推測します)。オーバーフロー方式もいまのような水槽一体版ではなく水道パイプとL字管を使って複雑に設計したものでした。彼もお気に入りの魚を少数のみいれて飼育しておりほとんどが採集魚でしたので白点になやまされることはあまりなかった思います。
つづく











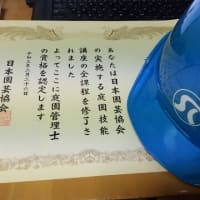
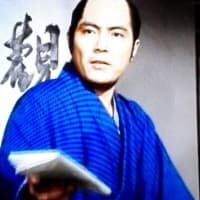



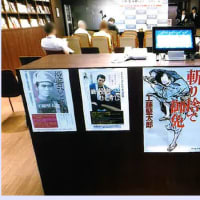


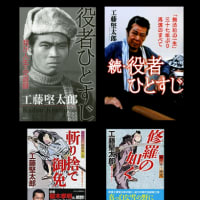



もっとも、病気の蔓延(主にストレス?水質悪化?)は
魚の数で、意外に決まるような気がします。
少なめで押さえておけば、そこそこの濾過でも(定期換水ありで)適応できる水質が作れそうな、、
おおければ、それなりにシステム構築すれば、、と言う感じに最近は思います。。
>魚の数で、意外に決まるような気がします。
いちがいには言えないと思いますが
魚の数より外部からの進入がもっとも感染の
確率が多いと思います。採集魚はその点、白点菌
の持込の確率はかなり少ないので概して丈夫です。
また水温の変化にもかなり鍛えられているので
チョウチョウウオなどタイドプールの高水温で
は33度ぐらいの水温でも元気に泳いでいます。
>おおければ、それなりにシステム構築すれば、、>と言う感じに最近は思います
それは賛同しますね。個人的な経験則からですが
ベルリン式などを除けばろ過はできるだけ強力な
ものが良いと思います。私んちの水槽は半ベルリン式ですがこれなども一つの方向性になってほしいまのです。
ショップで買った方が安全だ、、と言う思い込みがあったかもしれません。。
たしかに、ショップの水槽ないで病気をもらってくる確率の方が、
採取してきたさかなよりも多そうな気がしてきました。。
うちの水槽の場合は、
多分シストはいるんだろうな、、と言う感じなんですよね。。
昔は、白点になったコもいましたから。。
ただ、最近は見ないので、あれやらこれやら、いれないからかな、、と思ってましたが、
逆に、持ち込み頻度が減り、魚の絶対数がへり、、と
そういう(持ちこまない)環境になってたと言う事なんですね、、きっと。