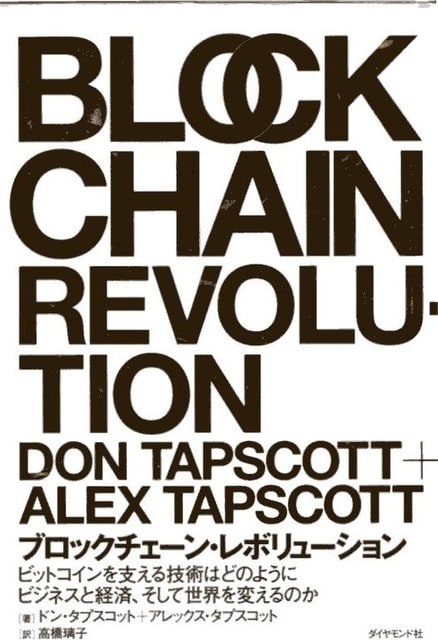
=">
目 次
Part1 革命が始まる
第1章 信頼のプロトコル
第2章 未来への果敢な挑戦
Part2 ブロックチェーンは世界をどう変えるのか
第3章 金融を再起動する
第4章 企業を再設計する
第5章 ビジネスモデルをハックする
第6章 モノの世界が動き出す
第7章 豊かさのバラドックス
第8章 民主主義はまだ死んでいない
第9章 僕らの音楽を取り戻せ
part3 ブロックチェーンの光と闇
第10章 革命に立ちはだかる高い壁
第11章 未来を創造するリーダーシップ
インターネットに足りなかったのは「信頼のプロトコル」
ブロックチェーンの主な特徴は
分散されていること。
パブリックであること。
高度なセキュリティが備わっていること。
「電球でも心臓モニターでも、そのモノがきちんと機能しなかったり対価を払わなかったりした場合、他のモノたちから自動的に拒絶されるようになるんです。」
本書ではブロックチェーンが可能にする新たな動きをさまざまな分野から紹介し、それがどのように世界を豊かにするかを見ていきたいと思う。
モバイル送金サービスのアブラ社は、ブロックチェーンを使った国際送金ネットワークを開発した。
だかその形態は二十世紀的なヒエラルキー組織ではなく、フラットなネットワークに近い形になるはずだ。
ドイツは、第二次世界大戦中、「エニグマ」と呼ばれる暗号機械を使って作戦指示を出していた。皮肉と言うべきか、それとも必然と言うべきか、ブロックチェーン時代の最先端のプライバシー技術にもこれと同じ名前がついている。
MITメディアラボ(所長伊藤穣一)は現在、プライバシーを完全に保証する分散型コンピューティング・プラットフォーム「エニグマ」の開発に取り組んでいる。準同型暗号とセキュアマルチパーティ計算という技術を使い、さらにブロックチェーンを利用して「誠実な行動に対して強いインセンティブを与える」ことで情報の秘匿を実現するプラットフォームだ。
ブロックチェーンの決定権やインセンティブ構造の中に、不誠実な行動を排除する仕組みが備わっているのだ。
ブリテンによれば、この「分散されている」という状態こそがブロックチェーンの肝である。発言権が広く分散されているおかげで、悪意ある個人やグループによる乗っ取りが不可能になるからだ。
ビットコインではプルーフ・オブ・ワークというしくみを取り入れている。時間とコストのかかる作業をした人に発言権を与えるというシステムだ。
プルーフ・オブ・ワークというしくみ
ビットコインのネットワークにつながっている各コンピューターは、専門用語でノードと呼ばれる。通常のノードはデータ転送の役目を負っていて、送られてきてデータに異常がないことをチェックすると、そのまま次のノードに受け渡す。
一方、ノードの中でも、未処理のデータをブロックに記録する役目を負ったコンピューター(およびその所有者)はマイナー(採掘者)と呼ばれる。マイナーはプルーフ・オブ・ワークの仕事をして、ビットコインのブロックチェーンに新たなブロック(情報のかたまり)をせっせと追加していく。
マイナーたちは、ネットワークに流れて来た未処理データを集めて、新しいブロックの形に加工する。ただし、ブロックを新しくつくるためには、まず難しいパズルを解かなくてはならない。解くのは難しく、答えが合っているかを確かめるのは簡単なパズルだ。パズルが解けた人は答えをネットワークに送信し、参加者たちが答え合わせをして、答があっていれば正しいブロックとして承認される。
ビットコインではインフレ防止のために、通貨供給量の上限が2100万BTCに設定されている。
サトシ・ナカモトは、利己的な行動がネットワーク全体の利益になるようにビットコインを設計した。
所得の分散のためのプラットフォーム
現代の会計学は、16世紀イタリアの数学者ルカ・パチョーリの発明に端を発している。彼は複式簿記と呼ばれる、とてもシンプルで便利なしくみを考案した。
複式簿記から三式簿記へ(会計へのブロックチェーン採用)
四半期決算などとぬるいことを言っている会社は、そのうち投資家から見捨てられるかもしれない。
(二〇一五年) オーガー(Augur)というスタートアップが史上最大規模のクラウドファンディングを立ちあげ、最初の一週間だけで、四〇〇万ドルが集まった。オーガーは誰の手も借りず、中間業者なしで、ブロックチェーンIPOで行った。
オーバーストック社は、……ブロックチェーン上で株式を発行し、売買できるプラットフォームを作った。
オーガーは、「集団の知恵」を利用したシステムだ。
ブロックチェーンを使えば、正確でエラーがなく、違法行為や不正に強く、流動性の高い予測市場が実現できる。
「われわれの予測市場では、取引先リスクを排除し、集中管理型のサーバーをなくし、ビットコインやイーサーなどの安定した暗号通貨を利用してグローバルなマーケツトを実現しました。すべての資金はスマートコントラクトに保存されるため、誰にも盗まれる心配がありません。」(オーガー)
これまでの金融業界はヒエラルキー的で行動や変化が遅く、巨大な権力にコントロールされた閉鎖的な世界であった。でもブロックチェーンなら、P2Pに支えられたフラットなソリューションが可能で、透明でありながらプライバシーが守られ、すべての人に開かれたイノベーティプな金融が実現できる。
イーサリアムは二〇一三年、当時十九歳だったロシア系カナダ人のブィタリック・ブテリンによって考案された。
コンセンシスは最先端のマネジメント科学にもとづく「ホラクラシー」というスタイルを取り入れている。上下関係がなく、コラボレーションに近いやり方で自主的に仕事を決定・実行する組織形態のことだ。
ホラクシーの基本方針には、「役職ではなく役割」「権限の移譲ではなく分散」「社内政治ではなく明確なルール」「大きな改編ではなく小さな改善の繰り返し」などがある。
彼等(コンセンシス)が将来的に目指しているのは、人間によるマネジメントを完全に廃し、スマートコントラクトが全体を制御する自律分散型の組織だ。
これまでインターネットの検索結果は、ある時点でのスナップショットにすぎなかった。ほんの数週間でインデックスが書き換えられ、検索結果が上書きされる。アントノブロスはこれを「二次元検索」と呼んでいる。二次元検索で使えるのは、ウェブ全体を横断する「横」の軸と、特定のウェブサイトを掘り下げる「縦」の軸の2種類だ。
ブロックチェーンはここに「時系列」の軸を追加する。いつ何が起こって今の状態になったのか、その経緯をすべて把握できるという意味だ。
「必要であれば何百年でも、何千年でも、完全な情報を保存しておけるのです。」とアントノブロスは言う。
スマートコントラクトはブロックチェーン上の「契約」である。ただし、紙の契約書と違って、それ自体に強制力のある契約だ。あらかじめ日時や執行条件を設定しておけば、プログラムが勝手にそれを実行してくれる。
ブロックチェーン技術のすごいところは、ヒエラルキーに頼ることなく、多数の人びと
が安定して仕事をやり通せるしくみを実現できることです。(ヨハイ・ベンクラー)
自律エージェントという言葉には、いくつもの定義がある。この本では、自分で周囲の
環境を読みとり、状況判断しながら仕事をするデバイスやソフトウェアを自律エ―ジェントと呼びたい。
これが自律分散型企業(DAE)の世界だ。ブロックチェーン技術と暗号通貨を基盤として多数の自律エージェントが手を結び、まったく新たな企業体を形成していく。
これは「二重使用の防止」に目を付けた画期的な解決策だ。知的財産のコピーは大きな問題となっていたけれど、ブロックチェーンがその問題をエレガントに解決するのだ。
とくに、コンピューターやデバイスが無線で直接接続され、おたがいに通信し合って自
律的なネットワークを形成する技術をメッシュネットワークという。網の目のようなネッ
トワークが全体をカバーしているので、どこかが壊れても別のノードがカバーして柔軟に
運用を続けられる。インターネットのインフラを整備することが難しい避地などでの活用が期待される技術だ。メッシュネットワークは中心を持たないため、アクセスポイントなどに依存するネットワークよりも障害に強く、規制や検閲の影響を受けにくいという特徴がある。
大規模な集中型システムのイメージが強いIBMも、いまやブロックチェーンを無視できなくなったようだ。「デバイス・デモクラシー」と題された報告書の中で、IBMはブロックチェーンの重要性を強調している。
分散されたIoTというわれわれのビジョンにおいて、ブロックチェーンはトラン
ザクション処理およびデバイス間インタラクション調整のフレームワークとなる。
インターネットは人と人とをつなげたが、ブロックチェーンはさらにモノとモノをつなげてくれるのだ。
インテルのミシェル・ティンズリーは、ブロックチェーンに大きく投資する理由を次のように説明する。
「パソコンが広く普及し、生産性は桁違いに上昇しました。パソコンをサーバーやデータセンター、あるいはクラウドにつなげることで、お金をかけなくても手軽にコンピューターパワーを活用できるようになりました。そして今、もうひとつの急速な変化がやってこようとしています。新たなビジネスモデルの登場です。
創造的破壊の十二のエリア
1 交通
2 インフラ管理
3 エネルギー・水・廃棄物
4 農業
5 環境モニタリングと災害予測
6 医療・ヘルスケア
7 金融・保険
8 書類や記録の管理
9 ビル管理・不動産管理
10 製造・メンテナンス
11 スマートホーム
12 小売業
創造的破壊の5つのベクトル(IBM)
❶リアルタイム検索と支払いによるモノの流動化
❷需要と供給の自動マッチング
❸リスク評価と信用のネットワーク化
❹システム利用の自動化
❺クラウドソーシングやオープンコラボレーションを活用したリアルタイムでパワフル
な価値統合プロセス
ところが、貯蓄について尋ねると、ニカラグア人はこう言うのだった。
「ああ、貯蓄は別にいいんですよ。みんな豚を持ってるから」
解決すべきは、貧しい人が金融や経済から排除されている状況だ。
*金融サービスから取り残された人たちを銀行は受け入れるためのインセンティブがない。
「アフリカの多くの国では固定電話が整備されていませんでしたが、携帯電話がこれを解決しました。一足飛びに携帯の時代になったのです。ブロックチェーンはこれと同じ効果を金融の世界にもたらすでしょう。」(タイラー・ウィンクルボス)
*スマートフォンをATMにかえる技術をアブラ社が開発した。
アブラはブロックチェーンの分散ネットワークとスマートフォン技術、そして人のつながりという3つの一見ばらばらな要素をひとつに結びつけ、単なる送金アプリではないグローバルな価値交換プラットフォームを実現しようとしている。
現在、エストニアは世界でも最先端のIT国家として名を馳せている。……。
エストニアの電子政府は、分散および相互接続性、オープン性、サイバーセキュリティを軸に設計されている。
エストニアは強固なセキュリティを実現するため、キーレス書名基盤(KSI)というしくみを導入した。これはブロックチェーン上で数学的にデータの真正性を保証する仕組みで、管理者を必要としない署名システムとして注目を集めている。
とくに若い人は選挙に希望を見出せず、別のやり方でシステムを変えたいと望んでいる。
彼等の車には「投票するな! やつらに力を与えるだけだ」というステッカーが貼られている。
典型的なのが銃規制問題だ。アメリカ人の92%は銃の購入者の身元調査を望んでいるのに、潤沢な資金を持つ全米ライフル協会がそうした規制法案をすべて握りつぶしている。「人民の、人民による、人民のための政治」はどこに消えてしまったのだろう。
スマートコントラクトは自動的に実行される契約だ。人間が恣意的に変えられる部分がないので、結果に対する不安がない。
ウェブサイト上の情報公開は増えてきたが、ブロックチェーンならリアルタイムの情報を自動的に、正確さが保証された状態で確認できるというメリットがある。
「メディアラボ以前から、電子通貨にはずっと関心があったんです」と伊藤穣一は言う。「90年代にはすでに、デジキャッシュという初期の電子決済システムのテストサーバーを動かしていました。」
2つの世界大戦を経て、政治や経済の合意だけでは長期的な平和が保たれないという事実を人類は思い知った。各国の関係は頻繁に、ときには劇的に変化する。持続的な平和を望むなら、もっと深く普遍的なもの、人々の倫理観や物の見方に働きかけていく必要がある。
革命にたちはだかる高い壁
課題1 未成熟な技術
課題2 エネルギーの過剰な消費
課題3 政府による規制や妨害
課題4 既存の業界からの圧力
課題5 持続的なインセンティブの必要性
課題6 ブロックチェーンが人間の雇用を奪う
課題7 自由な分散型プロトコルをどう制御するか
課題8 自律エージョントが人類を征服する
課題9 監視社会の可能性
課題10犯罪や反社会的行為への利用
やり直しがきかないという問題は、スマートコントラクトの窮屈さという問題にもつながつてくる。
大手マイニング企業のビットフューリーは、ビットコインのマイニングに特化したASIC(特定用途向け集積回路)を開発し、エネルギー効率がよく処理能力の高いマイニングマシンを生み出した。
人々のアイデンティティと社会のルールが厳密にコード化されたら、機械が人々を支配するディストピアが出現するのではないか。
「金や権力でネットワークを支配しようとする者が現われたら、ビットコインから分岐(フォーク)して新たなネットワークに移行してしまえばいいんです」(キオ二・ロドリゲス)
理論的には、全マイナーの計算能力の過半数を手にいれると、任意の取引を承認して
ブロックチェーンに登録することが可能になる(51%攻撃)。好きなだけ不正ができるということた゛。
2015年7月には、(有名な)科学者や技術者が名を連ね、自律型兵器の禁止を呼びかける公開状を提出している。
「大規模なネットワーク全体のデバイスを適切に管理するしくみを整えておく必要かあります」(ヴィント・サーフ)
シルクロードと言うサイト
「量子コンピューターは、きわめて大きな数字の素因数分解をきわめて高速に実行できると考えられています。そして公開鍵暗号の大半はそういった素因数分解で解ける性質のものです。量子コンピューターが実用化されれば、世界中の暗号インフラは根本的な変化を迫られることになります」(スティーブ・オモハンドロ)
イーサリアムは正式には「任意の状態をとることのできる、チューリング完全なスクリブティング・プラットフォーム」と説明されている。チューリング完全であるとは、要するにどんな処理でも実行できるということだ。
(ブロックチェーンのスタートアップを)年金基金の運用先としても注目を集め始めた。カナダ最大の公的年金基金を親会社に持つOMERSベンチャーズというベンチャーキャピタルも、2015年にブロックチェーン企業への投資を開始した。同社のジム・オーランドは「インターネットでいうウェブブラウザのようなキラーアプリ」の登場に期待していると話す。
国の管理を超えた暗号通貨が流通する中で、中央銀行はどうやって仕事をすればいいのだろう。経済がうまくいかないとき、中央銀行は金融政策で通貨をコントロールしようとする。しかし暗号通過は国が発行したものではないし、世界中に分散して存在しているので、金融政策で動かすことは不可能だ。
もつともシンプルな方法は、中央銀行がビットコインを保有することだ。
ブロックチェーン時代のガバナンス・ネットワーク
1 ナレッジ・ネットワーク
2 オペレーション・ネットワーク
3 政策ネットワーク
4 アドボカシー・ネットワーク
5 監視ネットワーク
6 プラットホーム
7 標準化ネットワーク
8 ステークホルダー・ネットワーク
9 移住者ネットワーク
10ガバナンス・ネットワーク
政策ネットワークがめざしているのは、政府の政策決定能力を奪うことではなく、トップダウンの意思決定システムを相談とコラボレーションのモデルに変えていくことだ。
すべての試みが生き残るわけではない。でもサトシのビジョンに従っていれば、成功できる可能性はおそらく高まる。
解説
夢のつづき――ブロックチェーンをめぐる自作自演インタビュー
若林 恵(『WIRED』日本版編集長)
ブロックチェーンをちゃんと「理念」として捉えた本っていうことですかね。
……、「会社」というものがない世界を実現すべく、ブロックチェーン・テクノロジ―を使ったお仕事プラットフォームを作っている元クリエイタ―やら、……。
でも、ブロックチェーンというコンセプトは、世界をまったく違った目で捉えることを可能にしてくれるし、現状のシステムやパラダイムのオルタナティブを提示し、そこに新しい「夢」を見ることを可能にもしてくれるわけです。
これは彼(タプスコット)のTEDの講演の冒頭でも語られることで、この本の冒頭でも書かれていますけど、要は、今までのインターネットっていうのは、「情報のインターネット」でしかなかった、と。しかも、そこでやり取りできる情報は、基本的には「コピーされた情報」でしかなかった。
インターネットが一般化した時に、多くの人がその実現を夢見た、P2Pで分散的にネットワーク化された個が、中央集権的に編成された世界にとって代わるという未来は、実は言うほど実現されていなくて、実際インターネットが捉えるものは、ごくごく限られたものでしかなかったんですね。逆に言うと、インターネットのポテンシャルは、むしろブロックチェーンという技術・コンセプトによって、むしろ飛躍的に拡大・拡張することができる、ということであって、タプスコットさんが、「ブロックチェーン・テクノロジーこそが次世代のインターネットの中心部分なのだ」と語ること、もしくは大物VCのマ―ク・アンドリーセンのような人が、これをして「インターネット以来の衝撃」と語ることの真意は、まさに、そこにあるんですよね。
*二〇一九年三月十一日抜粋終了。
*ソニー出井さんが(朝日新聞・2019.3.10 平成経済インタビュ―)で、「IT化遅れ 気づけば米中に敗北」の発言の通り、日本経済はどん詰まりにきている。
 以下のキ-ワ-ドをコピペして右サイドのこのブログ内で検索でお楽しみください。 → 情緒 演繹 帰納 内臓感覚 遊行寺 戦争 参考文献 高野聖 力業 ギリシャ 暗号 ソクラテス 香取飛行場 j・ロック 身体 墓 禅 401k 井筒 気分 講演 説話 小説 旅行 野球 哲学 空海 イスラ-ム かもしかみち 長安 干潟 民俗学 混沌 画像 大乗起信論 定家 神話 フェルマー 遊行 国家 気分の哲学
書評 飯島宗享
以下のキ-ワ-ドをコピペして右サイドのこのブログ内で検索でお楽しみください。 → 情緒 演繹 帰納 内臓感覚 遊行寺 戦争 参考文献 高野聖 力業 ギリシャ 暗号 ソクラテス 香取飛行場 j・ロック 身体 墓 禅 401k 井筒 気分 講演 説話 小説 旅行 野球 哲学 空海 イスラ-ム かもしかみち 長安 干潟 民俗学 混沌 画像 大乗起信論 定家 神話 フェルマー 遊行 国家 気分の哲学
書評 飯島宗享  以下のキ-ワ-ドをコピペして右サイドのこのブログ内で検索でお楽しみください。 → 情緒 演繹 帰納 内臓感覚 遊行寺 戦争 参考文献 高野聖 力業 ギリシャ 暗号 ソクラテス 香取飛行場 j・ロック 身体 墓 禅 401k 井筒 気分 講演 説話 小説 旅行 野球 哲学 空海 イスラ-ム かもしかみち 長安 干潟 民俗学 混沌 画像 大乗起信論 定家 神話 フェルマー 遊行 国家 気分の哲学
書評 飯島宗享
以下のキ-ワ-ドをコピペして右サイドのこのブログ内で検索でお楽しみください。 → 情緒 演繹 帰納 内臓感覚 遊行寺 戦争 参考文献 高野聖 力業 ギリシャ 暗号 ソクラテス 香取飛行場 j・ロック 身体 墓 禅 401k 井筒 気分 講演 説話 小説 旅行 野球 哲学 空海 イスラ-ム かもしかみち 長安 干潟 民俗学 混沌 画像 大乗起信論 定家 神話 フェルマー 遊行 国家 気分の哲学
書評 飯島宗享 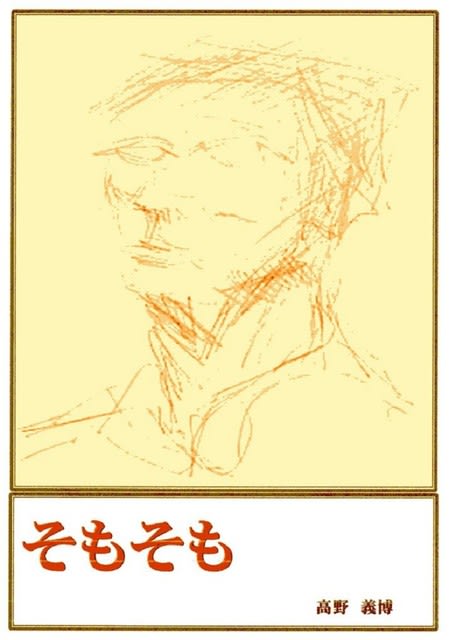

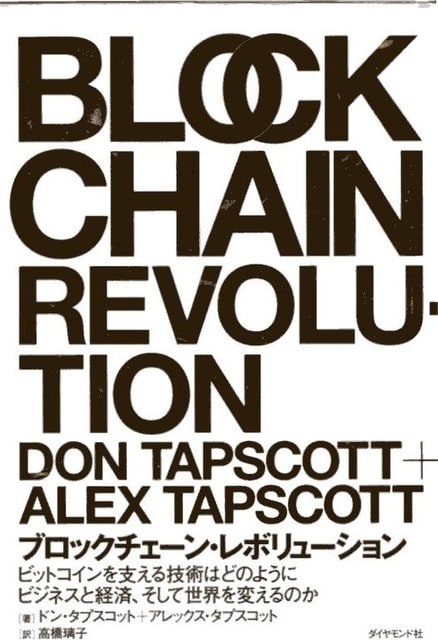 =">
=">