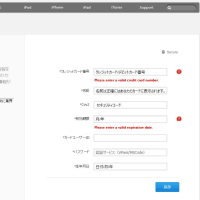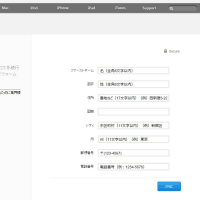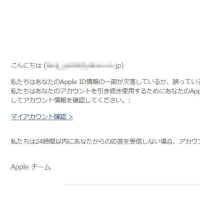シーベルト、ベクレル色々な単位でマズゴミが大騒ぎしていますが、これらのバックグラウンドは普段幾つなの?。
解り易く言えば騒音の例が良いだろう。閑静な住宅街で騒音測定したら生活音やら何やらで40dbだったとする。これをバックグラウンド騒音と言うのだがもしそこに右翼の街宣車が来たら一気に120dbになった。と・・・
これだけ説明すると120dbならさぞかし五月蝿いのだろうと予想できるが中身は生活音+街宣車音の120db。つまり街宣車の五月蝿さが80dbという事になる。
つまり原発事故前のコウナゴやカレイ、ヒラメは何ベクレルなの?って事。
ここが無いとどれだけ増えたのかさっぱり解らない。
それともお役所のガイドライン、あてになるかなw
小魚から放射性物質…影響ない程度・規制値なし(読売新聞) - goo ニュース
(読売新聞) 2011年04月04日 20時37分
茨城県北茨城市の平潟漁協は4日、同市の長浜沖でとれたコウナゴから1キロ当たり4080ベクレルの放射性ヨウ素131が検出されたと発表した。
魚介類の放射性ヨウ素についての規制値はないが、飲料水で300ベクレル、野菜類で2000ベクレルと定めた規制値に比べて高い。
コウナゴは1日に船びき網漁で捕獲された。1キロ当たり447ベクレルの放射性セシウムも検出されており、魚類の暫定規制値の500ベクレルに近い値だった。同漁協は、1日までに日立沖などで採取した魚介類5品目について、民間検査機関で放射性物質を検査。カレイやヒラメなどほかの魚介類から検出された放射性ヨウ素は最大でも35ベクレルで微量だった。
茨城県沖のコウナゴ漁は震災で中断しており、同県産のコウナゴは現在、市場に出回っていないという。
厚生労働省によると、魚類に関する放射性ヨウ素の規制値は、海水で拡散することや短期間で放射線が半減することなどから、危険性が低いとして定めていないという。