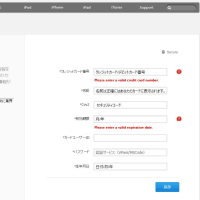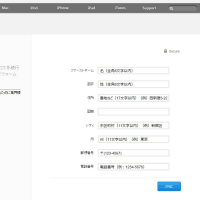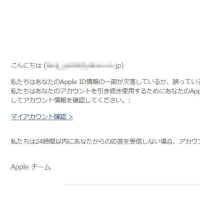生活様式が大きく変わってきたのも原因かな?と言う気がします。
核家族化や共稼ぎなど多くのお母さんは多忙な日々を送っている事と思います。
一方この御時世でも”私は専業主婦で姑居ないよ~”なんて幸せな方もおいでになる事は事実です。
祖母や私らの母の時代はしっかり食べて元気な子供をと言う具合でしたが昨今の社会では妊婦さんの肥満を考えているのかどうか医療関係の指導もそのあたりはかなりデリケートみたいですね。
しかし素人と言うのは医者のさじ加減がわかりにくい物で”太るな”と言われれば”では痩せないと”と短絡的な方向に行きがちではないでしょうか。まぁこの様な状況で生活されている人々に”ああしろ、こうしろ”と言っても皆忙しくてそんな細かな事まで構ってられないのが現状なのかな。
もう一つマズゴミによる影響も考えられませんかね~。よく育児系の雑誌に
”マタニティママもファッショナブルに”って・・・そんな狸腹してファッショナブルさ追求すんの!?。
誰の責任云々よりもバランスの良い指導と実践方法が求められないかな。
影響受けるのは子供たちだもの。
ちなみにウチの子も低体重児でしたけど・・・
低出生体重児の増加なぜ? 病院と2大学が研究へ(神戸新聞) - goo ニュース
2010年9月22日(水)16:07
2500グラム未満で生まれる低出生体重児の割合が増えていることから、パルモア病院(神戸市中央区)と神戸大、早稲田大は11月にも、母体の栄養状態と子どもの発育の関連についての調査研究をスタートさせる。海外では、出生体重が低いと生活習慣病のリスクが高まることなどが分かっているが、国内では長期的な研究例はない。妊婦の体重増に慎重なあまり、胎児の低体重への指導が不十分との指摘もあり、妊婦の栄養指導での活用が期待される。
出生数が減る中、出生数に占める低出生体重児の割合は増加しており、2009年は9・6%(10万2671人)と30年前のほぼ倍。欧米の研究では、出生体重が低いと成長後、糖尿病や心筋梗塞(こうそく)などの発症頻度が高いとされる。
パルモア病院などの研究班は、母体の栄養状態の悪化に注目。メンバーで産婦人科医でもある早稲田大の福岡秀興教授(63)らが首都圏で妊婦198人を調べたところ、約9割が必要カロリーを摂取していなかった。妊娠高血圧症候群などを避けるため妊婦の体重増に慎重な産院が多い半面、胎児が低体重になりやすい「やせ」への指導は不十分という。
研究班では、パルモア病院を受診する妊婦200人に血液検査などを実施し、妊娠中と分娩(ぶんべん)時のビタミンD、鉄など栄養素の含有量を調べ、食生活の聞き取りをする。出生児は、生後すぐと1カ月半健診時に臓器などを計測し、5歳まで定期検査で生活習慣病や発達障害などの有無を調べる。
これらの研究を踏まえ、母体の栄養状態の目安となるバイオマーカー(生体指標)を定め、健診などで広く活用する。さらに子どもの疾病との関連を探り、胎児期からの予防を目指す。小児科医で、研究班の神戸大大学院の飯島一誠・特命教授(54)は「日本では低体重への危機意識があまりに低い。経験則でなくデータに基づく栄養指導を確立したい」と話している。