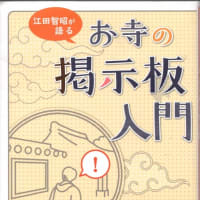村にあれ 森にあれ 窪地にあれ 高地にあれ
良き人の住む地は いずこもたのし 朝比奈宗源
昨秋11月に長野県木曽・妙覚寺をたずねた時、境内にある石碑に刻まれていたことばです。朝比奈宗源元円覚寺派管長(1891~1979)のご揮毫で、「釈尊のことば」と記されています。浅学の私には原典を見いだせないので、朝比奈宗源管長のことばとしてしまいました。おそらく、「ダンマパダ(法句経)」とか「スッタニパータ」にあることばだと思うのですが、みつかりません。
木曽路の澄んだ空気のなかで、「村にあれ、森にあれ、窪地にあれ、高地にあれ」というフレーズをよむといっそう澄んできたのを思い出します。
解説の必要もないことばですが、「良き人」というのがくせ者です。悪人に対するのか、善人なのか。有名な言葉だったら恥ずかしいことです。
ところで、私がしている唯一の社会的公務といえば、教誨師でしょうか。刑務所に出向いて、受刑者に宗教教誨をおこないます。
数人を相手にするグループ教誨と、一対一の個人教誨があります。少し前に個人教誨の機会がありました。その日は受刑者の母親の祥月命日だという。お経を読んだあと、受刑者が身の上のことや犯した罪のことを、問わず語りに話してくれました。午後の日ざしが差しこむ刑務所内の教誨室と呼ばれる畳の部屋にすわって話しを聞きました。聞きながら思い出したのは、森鴎外の『高瀬舟』です。
ご存じのとおり、江戸時代は寛政(1789~1801)の頃、京都町奉行所の同心、羽田庄兵衛が、弟殺しの罪人、喜助を護送して高瀬川を下っていく小舟のなかの出来事です。
このブログを書くにあたり、『高瀬川』を読み直してみました。すると、「問わず語り」ではなく、同心の庄兵衛は、「晴れやかで目にはかすかなかがやきがある」罪人喜助の挙動を不思議に思い、「喜助、お前何を思っているのか」と問うてしまうのですね。そして、罪人とおのれのを比べて「どうも喜助のような心持ちにはなれそうにない」という思いにいたる。
さて、少し前の個人教誨の時、私はほとんど問いかけをしなかった。問わなかったのに話してくれたのは、その前にお経を一緒によんで、わすが10分ほどだけどいっしょに坐禅をしたからではないか。読経と坐禅が、問わなくても話したいという気分にしてくれたと思うのは、坊主の手前味噌でしょうか。
今月のことば、「良き人の住む」の「良き」を抜いて「人の住む地はいずこもたのし」と読んでみては。
生涯を旅に生きた最後のゴゼと呼ばれる小林ハルさんに次の言葉があるといいます。
「いい人と歩けば祭り。悪い人と歩けば修行」
冒頭の写真に変な影が映っていますが、怪しい写真ではなくて、石碑がよく磨かれているので、景色と撮影者が鏡のように映っているからです