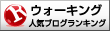森忠政公のお墓です。
森忠政~1570~1634年。
織田信長に仕えた森可成の六男。幼名・千丸。
関ケ原の戦い後は、信州・川中島13万7500石を安堵。その後、美作・津山藩18万6500石の藩主になった。
先月、この森忠政の記事があったのを思い出しましたので、載せておきます。
「森忠政」猛将一家も関ケ原は“見張り役”
森家は「武を誇る家柄」である。
津山郷土博物館(岡山県津山市)の館長、尾島治さんは「世間もそう見ているし、本人たちも自任していた」と話す。
森忠政の父と5人の兄は全て戦いの場で生涯を終えた。
父・可成(よしなり)と長兄・可隆(よしたか)は、忠政が生まれた元亀元(1570)年、織田信長の近江・朝 倉攻めで討ち死に。
後を継いだ次兄・長可(ながよし)は「鬼武蔵」の異名を持つ猛将。豊臣秀吉に従い、徳川家康と戦った小牧・長久手の戦い(1584年) で戦死した。
その2年前の本能寺の変では忠政の3人の兄、蘭丸、坊丸、力丸が落命。
このとき忠政13歳。
信長に仕え始めたばかりで安土城に残っていた。
明智勢に攻められる前に脱出。
そして長可の戦死後、若くして家を継ぎ、豊臣大名として活躍する。
秀吉死後は家康に接近した。
小山評定後、川中島・海津城(長野市)に戻り、地元を守備。徳川秀忠率いる徳川本隊が信州経由で関ケ原に向かうが、上田城で真 田昌幸に苦しめられた。
この真田勢や信州、越後方面の見張りを任された。
「後ろの守りがしっかりしていないと徳川勢も西へ向かうことができない。
重要な役 割だった」と尾島さん。
ただ、忠政は書状を送って家康、秀忠にしきりに関ケ原への出陣を願い出た。
書状のやり取りは「情報収集の面もあっ た」(尾島さん)が、武功を挙げるこれ以上にない舞台。
戦場で目に見える手柄を立て、時には主君の盾になって忠義を示す。
たとえ討ち死にしても、その評価 が家を繁栄させ、次の世代につながる。武辺者(ぶへんもの)の出世は命懸けだった。
(産経ニュース、2015年4月12日19:00より)