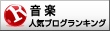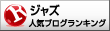司馬遼太郎の竜馬を久しぶりに読み直した。8巻あるが、なかなか読みごたえがある。維新で日本を救ったのは、やはり竜馬であると実感。また、「世に生を得るは、事をなすにあり」という生きざまは、座右の銘にしたい。維新の竜馬、戦後の白洲次郎こそが、日本を陰で支えてきた。
「中国が世界をメチャクチャにする」(ジェームズキング)を読了。イタリアの伝統的な織物産業や米国中西部の工作機械工業など、世界中の産業が経済開放後の中国の影響を受ける実状と、環境破壊や知的所有権問題など中国の抱える歪みなどが具体的な事例を踏まえてレポートされている。
山崎豊子の不毛地帯を読了した。瀬島龍三をモデルとしたとされる主人公壱岐正は、シベリアで11年もの長期にわたって過酷な状況の中で抑留された後、帰国して近畿商事に迎えられ、戦闘機、自動車、石油などをめぐり商社間の熾烈な戦いを生き抜いていくが、大本営参謀としての責任と戦争のために命を奪われていった仲間への思いが消えることはなかった。戦争の残した傷跡の深さをあらためて感じさせた。
藤沢周平の蝉しぐれを読み終わった。舞台は江戸期でありながら、時代劇のような現代劇のような、友情や愛をさわやかに唄った青春物語であると同時に、派閥抗争をめぐるスリリングな展開も味わい深く、なかなかの傑作であった。
北康利氏による白洲次郎を読んだ。自分の哲学、プリンシプルを明確に持ち、それを貫く姿勢、激しいまでに闘う姿勢、そして、決して表舞台に出ることなく黒子となって戦後の日本を体を張って守ろうとした次郎の姿に感動するとともに、戦後の日本を、GHQの横暴から、また米国以外の脅威から、守ったのは、本当は次郎の陰の努力によるものであることを実感した。彼の前には政界も官界も財界もかたなしではないか。自分も彼のような生き様の一端でも学び、実行できればと思うばかりである。
松本で開かれていたサイトウキネンフェスティバルへ招待で出かけた。小澤征爾さん指揮によるメンデルスゾーンのオラトリオ「エリア」。ユダヤ教の預言者エリアの偉業を讃えるオペラで、素人の私にも素晴らしさは十分に伝わってきた。ただし、内容は宗教に関わるものであり、極めて重いものがあり、かならずしも正確に理解できたわけではないと思う。何故松本で開かれることになったのかは知らないが、2004年には素晴らしい芸術館が完成し、今回もそこで演奏を聴くことができた。小澤さんの健康が心配されていたようであるが、素晴らしい演奏を聴かせていただき幸せなひと時を過ごすことができた。
藤原正彦の「国家の品格」を読む。「論理」の限界を説く一方で、情緒や惻隠の情などの重要性を説いている。若干論理展開が短絡的なところもあるが、この書に関連して思うのは、やはり日本は日本ならではの文化、思想、歴史を大事にし、日本人一人ひとりがそのidentyを見失わないことが重要であるということ。言語や技術を超えた人間力が今問われている。国際的なパワーポリティクスに単に受身で流されることのない日本、日本人でありたい。
池波正太郎の「男の作法」を読む。全編を通じて感じさせるのは、現代では忘れられかけてしまった粋の文化。人間は死ぬものであるという、その有限の運命を意識することが大事であると言っているが、まさにそのとおりだと思う。これによって生き様は変わってくる。仕事への取り組み方も、時間の使い方も、家族や他人への接し方も、何もかも、すべて変わってくる。この本は、そのほかにも、自分の気づかなかった日常のくらしにおける粋な常識を盛りだくさん教えてくれる。世に出されてからもう何年も経っており、もっと早くめぐりあっていればと思う一冊である。
天満敦子のヴァイオリンコンサートに出かけた。ルーマニアのPormbescu作曲の”Balada(望郷のバラード)”、バッハの”Partita”、アンコールで演奏してくれた坂本九の”見上げてごらん夜の星を”が特に良かった。繊細さと力強さのいずれにも豊かな表現力のある、しかも音色に深みのあるすばらしい演奏だった。前日青森で演奏したということだが疲れを感じさせない演奏で、しばし満ち足りた時間を過ごすことができた。作曲家Pormbescuは祖国ルーマニアの独立運動に身を投じ29歳の若さでこの世を去ったが、100年の時を経て彼の楽譜が天満の手に渡り、世界中の人の心を魅了しているとのことで、作曲家の思いを心に浮かべながら聴いた無伴奏のその調べには、やはり心を打たれた。

数年前にカリフォルニアを旅した時、カルメルのホテルで出会った一枚が、ピアニストJessica Williamsの"Joyful Sorrow"。中でも、Bill Evansにちなんだ"I Remember Bill"は、彼女自身の作曲による、限りなく透明で穏やかで静謐な調べで、その調べが流れ始めた瞬間にその悠久の世界に思わず引き込まれてしまう珠玉の作品。いつ聴いても心が落ち着く一曲であり、併せてその時の旅の思い出に浸らせてもくれる一曲である。静かな夜に聴いてみたい曲である。

東大、坂村健教授が、本日付け日経経済教室で日本の技術戦略強化を主張しておられるが、まさにそれを痛感する。世界市場での成功を狙うためには、国のリードが必要であると同時に、企業サイドもグローバルスタンダード化を意識した技術戦略が求められている。(注)著書「グローバルスタンダードと国家戦略」要参照。
サックスプレイヤーの織田浩司さんのアルバム”Pieces of the Moon”の一曲目に”Liebe”というのがあるが、私はこれが気に入っている。静かに未来へ向けて歩み出すような、落ち着いていながら伸びやかな雰囲気が心地よい。ややスローなテンポなので自分でも吹けそうな感じがして、チャレンジしてみたいと思っている。

しばらく前になるが、浅田次郎の蒼穹の昴を読んだ。清朝末期、時代の波に翻弄されながらも、熱く生きた春児と文秀の生きざまに感動した。また、この物語を通じて、清朝末期の政治的動乱を学ぶことができるとともに、官僚と宦官の世界がどのようなものか垣間見ることができた。限りなく壮大なドラマであり、どこまでが真実なのか知りたくなってしまう。