これは2006年11月15日付けの小文である。ちょうど富山県高岡市で子どもたちが集団で
行方不明となった時に書かれた。もう9年前の話である。第一次安倍内閣は「美しい国」
を標榜していた。
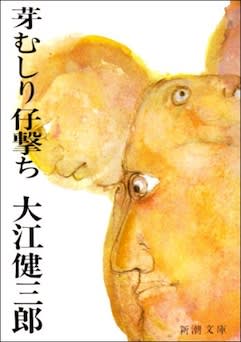
富山県高岡市の児童養護施設の男子中学生、小学生8人が、集団登校したまま行方不明となったという。そのニュースを聞きながら、大江健三郎の「芽むしり仔撃ち」を思い浮かべた。「芽むしり仔撃ち」は大江の青年期に書かれた最高傑作で、瑞々しくも悲しい作品であった。
また村上龍の「希望の国のエクソダス」を想い出した。
翌日未明、施設から20キロ離れた場所で彼等は発見された。彼等は富山市内の雨の県道を歩き続けた。その夜は駐車中のトラックの荷台で眠っていたという。子どもたちの一番上は中学3年生、一番下は小学2年生である。半袖半ズボンの子どもたちもいた。集団の家出らしい。
家庭に何らかの問題が在ってか、あるいは両親も引き取り手もないためか、養護施設以外に帰る家はない子どもたちの家出なのであった。家なき子らのエクソダスである。
昨年春、演出家のナガノユキノさんと万博会場に下見した帰りの車中、芝居や小説の話しで盛り上がった。
唐突に彼女が「芽むしり仔撃ち」について、あれほど優れた作品はないと言った。本当に好きな作品らしい。私は直ちにその作品の素晴らしさに賛同し、その昔、作者の大江健三郎には無断で「芽むしり仔撃ち」の映画用の脚本を書いたことがあると伝えた。ぜひ読ませて欲しいと言われて、お渡しする約束をしたが未だ果たしていない。
帰宅後に、原稿用紙に清書したものを探したがどうしても見当たらず、古びて黄ばんだ藁半紙20数枚に、汚い小さな字でビッシリと書き込んだ下書きしか残っていなかったからである。それをお見せするわけにはいくまい。
だいぶ以前、TVドラマ「金八先生」が評判になっていた頃、その偽善的セリフとストーリーにうんざりした。そのときは番組に強い反発を感じたが、家庭に流されるテレビとしては、ああいうストーリーしか成り立たないのだろう。
灰谷健次諸の児童文学もそうだが、「金八先生」も、どこか子どもたちに阿っているように思える。
大人たちは子どもたちをどう導こうというのか、またどう管理しようというのか。大人たちの偽善が、子どもたちを落胆させ反抗を招くのだ。大人たちはいち早く、その反抗の芽、大人の常識と管理から外れる芽を、摘もうとするのである。子どもたちは「隔離され」「捨てられる」のだ。
その頃の深刻な教育問題の本質をテーマとするなら、「芽むしり仔撃ち」を映画化したほうが、よほど強い衝撃を与え得るだろうと考えて、私が勝手に脚本化したのである。…
「芽むしり仔撃ち」とは、大人たちに見捨てられた少年たちの絶望と憤怒と、自分たちの国をつくり生き残らんとする意志と、彼等(悪い芽)を摘まんとする大人たちの残酷な欺瞞の物語なのである。
「芽むしり仔撃ち」は今も荒廃した教育問題、大人たちの姿勢を激しく撃つ、大江健三郎畢生の名作と断言する。
以下は私の脚本の中での科白である。無論原作の通りではない。また原作本を引っ張り出せる状況にない。
…南という少年と、私という主人公の少年の間で交わされる会話である。
南 「俺は、今このままここにいても、どこか遠くに行っても、同じだと
思うんだ。…だから俺は、どこか遠くに行こうと思うんだ…」
私 「南へかい?」
南 「ああ」
少年の南という名は本名ではない。少年がいつも「俺は南へ行きたい」と言っていることから付いた渾名なのである。
そう言えば「どこでもいい、どこでもいい、この世界の果てならば」と詩った詩人はボードレールだったか。どうしても思い出せない。
村上龍の「希望の国のエクソダス」は2000年に発表された。子どもの世界もインターネットやメールでつながる時代である。ある日突然8人ならぬ80万人の中学生たちが不登校におよぶ。中学生による独立国の建国…。国会に召還されたリーダーの中学生の少年が言う。
「この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。ただ希望だけがない」
「…はっきりしているのは、今のこの国と同じで、養鶏場には希望だけがないということです」
安倍晋三は「芽むしり仔撃ち」と「希望の国のエクソダス」を必読すべきである。教育基本法を改正して、愛国アイデンティティを叩き込んでも、この国の子どもたちに希望は見えてこないだろう。















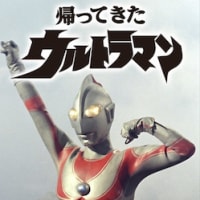
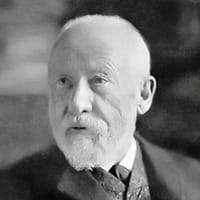
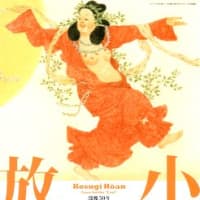


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます