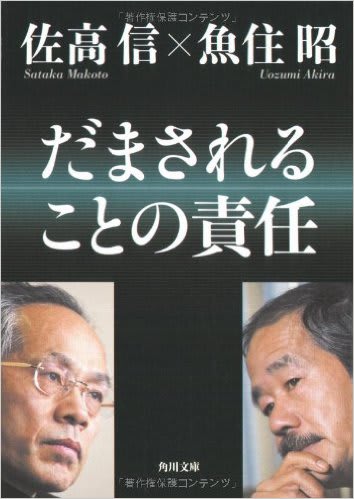だいぶ以前、よくセミナー、講演会なるものの企画やブッキング、実施の仕事を請け負っていた。広告代理店もクライアントも、よくTVで顔を見かける著名人のブッキングを好んだ。私の個人的意見、あるいは内心では下らないと思っている先生方がよく決まった。十人くらい実名を挙げたいが…やはり差し障りがあるので止めておく。
ただ話の行きがかり上、申し訳ないがお二人の名前を挙げさせていただく。長谷川慶太郎先生、三原敦雄先生である。その講演の 内容は「カネカネトーシ、カネカネトーシ…」と蝉の鳴声に似ていた。
三原先生は何度もお世話になり、個人的にはその気さくなお人柄が好きである。 しかし私の中 に「おかしい」という強い違和感があった。一年二年経ち、やがてバブルが弾けた。当然である。特に長谷川慶太郎先生は、軽薄にバブルを煽った戦犯の一人である。
アメリカの「製造」業がその拠点を人件費の安い海外に続々と移転した。象徴的な例はナイキである。本国ではデザインとマネジメントをするだけなのである。 こうしてアメリカの製造業は空洞化した。チマチマとした物作りの利益などたかが知れている。日本は自国の販売価格より安い価格で輸出してくる。いわゆる内外価格差である。日本を急追する韓国、台湾は安い人件費という競争力で輸出攻勢をかけてくる。さらにマレーシア、タイや中国などが続く。
それらとの競争は愚かである。製造は彼等に任せる。アメリカの製造はジャマイカやハイチ、インドネシア、フィリピン等の最貧国に作らせればよい。それより世界の金融を牛耳るのだ。こうしてアメリカは製造業から金融とサービスにシフトしたのである。これがアメ リカの戦略だった。金融と言っても、金を貸しチマチマと金利を稼ぐのではたかが知れている。新しい金融商品はデリバティブである。そして美味しいのは投機である。「金融工学」ともてはやされるギャンブルである。ワンクリックで数十万ドル、時に数億ドルの利益が可能なのだ。…これはおかしい。こういう経済システムそのものが、狂っているのだ。
日本のバブルが弾ける前の話である。ある著名な経済評論家や東大の経済学の教授が、TVなどで明るい持論を展開していた。日本は技術立国である、 その高い技術を海外に売るというのである。よく聞けば、その高い技術の「製品」を海外に売るという話ではない。彼等の言う「技術」を売るというのは「技術移転」をいうのである。簡単に言えば製造 システムを売り、さらに技術料、技術指導料、技術コンサル料を稼ぐのである。私は強い違和感を覚えた。海外の優れた技術はどんどん導入すべきである。しかし海外より優れた日本の技術は移転してはならないと思うのだ。 技術が日本の競争力なら絶対「技術移転」してはならないのだ。
さて、アメリカを追うように、日本も人件費の安い国々に生産拠点を移しはじめた。技術移転、生産拠点移転である。これらの企業は日本の雇用に何ら役立っていない。こうして製造業の空洞化が進んだ。
さらに日本もアメリカの模倣をしてこれからは「金融サービス」だと後を追った。しかしたちまちアメリカ主導のBIS規制の罠にかけられ、日本の銀行は苦境に追い込まれていった。そのため貸し渋りに拍車がかかり、景気の浮揚が図れなかった。
また日本の金融機関は「金融工学」…このババ抜きのようなデリバティブ、投機に弱かった。さらにアメリカ型の金融投機は世界各国に金融危機を拡散し、つい にリーマンショックを引き起こした。当然の帰結である。この強欲金融資本主義は、懲りることなく再びショックを起こすことだろう。
昨年タイで洪水が起こり、これが長引いた。すると日本の有名企業の製品が日本に入ってこなくなった。ある日本の半導体メーカーだったと思うが、洪水で生産が停まったため、日本国内で代替生産することにした。ところが日本国内には若い派遣労働者しかおらず、彼等はほとんど技術がない。そのためタイ人従業 員(熟練 工)を日本に呼び寄せ、日本人の派遣労働者の技術指導に当たらせたのである。かつてタイ人を指導した熟練工はもはや日本には存在していないのだ。これは象徴的なことである。これが日本の技術の現実なのだ。…何が日本は技術立国だ、何が物づくりの国だというのだ。これが製造業、物づくり、技術の空洞化である。
売国奴的小泉やアメリカの手先竹中屁蔵らによって規制緩和が唱えられ、社会はこれまでの知恵を愚弄され、コストカットの名目で社会のセーフティネットを破壊された。国際競争力の名分の元に賃金が抑えられ、いつでも気兼ねなく解雇できる雇用に関する規制緩和が、大量の派遣労働者を生み、大量の貧困を生んだ。
いい気になって海外に技術移転し、さらに生産拠点を海外に移し、日本の雇用には全く寄与せず、移転先の国に技術を盗まれ、キャッチアップされる。 技術の高さが比較優位だった日本が、人件費の安さが国際競争力だったこれらの国に技術で並ばれ、さらにその技術の継承もなく、その技術で超された。
…こんな売国奴的財界がまた亡国のTPP(※)をごり押しし、原発ゼロなら電気代が上がるから海外に生産拠点を移さざるを得ないと政府を恫喝する。
ふん、生産拠点を中国などに移しているから、焼き討ちにも遭うのだ。…そうしたら工場の門扉や店舗の入り口に中国国旗を掲げていた。そうかもはや日本企業ではないのか。こんな企業、日本でも不買運動をすべきである。
(※)ちなみにTPPは途中からアメリカが乗っ取って主導権を握った。アメリカは再び日本を罠にはめるだろう。
今年の春頃だったと思うが、NHKの「おはよう日本」が珍しく企業名を出して特集を伝えた。ビジネスジェット機をつくるホンダエアロインク(ホンダエアクラフトカンパニー)である。ホンダ全額出資の子会社であるという。自動車で研鑽した技術が活かされ、広い客席を実現(主翼上面にエンジンを配置) し、受注も順調だという。社長は日本人の四十代の技術者である。日本の優れた物づくりの技術が、高らかに報告されていた。
しかしよく聞いていると、本社も工場もノースカロライナ州である。社長一人が日本人で、従業員はほとんどアメリカ人であるという。日本資本に違いないが、これはアメリカの会社であって日本企業とは言いかねる。日本の雇用には何の貢献もしてい ないのだ。これで日本(人)にこの技術の集積や継承が可能なのだろうか。工場で直接製造に携わっている日本人は誰もいないのだ。
(この一文は2012年7月22日に書いたものである。)