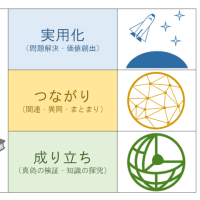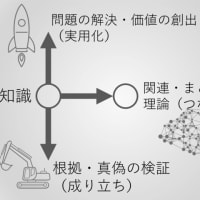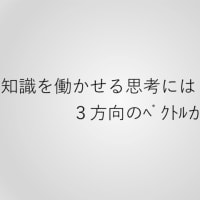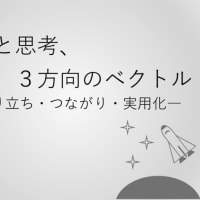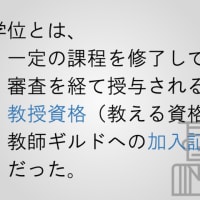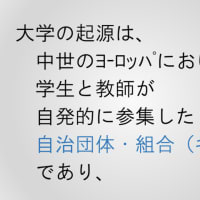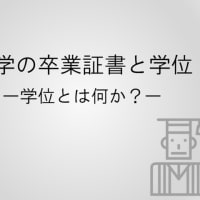<学位論文>
注意欠陥多動性障害児の注意制御における動機づけに関する認知心理学的基礎研究
藤田英樹
筑波大学博士 (心身障害学) 学位論文 (甲第5061号)
<内容>
注意欠陥/多動性障害(ADHD)は児童期に多くみられる発達障害の1つであり、成人期以降の予後は多様であり、二次的障害を予防するためにも早期からの適切な支援が必要とされる。
ADHDは不注意、多動性ー衝動性の3つの臨床症状を示す医学的診断概念である。ADHD研究の関心は、歴史的に見て、多動性→不注意→衝動性の順に変遷した。現在のADHD研究はADHDの衝動性に注目しており、衝動性の基礎要因として、反応抑制、実行機能ならびに動機づけの3つが挙げられた。ADHD認知理論としては、反応抑制理論(Barkley)、認知エナジェティックモデル(Sergeant)およびデュアルパスウェイモデル(Sonuga-Barke)の3つが代表的である。
本研究では、ADHD児の反応抑制を含めた遂行成績が報酬の動機づけにより改善することから、「遂行制御を働かせるために必要となる動機づけの困難」であることを考察した。ADHD児の反応抑制とは、運動抑制ではなく、尚早な反応決定と運動活性亢進の組み合わせとして説明される。
さらにADHD児の動機づけ特性とは、「努力を要する動機づけ(effort エフォート)の自己調節(self-regulation)困難」と、その困難を努力を要さずに得られる外的動機づけにより補償しようとすることである。
ADHD児の示す臨床症状とは、努力を要する動機づけの低さによる低遂行そのものに加えて、その動機づけの低さを補償しようとする行動(よそ見・立ち歩きなど)も含まれると考えられる。このことは、ADHDの古典的理論として知られていたoptimal stimulation理論(ADHDは過剰活性ではなく、過少活性の状態であり、より多くの刺激を必要とする)とつながっている。