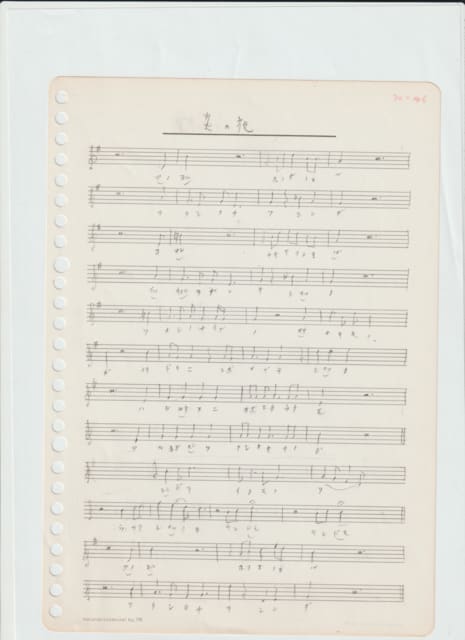ウロシだった。
~動物物語1
小学一年生から二年生になるとき、クラス替えはなく、担任も同じだった。妙に厳しい女教師で、私は緊張の日々を送っていた。教室でラジオ放送を聞かされたとき、流れてくる音楽に合わせて袖の金属のボタンで机を叩いた。何度注意されても止められない。音楽に合わせて腕が勝手に動いてしまうのだ。教室から追い出された。建物の外の犬走りに立っていると、窓から生徒たちが「先生が戻れと言っているよ」と声を掛けてくれたが、本人は顔さえ見せなかった。
彼女の笑顔を見た人は誰もいなかったそうだ。後に、四十代で初めて結婚したとき、人々は初めて彼女の笑顔を見たという。
私は彼女に使い走りをやらされたことがある。授業中、上級生のクラスに独りで乗り込んで、そのクラスの生徒の悪戯を非難したのだ。私自身が彼らによって迷惑を蒙ったわけではない。教師に言われた通りのことを口にしただけだ。私は彼女の使い捨てだったようだ。鉄砲玉。
この話が母に伝わり、私に聞いてきた。
「本当? 勇気があるのね」
返事をする気力もなく、私は泣いた。母は「褒めているのに、なぜ、泣くの」と、妙な笑いを浮かべた。彼女は私を自慢の種にしたかったらしい。私が泣こうが苦しもうが、気にしない。そういう人だった。
大人は私を利用するためだけに近づく。言葉にして考えたわけではないが、そんな思いが七歳頃に固まった。
三年生になってクラス替えがあり、担任が変った。新しい担任はおどおどしがちな私を憐れんでくれるようで、ほっとしていたのだが、その気分が突然消えた。
私にとっては大事件だ。
初夏の明るい午後、国語科の授業で、ある生徒が「動物物語」を「ドウブツブツゴ」と読んでしまった。教師は、ただ笑って、生徒を着席させ、何の説明もせずに進んだ。私はひやりとした。あの生徒の悔しそうな、困ったような横顔を、今もたまに思い出す。彼だって、「物語」を「ものがたり」と読むことぐらい、知っていたのだろう。だが、〈音読みで統一するのが正式〉と勘違いしたのかもしれない。褒められると思ったら、笑われてしまった。そんなふうに想像される。
「物語」を、なぜ、「ブツゴ」と読んではならないのか。なぜ、教師はそのことについて説明をしないのか。優しい先生が、急に冷たい人間に思えてきた。私だって、いつ、あんなふうに突き放されるか、知れない。教師は、やはり信用できない。
(終)