いろんなひとがいると思うけど、
私は、幼い頃から、
私はどこから来たの?
この家はいつからあったの?
お父さんはどんな子供だったの?
お母さんはどんな学生時代を過ごしたの? と、ルーツ好きな子供でした。
そのため、中学1年の時には、先祖探しというのを夏休みの課題にし、
父も母も祖父も知らない、
思わぬ・・・なんとやら
 ・・・を見つけ、
・・・を見つけ、
その後も、母方の曽祖母の先祖に行きあたってみたら・・・
ビックリする事実が出て・・と
でも・・・そんなことが好きでした。
ところが、その・・・直近のルーツ、父や母、祖父や祖母は、
ドラマ以上にドラマな人生 を送ってきた人たちで、
を送ってきた人たちで、
私はそれを知ることで、いろんな思いを知りました。
そのことはいずれ、言葉にしようと思っていますが・・・。
私自身に降りかかった様々なできごとに、
私がどうにか負けきらず立ち上がれたのは、
(正確にはまだ治っていないので、途中だけれど・・・)
『それでも、笑っていられる』のは、
そうした父母の強さがお守りになってきたからだと思うから・・・
ということで、
この本、角田光代さんの『ツリーハウス』は、
特別な思いで、読みました。

おはなしは、
東京のとある場所で中華料理店<翡翠飯店>を営む一家三代の、
戦時中から現在までを描いた長編小説です。
翡翠飯店は、戦後良嗣(孫)の祖父母が始めた飲食店。
ある日、祖父が亡くなったことがきっかけで祖母が変わり始めます。
うちにいるのに『うちに帰りたい』と言うようになってしまったのです。
若い頃満州で暮らしていたという祖母。
その話を聞いた良嗣は祖母の『うち』を探しに、
祖母とうちに同居している伯父の大二郎と一緒に旧満州へ。
旧満州に来ても何も話さない祖母。
動かない祖母が、やっと動き出し、わかっていく『過去』。
<人生にもしなんてない。あるのは無だけだ。>
満州での祖父母の生活。
満州からの引き揚げの描写は、キツイ。
生きるとは、本当に大変なことだと思います。
いろいろな意味で、昔と今は大きく違うけれど、
自分で自分を生きるのは、どの時代も大変なことだと、
あらためて、言葉にしてみました。
<謎の多い祖父の戸籍>
祖母のヤエさんの『生きる』が、子育てを通して見えてきます。
<逃げることしか教えることができなかった>
後悔ともとれるその言葉は、
私の祖父の『生きる』と重なります。

小説の中の人物に、特別な人が出ているわけではありません。
その時代には、ヤエさんのように、
時代の濁流の中でもがき或いは流されて生きたひとが、たくさんいたことでしょう。
そして<逃げて>生きたひとたちも家族を作り子どもを産む。
家(ハウス)は、家族が家族を作り、
枝分かれして、大きな大きな木に成長していくのです。
祖母は、祖父を亡くしたことで、
その大きな木(うち)に、幹(こころ)に触れたのでしょうか。
『うちにかえりたい』
家族は、そこにあるもので、あるものじゃない。
<血>という絆があったとしても、
それは絶対であり、絶対ではないのです。
心を、手を、つなぎ<続け>ていく、
バトンを渡していくことは、当たり前にできることではないのです。
ヤエさんが、振り返った苦い苦しい過去は、
旧満州の<うち>に戻ることで見えたものは、
彼女の孫である良嗣の目や心を通して、
祖父母が建てたツリーハウスを・・・育てていくのだと感じました。
<ルーツ>を探ると、心の根っこが見える気がします。




私は、幼い頃から、
私はどこから来たの?
この家はいつからあったの?
お父さんはどんな子供だったの?
お母さんはどんな学生時代を過ごしたの? と、ルーツ好きな子供でした。
そのため、中学1年の時には、先祖探しというのを夏休みの課題にし、
父も母も祖父も知らない、
思わぬ・・・なんとやら

 ・・・を見つけ、
・・・を見つけ、その後も、母方の曽祖母の先祖に行きあたってみたら・・・
ビックリする事実が出て・・と

でも・・・そんなことが好きでした。
ところが、その・・・直近のルーツ、父や母、祖父や祖母は、
ドラマ以上にドラマな人生
 を送ってきた人たちで、
を送ってきた人たちで、私はそれを知ることで、いろんな思いを知りました。
そのことはいずれ、言葉にしようと思っていますが・・・。
私自身に降りかかった様々なできごとに、
私がどうにか負けきらず立ち上がれたのは、
(正確にはまだ治っていないので、途中だけれど・・・)
『それでも、笑っていられる』のは、
そうした父母の強さがお守りになってきたからだと思うから・・・
ということで、
この本、角田光代さんの『ツリーハウス』は、
特別な思いで、読みました。

おはなしは、
東京のとある場所で中華料理店<翡翠飯店>を営む一家三代の、
戦時中から現在までを描いた長編小説です。
翡翠飯店は、戦後良嗣(孫)の祖父母が始めた飲食店。
ある日、祖父が亡くなったことがきっかけで祖母が変わり始めます。
うちにいるのに『うちに帰りたい』と言うようになってしまったのです。
若い頃満州で暮らしていたという祖母。
その話を聞いた良嗣は祖母の『うち』を探しに、
祖母とうちに同居している伯父の大二郎と一緒に旧満州へ。
旧満州に来ても何も話さない祖母。
動かない祖母が、やっと動き出し、わかっていく『過去』。
<人生にもしなんてない。あるのは無だけだ。>
満州での祖父母の生活。
満州からの引き揚げの描写は、キツイ。
生きるとは、本当に大変なことだと思います。
いろいろな意味で、昔と今は大きく違うけれど、
自分で自分を生きるのは、どの時代も大変なことだと、
あらためて、言葉にしてみました。
<謎の多い祖父の戸籍>
祖母のヤエさんの『生きる』が、子育てを通して見えてきます。
<逃げることしか教えることができなかった>
後悔ともとれるその言葉は、
私の祖父の『生きる』と重なります。

小説の中の人物に、特別な人が出ているわけではありません。
その時代には、ヤエさんのように、
時代の濁流の中でもがき或いは流されて生きたひとが、たくさんいたことでしょう。
そして<逃げて>生きたひとたちも家族を作り子どもを産む。
家(ハウス)は、家族が家族を作り、
枝分かれして、大きな大きな木に成長していくのです。
祖母は、祖父を亡くしたことで、
その大きな木(うち)に、幹(こころ)に触れたのでしょうか。
『うちにかえりたい』
家族は、そこにあるもので、あるものじゃない。
<血>という絆があったとしても、
それは絶対であり、絶対ではないのです。
心を、手を、つなぎ<続け>ていく、
バトンを渡していくことは、当たり前にできることではないのです。
ヤエさんが、振り返った苦い苦しい過去は、
旧満州の<うち>に戻ることで見えたものは、
彼女の孫である良嗣の目や心を通して、
祖父母が建てたツリーハウスを・・・育てていくのだと感じました。
<ルーツ>を探ると、心の根っこが見える気がします。














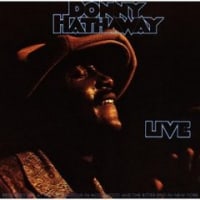
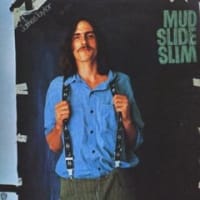
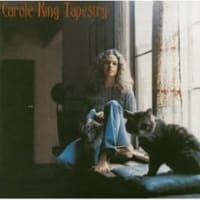
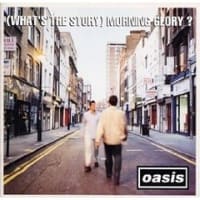
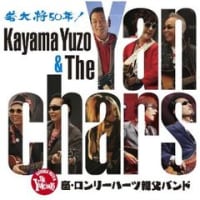
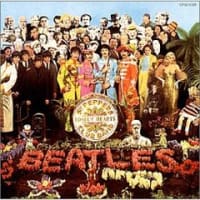



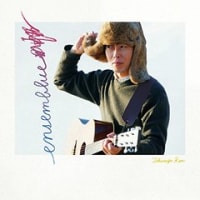
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます