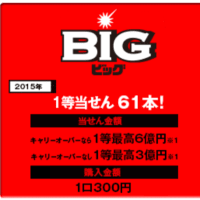12/16(土)そごう千葉店9Fにある「こだわり趣味の街」に行った。手作りの店が沢山あり、自分の好きな切手・コインの店もある。またヒゲタ醤油・ヤマサ醤油・野田醤油(キッコーマン)についての由来も書かれてあった。
ヒゲタ醤油は禅僧心地覚心が紀州由良(和歌山県日高郡)に興国寺を開き、味噌から1616年田中玄蕃が溜り醤油の製造販売を始めたとの事。
ヤマサ醤油は1645年濱口儀兵衛が、紀州(和歌山県)から銚子(千葉県)へ移り、醤油の製造販売を始めたとの事。ヤマサ醤油の商標の「サ」は当初濱口儀兵衛の「キ」を採用したが、紀州徳川家の船印と同じだった為、「キ」を横にし「サ」にしたとの事。
キッコーマン(旧野田醤油)は1558年~1570年飯田市郎兵衛が製造販売を始めたとの事。キッコーマンは「亀甲萬(鶴は千年、亀は萬年から)」。
日本の醤油の発祥地は紀州湯浅(和歌山県有田郡湯浅町)で八百年の歴史がある。紀州湯浅は醤油発祥の地として有名だが、その起源は鎌倉時代(1234年)遡る。 紀州由良禅寺「興国寺」の開祖「法燈円明國師(ほうとうえんめいこくし)」が、中国(南宋)の金山寺から持ち帰った金山寺味噌(経山寺味噌)が、当時、興国寺では野菜と大豆から作られる金山寺味噌を健康食として盛んに醸造され、やがて湯浅周辺の山漁村に伝わった。
金山寺味噌を醸造する際、使われる瓜や茄子などの、野菜からの浸透圧によって余分な水分がしみでてくる。本来はカビや腐敗の原因となるとして捨てられていた。ところがこの汁を調味料として使ってみるとなかなか美味で、そこで初めからこの汁を利用するつもりでつくれば、「新しい醤(ひしお)」つまり調味料ができるのではないかと考え、改良に改良を重ね、やがて醤油となった。これが日本における醤油の起源あると伝えられている。
湯浅の気候風土が醤油の醸造に極めて適していた事から、醤油の醸造が本格的に始められ、江戸時代に入っては、紀州徳川家の保護を受け湯浅醤油が育った。
江戸の初期、上方醤油は米の3~4倍はする高価な商品だったが、堺や大坂から船で大量に江戸に送られ、関東醤油の倍近くの値段で売られていたという記録もある。そのころの江戸はまだ発展途上にあり、食生活を含めた文化の中心は上方だった。
当時、清酒や醤油、塩等上方の優れた産物が江戸に送られていた。それらは「下り酒」「下り醤油」等と呼ばれて珍重された。反対に品質の良くない醤油は下る事が出来なかったと言われていた。つまらないモノやコトの事を「下らない」(江戸弁)というのはこの時代の名残だ。また地元の酒・醤油は「下りでない」ということから「下らない」となった説もある。
江戸時代中期を過ぎると、関東の常陸・下総・上総・相模などで、醤油づくりが盛んになり大きく発展した。味も江戸の人々の嗜好に合わせて、今日の濃口醤油に近いものが生産されるようになった。そして次第に上方からの下り醤油は駆逐され、江戸の醤油は関東ものが占める状態になっていった。
温暖多湿で夏冬の気温差が少ないという気候が醤油造りに欠かせない麹菌や酵母など微生物の生育に適している事と、大消費地の江戸へは利根川、江戸川などの水運を利用して製品を運ぶことができた。また、原料については、常陸の大豆、小麦が入手し易い地理的な位置にあった。このような地理的条件の元、江戸の町の発展に伴って、千葉県の醤油も発展していったそうだ。
湯浅醤油:http://www.yuasasyouyu.co.jp/
湯浅醤油工場見学:http://www.yuasasyouyu.co.jp/kouzyoukengaku.htm
湯浅醤油の由来:http://homepage3.nifty.com/yuasashoyu/yurai.html
ヒゲタ醤油:http://www.higeta.co.jp/
ヒゲタ醤油工場資料館見学:http://www.higeta.co.jp/museum/factory/kengaku.html
ヤマサ醤油:http://www.yamasa.com/
ヤマサ醤油施設見学ガイド:
http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=924
キッコーマン(旧野田醤油):http://www.kikkoman.co.jp/
キッコーマン工場案内:http://www.kikkoman.co.jp/soyworld/school/8/index.html
Jandy'Blog:うなぎ「茂利戸家(もりとや)」#2千葉県銚子と和歌山県の関係:
http://blog.goo.ne.jp/jandy7322/e/
c349fcdb244295a499437d795dcb502c
宜しければクリックして下さい。 日記@BlogRanking へ 人気blogランキングへ
ヒゲタ醤油は禅僧心地覚心が紀州由良(和歌山県日高郡)に興国寺を開き、味噌から1616年田中玄蕃が溜り醤油の製造販売を始めたとの事。
ヤマサ醤油は1645年濱口儀兵衛が、紀州(和歌山県)から銚子(千葉県)へ移り、醤油の製造販売を始めたとの事。ヤマサ醤油の商標の「サ」は当初濱口儀兵衛の「キ」を採用したが、紀州徳川家の船印と同じだった為、「キ」を横にし「サ」にしたとの事。
キッコーマン(旧野田醤油)は1558年~1570年飯田市郎兵衛が製造販売を始めたとの事。キッコーマンは「亀甲萬(鶴は千年、亀は萬年から)」。
日本の醤油の発祥地は紀州湯浅(和歌山県有田郡湯浅町)で八百年の歴史がある。紀州湯浅は醤油発祥の地として有名だが、その起源は鎌倉時代(1234年)遡る。 紀州由良禅寺「興国寺」の開祖「法燈円明國師(ほうとうえんめいこくし)」が、中国(南宋)の金山寺から持ち帰った金山寺味噌(経山寺味噌)が、当時、興国寺では野菜と大豆から作られる金山寺味噌を健康食として盛んに醸造され、やがて湯浅周辺の山漁村に伝わった。
金山寺味噌を醸造する際、使われる瓜や茄子などの、野菜からの浸透圧によって余分な水分がしみでてくる。本来はカビや腐敗の原因となるとして捨てられていた。ところがこの汁を調味料として使ってみるとなかなか美味で、そこで初めからこの汁を利用するつもりでつくれば、「新しい醤(ひしお)」つまり調味料ができるのではないかと考え、改良に改良を重ね、やがて醤油となった。これが日本における醤油の起源あると伝えられている。
湯浅の気候風土が醤油の醸造に極めて適していた事から、醤油の醸造が本格的に始められ、江戸時代に入っては、紀州徳川家の保護を受け湯浅醤油が育った。
江戸の初期、上方醤油は米の3~4倍はする高価な商品だったが、堺や大坂から船で大量に江戸に送られ、関東醤油の倍近くの値段で売られていたという記録もある。そのころの江戸はまだ発展途上にあり、食生活を含めた文化の中心は上方だった。
当時、清酒や醤油、塩等上方の優れた産物が江戸に送られていた。それらは「下り酒」「下り醤油」等と呼ばれて珍重された。反対に品質の良くない醤油は下る事が出来なかったと言われていた。つまらないモノやコトの事を「下らない」(江戸弁)というのはこの時代の名残だ。また地元の酒・醤油は「下りでない」ということから「下らない」となった説もある。
江戸時代中期を過ぎると、関東の常陸・下総・上総・相模などで、醤油づくりが盛んになり大きく発展した。味も江戸の人々の嗜好に合わせて、今日の濃口醤油に近いものが生産されるようになった。そして次第に上方からの下り醤油は駆逐され、江戸の醤油は関東ものが占める状態になっていった。
温暖多湿で夏冬の気温差が少ないという気候が醤油造りに欠かせない麹菌や酵母など微生物の生育に適している事と、大消費地の江戸へは利根川、江戸川などの水運を利用して製品を運ぶことができた。また、原料については、常陸の大豆、小麦が入手し易い地理的な位置にあった。このような地理的条件の元、江戸の町の発展に伴って、千葉県の醤油も発展していったそうだ。
湯浅醤油:http://www.yuasasyouyu.co.jp/
湯浅醤油工場見学:http://www.yuasasyouyu.co.jp/kouzyoukengaku.htm
湯浅醤油の由来:http://homepage3.nifty.com/yuasashoyu/yurai.html
ヒゲタ醤油:http://www.higeta.co.jp/
ヒゲタ醤油工場資料館見学:http://www.higeta.co.jp/museum/factory/kengaku.html
ヤマサ醤油:http://www.yamasa.com/
ヤマサ醤油施設見学ガイド:
http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=924
キッコーマン(旧野田醤油):http://www.kikkoman.co.jp/
キッコーマン工場案内:http://www.kikkoman.co.jp/soyworld/school/8/index.html
Jandy'Blog:うなぎ「茂利戸家(もりとや)」#2千葉県銚子と和歌山県の関係:
http://blog.goo.ne.jp/jandy7322/e/
c349fcdb244295a499437d795dcb502c
宜しければクリックして下さい。 日記@BlogRanking へ 人気blogランキングへ